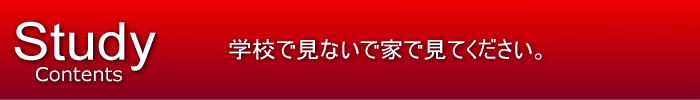Charlotte's Web 15
ⅩⅤ. The Crickets
(15.コオロギ)
The Crickets sang in the grasses. They sang the song of summer's ending, a sad, monotonous song. "Summer is over and gone," they sang. "Over and gone, over and gone. Summer is dying, dying."
(草のかげでコオロギが鳴いていました。コオロギたちは、かなしげな一本調子で、夏のおわりの歌をうたっていたのです。「夏がおわる。おわる、おわる。夏がすぎてゆく」と、コオロギはうたっていました。)
The crickets felt it was their duty to warm everybody that summertime cannot last forever. Even on the most beautiful days in the whole year--the days when summer is changing into fall--the crickets spread the rumor of sadness and change.
(コオロギたちは、夏がいつまでもつづくわけではないということを知らせるのが、自分たちの仕事だとこころえていました。一年でいちばん美しい季節-夏がおわっ威漱になろうとする時期-なのに、やがてかなしい変化がおとずれることを、コオロギたちはみんなに知らせていたのです。)
Everybody heard the song of the crickets. Avery and Fern Arable heard it as they walked the dusty road. They knew that school would soon begin again. The young geese heard it and knew that they would never be little goslings again. Charlotte heard it and knew that she hadn't much time left. Mrs. Zuckerman, at work in the kitchen, heard the crickets, and a sadness came over her, too. "Another summer gone," she sighed. Lurvy, at work building a crate for Wilbur, heard the song and knew it was time to dig potatoes.
(だれもが、コオロギの歌をきいていました。土ぼこりのたつ道を歩いていたエイヴリーとファーンはそれをきいて、学校がもうすぐはじまることを思いだしました。ガチョウの子どもたちはそれをきいて、自分たちがもう小さなひな鳥ではないのを知りました。シャーロットはそれをきいて、もうあまり時間がのこされていないのだと覚悟しました。台所で働いていたザッカーマンのおばさんは、コオロギの声をきくとわびしくなって、「また夏がいってしまうんだね」と、ため息をつきました。ウィルバー用の木箱をつくっていたラーヴィーは、コオロギの声をきいて、そろそろジャガイモをほりあげなくちゃ、と思っていました。)
"Summer is over and gone," repeated the crickets. "How many nights till frost?" sang the crickets. "Good-bye, summer, good-bye, good-bye!"
(「夏がすぎてゆく」コオロギはくりかえしました。「霜がおりるのも、もうすぐだ」コオロギはうたいました。「夏よ、さよなら、さよなら、さよなら!」)
The sheep heard the crickets, and they felt so uneasy they broke a hole in the pasture fence and wandered up into the field across the road. The gander discovered the hole and led his family through, and they walked to the orchard and ate the apples that were lying on the ground. A little maple tree in the swamp heard the cricket song and turned bright red with anxiety.
(羊たちはコオロギの声をきくと、不安にかられて牧草地の垣根に穴をあけ、そこをくぐりぬけて道路の向こうの畑までさまよいでていきました。その穴をみつけたガチョウのおじさんは、一家をひきつれて外へでると果樹園までいき、下に落ちていたリンゴを食べました。沼地の小さなカエデの木は、コオロギの歌をきいて胸がしめつけられ、まっ赤な色にかわりました。)
Wilbur was now the center of attraction on the farm. Good food and regular hours were showing results: Wilbur was a pig any man would be proud of. One day more than a hundred people came to stand at his yard and admire him. Charlotte had written the word RADIANT, and Wilbur really looked radiant as he stood in the golden sunlight. Ever since the spider had befriended him, he had done his best to live up to his reputation. When Charlotte's web said SOMEPIG, Wilbur had tried hard to look like some pig. When Charlotte's web said TERRIFIC, Wilbur had tried to look terrific. And now that the web said RADIANT, he did everything possible to make himself glow.
(ウィルバーは、今では農場のよびものになっていました。おいしい食べものと規則正しい生活のおかげで、ウイルバーはだれもがじまんに思うようなブタに成長していました。ある日、百人以上の人がウィルバーを見にやってきました。シャーロットは『ぴかぴか』という文字を書いておいたのですが、金色の日の光に照らされたウィルバーは、ほんとうにぴかぴかにかがやいていました。このクモと友だちになって以来、ウィルバーは評判をうらぎらないようにがんばってきました。シャーロットが『たいしたブタ』と書いたときには、ウィルバーはたいしたブタに見えるように、いっしょけんめい努力しました。シャーロットの巣に『すばらしい』という文字があらわれたときには、ウィルバーはすばらしく見えるように努力しました。そしてシャーロットの巣に『ぴかぴか』という文字があらわれている今、ウィルバーはじぶんがかがやいて見えるように、できるだけのことをしていました。)
It is not easy to look radiant, but Wilbur threw himself into it with a will. He would turn his head slightly and blink his long eye-lashes. Then he would breathe deeply. And when his audience grew bored, he would spring into the air and do a back flip with a half with a half twist. At this the crowd would yell and cheer. "How's that for a pig?" Mr. Zuckerman would ask, well pleased with himself. "That pig is radiant."
(ぴかぴかに見せるのは、たやすいことではありませんが、ウィルバーはせいいっぱい努力していました。頭をちょっとかしげて、長いまつげをパチパチさせます。それから大きく息をします。見物客があきてくると、ぴょんととびあがって、半回転ひねりを入れたうしろ宙がえりをしてみせました。これを見た人は、みんな大きな歓声をあげました。すると、ザッカーマンのおじさんは気をよくして、「どんなもんです?このブタはぴっかびかでしょうが?」というのでした。)
Some of Wilbur's friends in the barn worried for fear all this attention would go to his head and make him stuck up. But it never did. Wilbur was modest; fame did not spoil him. He still worried some about the future, as he could hardly believe that a mere spider would be able to save his life. Sometimes at night he would have a bad dream. He would dream that men were coming to get him with knives and guns. But that was only a dream. In the daytime, Wilbur usually felt happy and confident. No pig ever had truer friends, and he realized that friendship is one of the most satisfying things in the world. Even the song of the crickets did not make Wilbur too sad. He knew it was almost time for the County Fair, and he was looking forward to the trip. If he could distinguish himself at the Fair, and maybe win some prize money, he was sure Zuckerman would let him live.
(納屋の動物たちのなかには、これだけ注目をあつめると、ウィルバーがなまいきになるのではないかと心配する者もいました。でも、そんなことにはなりませんでした。ウィルバーはひかえめなブタで、有名になっても、いい気になったりはしなかったのです。それに、先のことがまだ少し心配でした。一ぴきのクモに自分の命を救うことができるなんて半信半疑だったからです。夜になると、わるい夢にうなされることもありました。人間が包丁や銃を持って、おそってくる夢を見るのです。でも、それはただの夢でした。昼間は、ウィルバーはたいていしあわせで、自信にみちていました。こんなに信頼できる友だちをもったブタは、ほかにいません。そして、世の中でいちばんたしかなのは友情だということを、ウィルバーは知っていました。コオロギの歌をきいても、ウィルバーはあまりさびしくなりませんでした。もうすぐ品評会がひらかれるのを知っていて、出場を楽しみにしていたからです。品評会でウィルバーが優秀と認められ、賞金でももらえれば、ザッカーマンさんは自分を生かしておいてくれるでしょう。)
Charlotte had worries of her own, but she kept quiet about them. One morning Wilbur asked her about the Fair.
(シャーロットのほうは心配ごとをかかえていましたが、それをだれにも話しませんでした。ある朝、ウィルバーは品評会のことでシャーロットにたずねました。)
"You're going with me, aren't you, Charlotte?" he said.
(「シャーロット、品評会にはついてきてくれるんでしょ?」)
"Well, I don't know," replied Charlotte. "The Fair comes at a bad time for me. I shall find it inconvenient to leave home, even for a few days."
(「さあ、どうかしら」と、シャーロットはこたえました。「ちょうど時期がわるいのよ。そのころは、たとえ二、三日でも、家をるすにするわけにはいかないんじゃないかしら」)
"Why?" asked Wilbur.
(「どうしてなの?」ウィルバーがききました。)
"Oh, I just don't feel like leaving my web. Too much going on around here."
(「ただ巣をはなれたくないのよ。いそがしい時期なの」)
"Please come with me!" begged Wilbur. "I need you, Charlotte. I can't stand going to the Fair without you. You've just got to come."
(「おねがいだから、いつしょにいってよ!そばにいてくれなきゃ、ぼく、こまっちゃうよ。いっしょじゃなきゃ、品評会なんかでられないよ。どうしたって、いってよね」ウィルバーはたのみました。)
"No," said Charlotte, "I believe I'd better stay home and see if I can't get some work done."
(「いいえ。きっと家にいて、しなきゃいけないことがあると思うの」)
"What kind of work?" asked Wilbur.
(「どんなことしなきゃいけないの?」)
"Egg laying. It's time I made an egg sac and filled it with eggs."
(「たまごを産むことよ。そろそろたまごぶくろをつくって、そのなかにたまごを産んでおかないとね」)
"I didn't know you could lay eggs," said Wilbur in amazement.
(「きみにたまごが産めるなんて、ぼく知らなかったよ」ウィルバーは、びっくりしました。)
"Oh, sure," said the spider. "I'm versatile."
(「もちろん産めるのよ。わたしは多才なの」)
"What does 'versatile' mean--full of eggs?" asked Wilbur.
(「タサイって?たまごをいっぱい持ってるってこと?」ウィルバーがたずねました。)
"Certainly not," said Charlotte. "'Versatile' means I can turn with ease from one thing to another. It means I don't have to limit my activities to spinning and trapping and stunts like that."
(「いいえ、ちがうわ。多才っていうのは、いろいろなことがかんたんにできるってことなの。糸を吐いたり獲物をつかまえたりするだけじゃないってことよ」)
"Why don't you come with me to the Fair Grounds and lay your eggs there?" pleased Wilbur. "It would be wonderful fun."
(「だったら、品評会についてきて、そこでたまごを産むってわけにはいかないの?そうしたら、おもしろいと思うけどな」)
Charlotte gave her web a twitch and moodily watched it sway. "I'm afraid not," she said. "You don't know the first thing about egg laying, Wilbur. I can't arrange my family duties to suit the management of the County Fair. When I get ready to lay eggs, I have to lay eggs, Fair or no Fair. However, I don't want you to worry about it--you might lose weight. We'll leave it this way: I'll come to the Fair if I possibly can."
(シャーロットは網をぐいっとひっぱり、糸がゆれるのをゆううつそうにながめました。「むりね。あなたは、たまごを産むってことについて、なんにも知らないんでしょ、ウィルバー。家族への義務を、品評会の予定にあわせるわけにはいかないのよ。たまごを産む用意がととのったら、品評会があろうとなかろうと、たまごを産まなくちゃいけないの。でも、心配しないでいいのよ。心配すると、体重がへっちゃうわよ。そうだわ、こうしておきましょうよ。事情がゆるすなら、わたしも品評会にいくっていうことにしておきましょう」)
"Oh, good!" said Wilbur. "I knew you wouldn't forsake me just when I need you most."
(「ああ、よかった!いちばんそばにいてほしいときに、ぼくを見捨てたりしちゃいやだよ」と、ウィルバーはたのみました。)
All that day Wilbur stayed inside, taking life easy in the straw. Charlotte rested and ate a grasshopper. She knew that she couldn't help Wilbur much longer. In a few days she would have to drop everything and build the beautiful little sac that would hold her eggs.
(その日、ウィルバーは一日じゅう、納屋のわらの上でごろごろしていました。シャーロットはひと休みして、バッタを食べました。シャーロットには、ウィルバーをたすけてあげられる日々も、もう長くはないことがわかっていたのです。もうあと何日かしたら、ほかのことはみんなさしおいて、たまごを産むための小さなたまごぶくろをつくらなければなりません。)
little sac that would hold her eggs. (その日、ウィルバーは一日じゅう、納屋のわらの上でごろごろしていました。シャーロットはひと休みして、バッタを食べました。シャーロットには、ウィルバーをたすけてあげられる日々も、もう長くはないことがわかっていたのです。もうあと何日かしたら、ほかのことはみんなさしおいて、たまごを産むための小さなたまごぶくろをつくらなければなりません。)
英文のみです。
日本語訳のみです。
Charlotte's Web 16
(15.コオロギ)
The Crickets sang in the grasses. They sang the song of summer's ending, a sad, monotonous song. "Summer is over and gone," they sang. "Over and gone, over and gone. Summer is dying, dying."
(草のかげでコオロギが鳴いていました。コオロギたちは、かなしげな一本調子で、夏のおわりの歌をうたっていたのです。「夏がおわる。おわる、おわる。夏がすぎてゆく」と、コオロギはうたっていました。)
The crickets felt it was their duty to warm everybody that summertime cannot last forever. Even on the most beautiful days in the whole year--the days when summer is changing into fall--the crickets spread the rumor of sadness and change.
(コオロギたちは、夏がいつまでもつづくわけではないということを知らせるのが、自分たちの仕事だとこころえていました。一年でいちばん美しい季節-夏がおわっ威漱になろうとする時期-なのに、やがてかなしい変化がおとずれることを、コオロギたちはみんなに知らせていたのです。)
Everybody heard the song of the crickets. Avery and Fern Arable heard it as they walked the dusty road. They knew that school would soon begin again. The young geese heard it and knew that they would never be little goslings again. Charlotte heard it and knew that she hadn't much time left. Mrs. Zuckerman, at work in the kitchen, heard the crickets, and a sadness came over her, too. "Another summer gone," she sighed. Lurvy, at work building a crate for Wilbur, heard the song and knew it was time to dig potatoes.
(だれもが、コオロギの歌をきいていました。土ぼこりのたつ道を歩いていたエイヴリーとファーンはそれをきいて、学校がもうすぐはじまることを思いだしました。ガチョウの子どもたちはそれをきいて、自分たちがもう小さなひな鳥ではないのを知りました。シャーロットはそれをきいて、もうあまり時間がのこされていないのだと覚悟しました。台所で働いていたザッカーマンのおばさんは、コオロギの声をきくとわびしくなって、「また夏がいってしまうんだね」と、ため息をつきました。ウィルバー用の木箱をつくっていたラーヴィーは、コオロギの声をきいて、そろそろジャガイモをほりあげなくちゃ、と思っていました。)
"Summer is over and gone," repeated the crickets. "How many nights till frost?" sang the crickets. "Good-bye, summer, good-bye, good-bye!"
(「夏がすぎてゆく」コオロギはくりかえしました。「霜がおりるのも、もうすぐだ」コオロギはうたいました。「夏よ、さよなら、さよなら、さよなら!」)
The sheep heard the crickets, and they felt so uneasy they broke a hole in the pasture fence and wandered up into the field across the road. The gander discovered the hole and led his family through, and they walked to the orchard and ate the apples that were lying on the ground. A little maple tree in the swamp heard the cricket song and turned bright red with anxiety.
(羊たちはコオロギの声をきくと、不安にかられて牧草地の垣根に穴をあけ、そこをくぐりぬけて道路の向こうの畑までさまよいでていきました。その穴をみつけたガチョウのおじさんは、一家をひきつれて外へでると果樹園までいき、下に落ちていたリンゴを食べました。沼地の小さなカエデの木は、コオロギの歌をきいて胸がしめつけられ、まっ赤な色にかわりました。)
Wilbur was now the center of attraction on the farm. Good food and regular hours were showing results: Wilbur was a pig any man would be proud of. One day more than a hundred people came to stand at his yard and admire him. Charlotte had written the word RADIANT, and Wilbur really looked radiant as he stood in the golden sunlight. Ever since the spider had befriended him, he had done his best to live up to his reputation. When Charlotte's web said SOMEPIG, Wilbur had tried hard to look like some pig. When Charlotte's web said TERRIFIC, Wilbur had tried to look terrific. And now that the web said RADIANT, he did everything possible to make himself glow.
(ウィルバーは、今では農場のよびものになっていました。おいしい食べものと規則正しい生活のおかげで、ウイルバーはだれもがじまんに思うようなブタに成長していました。ある日、百人以上の人がウィルバーを見にやってきました。シャーロットは『ぴかぴか』という文字を書いておいたのですが、金色の日の光に照らされたウィルバーは、ほんとうにぴかぴかにかがやいていました。このクモと友だちになって以来、ウィルバーは評判をうらぎらないようにがんばってきました。シャーロットが『たいしたブタ』と書いたときには、ウィルバーはたいしたブタに見えるように、いっしょけんめい努力しました。シャーロットの巣に『すばらしい』という文字があらわれたときには、ウィルバーはすばらしく見えるように努力しました。そしてシャーロットの巣に『ぴかぴか』という文字があらわれている今、ウィルバーはじぶんがかがやいて見えるように、できるだけのことをしていました。)
It is not easy to look radiant, but Wilbur threw himself into it with a will. He would turn his head slightly and blink his long eye-lashes. Then he would breathe deeply. And when his audience grew bored, he would spring into the air and do a back flip with a half with a half twist. At this the crowd would yell and cheer. "How's that for a pig?" Mr. Zuckerman would ask, well pleased with himself. "That pig is radiant."
(ぴかぴかに見せるのは、たやすいことではありませんが、ウィルバーはせいいっぱい努力していました。頭をちょっとかしげて、長いまつげをパチパチさせます。それから大きく息をします。見物客があきてくると、ぴょんととびあがって、半回転ひねりを入れたうしろ宙がえりをしてみせました。これを見た人は、みんな大きな歓声をあげました。すると、ザッカーマンのおじさんは気をよくして、「どんなもんです?このブタはぴっかびかでしょうが?」というのでした。)
Some of Wilbur's friends in the barn worried for fear all this attention would go to his head and make him stuck up. But it never did. Wilbur was modest; fame did not spoil him. He still worried some about the future, as he could hardly believe that a mere spider would be able to save his life. Sometimes at night he would have a bad dream. He would dream that men were coming to get him with knives and guns. But that was only a dream. In the daytime, Wilbur usually felt happy and confident. No pig ever had truer friends, and he realized that friendship is one of the most satisfying things in the world. Even the song of the crickets did not make Wilbur too sad. He knew it was almost time for the County Fair, and he was looking forward to the trip. If he could distinguish himself at the Fair, and maybe win some prize money, he was sure Zuckerman would let him live.
(納屋の動物たちのなかには、これだけ注目をあつめると、ウィルバーがなまいきになるのではないかと心配する者もいました。でも、そんなことにはなりませんでした。ウィルバーはひかえめなブタで、有名になっても、いい気になったりはしなかったのです。それに、先のことがまだ少し心配でした。一ぴきのクモに自分の命を救うことができるなんて半信半疑だったからです。夜になると、わるい夢にうなされることもありました。人間が包丁や銃を持って、おそってくる夢を見るのです。でも、それはただの夢でした。昼間は、ウィルバーはたいていしあわせで、自信にみちていました。こんなに信頼できる友だちをもったブタは、ほかにいません。そして、世の中でいちばんたしかなのは友情だということを、ウィルバーは知っていました。コオロギの歌をきいても、ウィルバーはあまりさびしくなりませんでした。もうすぐ品評会がひらかれるのを知っていて、出場を楽しみにしていたからです。品評会でウィルバーが優秀と認められ、賞金でももらえれば、ザッカーマンさんは自分を生かしておいてくれるでしょう。)
Charlotte had worries of her own, but she kept quiet about them. One morning Wilbur asked her about the Fair.
(シャーロットのほうは心配ごとをかかえていましたが、それをだれにも話しませんでした。ある朝、ウィルバーは品評会のことでシャーロットにたずねました。)
"You're going with me, aren't you, Charlotte?" he said.
(「シャーロット、品評会にはついてきてくれるんでしょ?」)
"Well, I don't know," replied Charlotte. "The Fair comes at a bad time for me. I shall find it inconvenient to leave home, even for a few days."
(「さあ、どうかしら」と、シャーロットはこたえました。「ちょうど時期がわるいのよ。そのころは、たとえ二、三日でも、家をるすにするわけにはいかないんじゃないかしら」)
"Why?" asked Wilbur.
(「どうしてなの?」ウィルバーがききました。)
"Oh, I just don't feel like leaving my web. Too much going on around here."
(「ただ巣をはなれたくないのよ。いそがしい時期なの」)
"Please come with me!" begged Wilbur. "I need you, Charlotte. I can't stand going to the Fair without you. You've just got to come."
(「おねがいだから、いつしょにいってよ!そばにいてくれなきゃ、ぼく、こまっちゃうよ。いっしょじゃなきゃ、品評会なんかでられないよ。どうしたって、いってよね」ウィルバーはたのみました。)
"No," said Charlotte, "I believe I'd better stay home and see if I can't get some work done."
(「いいえ。きっと家にいて、しなきゃいけないことがあると思うの」)
"What kind of work?" asked Wilbur.
(「どんなことしなきゃいけないの?」)
"Egg laying. It's time I made an egg sac and filled it with eggs."
(「たまごを産むことよ。そろそろたまごぶくろをつくって、そのなかにたまごを産んでおかないとね」)
"I didn't know you could lay eggs," said Wilbur in amazement.
(「きみにたまごが産めるなんて、ぼく知らなかったよ」ウィルバーは、びっくりしました。)
"Oh, sure," said the spider. "I'm versatile."
(「もちろん産めるのよ。わたしは多才なの」)
"What does 'versatile' mean--full of eggs?" asked Wilbur.
(「タサイって?たまごをいっぱい持ってるってこと?」ウィルバーがたずねました。)
"Certainly not," said Charlotte. "'Versatile' means I can turn with ease from one thing to another. It means I don't have to limit my activities to spinning and trapping and stunts like that."
(「いいえ、ちがうわ。多才っていうのは、いろいろなことがかんたんにできるってことなの。糸を吐いたり獲物をつかまえたりするだけじゃないってことよ」)
"Why don't you come with me to the Fair Grounds and lay your eggs there?" pleased Wilbur. "It would be wonderful fun."
(「だったら、品評会についてきて、そこでたまごを産むってわけにはいかないの?そうしたら、おもしろいと思うけどな」)
Charlotte gave her web a twitch and moodily watched it sway. "I'm afraid not," she said. "You don't know the first thing about egg laying, Wilbur. I can't arrange my family duties to suit the management of the County Fair. When I get ready to lay eggs, I have to lay eggs, Fair or no Fair. However, I don't want you to worry about it--you might lose weight. We'll leave it this way: I'll come to the Fair if I possibly can."
(シャーロットは網をぐいっとひっぱり、糸がゆれるのをゆううつそうにながめました。「むりね。あなたは、たまごを産むってことについて、なんにも知らないんでしょ、ウィルバー。家族への義務を、品評会の予定にあわせるわけにはいかないのよ。たまごを産む用意がととのったら、品評会があろうとなかろうと、たまごを産まなくちゃいけないの。でも、心配しないでいいのよ。心配すると、体重がへっちゃうわよ。そうだわ、こうしておきましょうよ。事情がゆるすなら、わたしも品評会にいくっていうことにしておきましょう」)
"Oh, good!" said Wilbur. "I knew you wouldn't forsake me just when I need you most."
(「ああ、よかった!いちばんそばにいてほしいときに、ぼくを見捨てたりしちゃいやだよ」と、ウィルバーはたのみました。)
All that day Wilbur stayed inside, taking life easy in the straw. Charlotte rested and ate a grasshopper. She knew that she couldn't help Wilbur much longer. In a few days she would have to drop everything and build the beautiful little sac that would hold her eggs.
(その日、ウィルバーは一日じゅう、納屋のわらの上でごろごろしていました。シャーロットはひと休みして、バッタを食べました。シャーロットには、ウィルバーをたすけてあげられる日々も、もう長くはないことがわかっていたのです。もうあと何日かしたら、ほかのことはみんなさしおいて、たまごを産むための小さなたまごぶくろをつくらなければなりません。)
little sac that would hold her eggs. (その日、ウィルバーは一日じゅう、納屋のわらの上でごろごろしていました。シャーロットはひと休みして、バッタを食べました。シャーロットには、ウィルバーをたすけてあげられる日々も、もう長くはないことがわかっていたのです。もうあと何日かしたら、ほかのことはみんなさしおいて、たまごを産むための小さなたまごぶくろをつくらなければなりません。)
英文のみです。
ⅩⅤ. The Crickets
The Crickets sang in the grasses. They sang the song of summer's ending, a sad, monotonous song. "Summer is over and gone," they sang. "Over and gone, over and gone. Summer is dying, dying."
The crickets felt it was their duty to warm everybody that summertime cannot last forever. Even on the most beautiful days in the whole year--the days when summer is changing into fall--the crickets spread the rumor of sadness and change.
Everybody heard the song of the crickets. Avery and Fern Arable heard it as they walked the dusty road. They knew that school would soon begin again. The young geese heard it and knew that they would never be little goslings again. Charlotte heard it and knew that she hadn't much time left. Mrs. Zuckerman, at work in the kitchen, heard the crickets, and a sadness came over her, too. "Another summer gone," she sighed. Lurvy, at work building a crate for Wilbur, heard the song and knew it was time to dig potatoes.
"Summer is over and gone," repeated the crickets. "How many nights till frost?" sang the crickets. "Good-bye, summer, good-bye, good-bye!"
The sheep heard the crickets, and they felt so uneasy they broke a hole in the pasture fence and wandered up into the field across the road. The gander discovered the hole and led his family through, and they walked to the orchard and ate the apples that were lying on the ground. A little maple tree in the swamp heard the cricket song and turned bright red with anxiety.
Wilbur was now the center of attraction on the farm. Good food and regular hours were showing results: Wilbur was a pig any man would be proud of. One day more than a hundred people came to stand at his yard and admire him. Charlotte had written the word RADIANT, and Wilbur really looked radiant as he stood in the golden sunlight. Ever since the spider had befriended him, he had done his best to live up to his reputation. When Charlotte's web said SOMEPIG, Wilbur had tried hard to look like some pig. When Charlotte's web said TERRIFIC, Wilbur had tried to look terrific. And now that the web said RADIANT, he did everything possible to make himself glow.
It is not easy to look radiant, but Wilbur threw himself into it with a will. He would turn his head slightly and blink his long eye-lashes. Then he would breathe deeply. And when his audience grew bored, he would spring into the air and do a back flip with a half with a half twist. At this the crowd would yell and cheer. "How's that for a pig?" Mr. Zuckerman would ask, well pleased with himself. "That pig is radiant."
Some of Wilbur's friends in the barn worried for fear all this attention would go to his head and make him stuck up. But it never did. Wilbur was modest; fame did not spoil him. He still worried some about the future, as he could hardly believe that a mere spider would be able to save his life. Sometimes at night he would have a bad dream. He would dream that men were coming to get him with knives and guns. But that was only a dream. In the daytime, Wilbur usually felt happy and confident. No pig ever had truer friends, and he realized that friendship is one of the most satisfying things in the world. Even the song of the crickets did not make Wilbur too sad. He knew it was almost time for the County Fair, and he was looking forward to the trip. If he could distinguish himself at the Fair, and maybe win some prize money, he was sure Zuckerman would let him live.
Charlotte had worries of her own, but she kept quiet about them. One morning Wilbur asked her about the Fair.
"You're going with me, aren't you, Charlotte?" he said.
"Well, I don't know," replied Charlotte. "The Fair comes at a bad time for me. I shall find it inconvenient to leave home, even for a few days."
"Why?" asked Wilbur.
"Oh, I just don't feel like leaving my web. Too much going on around here."
"Please come with me!" begged Wilbur. "I need you, Charlotte. I can't stand going to the Fair without you. You've just got to come."
"No," said Charlotte, "I believe I'd better stay home and see if I can't get some work done."
"What kind of work?" asked Wilbur.
"Egg laying. It's time I made an egg sac and filled it with eggs."
"I didn't know you could lay eggs," said Wilbur in amazement.
"Oh, sure," said the spider. "I'm versatile."
"What does 'versatile' mean--full of eggs?" asked Wilbur.
"Certainly not," said Charlotte. "'Versatile' means I can turn with ease from one thing to another. It means I don't have to limit my activities to spinning and trapping and stunts like that."
"Why don't you come with me to the Fair Grounds and lay your eggs there?" pleased Wilbur. "It would be wonderful fun."
Charlotte gave her web a twitch and moodily watched it sway. "I'm afraid not," she said. "You don't know the first thing about egg laying, Wilbur. I can't arrange my family duties to suit the management of the County Fair. When I get ready to lay eggs, I have to lay eggs, Fair or no Fair. However, I don't want you to worry about it--you might lose weight. We'll leave it this way: I'll come to the Fair if I possibly can."
"Oh, good!" said Wilbur. "I knew you wouldn't forsake me just when I need you most."
All that day Wilbur stayed inside, taking life easy in the straw. Charlotte rested and ate a grasshopper. She knew that she couldn't help Wilbur much longer. In a few days she would have to drop everything and build the beautiful little sac that would hold her eggs.
The Crickets sang in the grasses. They sang the song of summer's ending, a sad, monotonous song. "Summer is over and gone," they sang. "Over and gone, over and gone. Summer is dying, dying."
The crickets felt it was their duty to warm everybody that summertime cannot last forever. Even on the most beautiful days in the whole year--the days when summer is changing into fall--the crickets spread the rumor of sadness and change.
Everybody heard the song of the crickets. Avery and Fern Arable heard it as they walked the dusty road. They knew that school would soon begin again. The young geese heard it and knew that they would never be little goslings again. Charlotte heard it and knew that she hadn't much time left. Mrs. Zuckerman, at work in the kitchen, heard the crickets, and a sadness came over her, too. "Another summer gone," she sighed. Lurvy, at work building a crate for Wilbur, heard the song and knew it was time to dig potatoes.
"Summer is over and gone," repeated the crickets. "How many nights till frost?" sang the crickets. "Good-bye, summer, good-bye, good-bye!"
The sheep heard the crickets, and they felt so uneasy they broke a hole in the pasture fence and wandered up into the field across the road. The gander discovered the hole and led his family through, and they walked to the orchard and ate the apples that were lying on the ground. A little maple tree in the swamp heard the cricket song and turned bright red with anxiety.
Wilbur was now the center of attraction on the farm. Good food and regular hours were showing results: Wilbur was a pig any man would be proud of. One day more than a hundred people came to stand at his yard and admire him. Charlotte had written the word RADIANT, and Wilbur really looked radiant as he stood in the golden sunlight. Ever since the spider had befriended him, he had done his best to live up to his reputation. When Charlotte's web said SOMEPIG, Wilbur had tried hard to look like some pig. When Charlotte's web said TERRIFIC, Wilbur had tried to look terrific. And now that the web said RADIANT, he did everything possible to make himself glow.
It is not easy to look radiant, but Wilbur threw himself into it with a will. He would turn his head slightly and blink his long eye-lashes. Then he would breathe deeply. And when his audience grew bored, he would spring into the air and do a back flip with a half with a half twist. At this the crowd would yell and cheer. "How's that for a pig?" Mr. Zuckerman would ask, well pleased with himself. "That pig is radiant."
Some of Wilbur's friends in the barn worried for fear all this attention would go to his head and make him stuck up. But it never did. Wilbur was modest; fame did not spoil him. He still worried some about the future, as he could hardly believe that a mere spider would be able to save his life. Sometimes at night he would have a bad dream. He would dream that men were coming to get him with knives and guns. But that was only a dream. In the daytime, Wilbur usually felt happy and confident. No pig ever had truer friends, and he realized that friendship is one of the most satisfying things in the world. Even the song of the crickets did not make Wilbur too sad. He knew it was almost time for the County Fair, and he was looking forward to the trip. If he could distinguish himself at the Fair, and maybe win some prize money, he was sure Zuckerman would let him live.
Charlotte had worries of her own, but she kept quiet about them. One morning Wilbur asked her about the Fair.
"You're going with me, aren't you, Charlotte?" he said.
"Well, I don't know," replied Charlotte. "The Fair comes at a bad time for me. I shall find it inconvenient to leave home, even for a few days."
"Why?" asked Wilbur.
"Oh, I just don't feel like leaving my web. Too much going on around here."
"Please come with me!" begged Wilbur. "I need you, Charlotte. I can't stand going to the Fair without you. You've just got to come."
"No," said Charlotte, "I believe I'd better stay home and see if I can't get some work done."
"What kind of work?" asked Wilbur.
"Egg laying. It's time I made an egg sac and filled it with eggs."
"I didn't know you could lay eggs," said Wilbur in amazement.
"Oh, sure," said the spider. "I'm versatile."
"What does 'versatile' mean--full of eggs?" asked Wilbur.
"Certainly not," said Charlotte. "'Versatile' means I can turn with ease from one thing to another. It means I don't have to limit my activities to spinning and trapping and stunts like that."
"Why don't you come with me to the Fair Grounds and lay your eggs there?" pleased Wilbur. "It would be wonderful fun."
Charlotte gave her web a twitch and moodily watched it sway. "I'm afraid not," she said. "You don't know the first thing about egg laying, Wilbur. I can't arrange my family duties to suit the management of the County Fair. When I get ready to lay eggs, I have to lay eggs, Fair or no Fair. However, I don't want you to worry about it--you might lose weight. We'll leave it this way: I'll come to the Fair if I possibly can."
"Oh, good!" said Wilbur. "I knew you wouldn't forsake me just when I need you most."
All that day Wilbur stayed inside, taking life easy in the straw. Charlotte rested and ate a grasshopper. She knew that she couldn't help Wilbur much longer. In a few days she would have to drop everything and build the beautiful little sac that would hold her eggs.
日本語訳のみです。
15.コオロギ
草のかげでコオロギが鳴いていました。コオロギたちは、かなしげな一本調子で、夏のおわりの歌をうたっていたのです。「夏がおわる。おわる、おわる。夏がすぎてゆく」と、コオロギはうたっていました。
コオロギたちは、夏がいつまでもつづくわけではないということを知らせるのが、自分たちの仕事だとこころえていました。一年でいちばん美しい季節-夏がおわっ威漱になろうとする時期-なのに、やがてかなしい変化がおとずれることを、コオロギたちはみんなに知らせていたのです。
だれもが、コオロギの歌をきいていました。土ぼこりのたつ道を歩いていたエイヴリーとファーンはそれをきいて、学校がもうすぐはじまることを思いだしました。ガチョウの子どもたちはそれをきいて、自分たちがもう小さなひな鳥ではないのを知りました。シャーロットはそれをきいて、もうあまり時間がのこされていないのだと覚悟しました。台所で働いていたザッカーマンのおばさんは、コオロギの声をきくとわびしくなって、「また夏がいってしまうんだね」と、ため息をつきました。ウィルバー用の木箱をつくっていたラーヴィーは、コオロギの声をきいて、そろそろジャガイモをほりあげなくちゃ、と思っていました。
「夏がすぎてゆく」コオロギはくりかえしました。「霜がおりるのも、もうすぐだ」コオロギはうたいました。「夏よ、さよなら、さよなら、さよなら!」
羊たちはコオロギの声をきくと、不安にかられて牧草地の垣根に穴をあけ、そこをくぐりぬけて道路の向こうの畑までさまよいでていきました。その穴をみつけたガチョウのおじさんは、一家をひきつれて外へでると果樹園までいき、下に落ちていたリンゴを食べました。沼地の小さなカエデの木は、コオロギの歌をきいて胸がしめつけられ、まっ赤な色にかわりました。
ウィルバーは、今では農場のよびものになっていました。おいしい食べものと規則正しい生活のおかげで、ウイルバーはだれもがじまんに思うようなブタに成長していました。ある日、百人以上の人がウィルバーを見にやってきました。シャーロットは『ぴかぴか』という文字を書いておいたのですが、金色の日の光に照らされたウィルバーは、ほんとうにぴかぴかにかがやいていました。このクモと友だちになって以来、ウィルバーは評判をうらぎらないようにがんばってきました。シャーロットが『たいしたブタ』と書いたときには、ウィルバーはたいしたブタに見えるように、いっしょけんめい努力しました。シャーロットの巣に『すばらしい』という文字があらわれたときには、ウィルバーはすばらしく見えるように努力しました。そしてシャーロットの巣に『ぴかぴか』という文字があらわれている今、ウィルバーはじぶんがかがやいて見えるように、できるだけのことをしていました。
ぴかぴかに見せるのは、たやすいことではありませんが、ウィルバーはせいいっぱい努力していました。頭をちょっとかしげて、長いまつげをパチパチさせます。それから大きく息をします。見物客があきてくると、ぴょんととびあがって、半回転ひねりを入れたうしろ宙がえりをしてみせました。これを見た人は、みんな大きな歓声をあげました。すると、ザッカーマンのおじさんは気をよくして、「どんなもんです?このブタはぴっかびかでしょうが?」というのでした。
納屋の動物たちのなかには、これだけ注目をあつめると、ウィルバーがなまいきになるのではないかと心配する者もいました。でも、そんなことにはなりませんでした。ウィルバーはひかえめなブタで、有名になっても、いい気になったりはしなかったのです。それに、先のことがまだ少し心配でした。一ぴきのクモに自分の命を救うことができるなんて半信半疑だったからです。夜になると、わるい夢にうなされることもありました。人間が包丁や銃を持って、おそってくる夢を見るのです。でも、それはただの夢でした。昼間は、ウィルバーはたいていしあわせで、自信にみちていました。こんなに信頼できる友だちをもったブタは、ほかにいません。そして、世の中でいちばんたしかなのは友情だということを、ウィルバーは知っていました。コオロギの歌をきいても、ウィルバーはあまりさびしくなりませんでした。もうすぐ品評会がひらかれるのを知っていて、出場を楽しみにしていたからです。品評会でウィルバーが優秀と認められ、賞金でももらえれば、ザッカーマンさんは自分を生かしておいてくれるでしょう。
シャーロットのほうは心配ごとをかかえていましたが、それをだれにも話しませんでした。ある朝、ウィルバーは品評会のことでシャーロットにたずねました。
「シャーロット、品評会にはついてきてくれるんでしょ?」
「さあ、どうかしら」と、シャーロットはこたえました。「ちょうど時期がわるいのよ。そのころは、たとえ二、三日でも、家をるすにするわけにはいかないんじゃないかしら」
「どうしてなの?」ウィルバーがききました。
「ただ巣をはなれたくないのよ。いそがしい時期なの」
「おねがいだから、いつしょにいってよ!そばにいてくれなきゃ、ぼく、こまっちゃうよ。いっしょじゃなきゃ、品評会なんかでられないよ。どうしたって、いってよね」ウィルバーはたのみました。
「いいえ。きっと家にいて、しなきゃいけないことがあると思うの」
「どんなことしなきゃいけないの?」
「たまごを産むことよ。そろそろたまごぶくろをつくって、そのなかにたまごを産んでおかないとね」
「きみにたまごが産めるなんて、ぼく知らなかったよ」ウィルバーは、びっくりしました。
「もちろん産めるのよ。わたしは多才なの」
「タサイって?たまごをいっぱい持ってるってこと?」ウィルバーがたずねました。
「いいえ、ちがうわ。多才っていうのは、いろいろなことがかんたんにできるってことなの。糸を吐いたり獲物をつかまえたりするだけじゃないってことよ」
「だったら、品評会についてきて、そこでたまごを産むってわけにはいかないの?そうしたら、おもしろいと思うけどな」
シャーロットは網をぐいっとひっぱり、糸がゆれるのをゆううつそうにながめました。
「むりね。あなたは、たまごを産むってことについて、なんにも知らないんでしょ、ウィルバー。家族への義務を、品評会の予定にあわせるわけにはいかないのよ。たまごを産む用意がととのったら、品評会があろうとなかろうと、たまごを産まなくちゃいけないの。でも、心配しないでいいのよ。心配すると、体重がへっちゃうわよ。そうだわ、こうしておきましょうよ。事情がゆるすなら、わたしも品評会にいくっていうことにしておきましょう」
「ああ、よかった!いちばんそばにいてほしいときに、ぼくを見捨てたりしちゃいやだよ」と、ウィルバーはたのみました。
その日、ウィルバーは一日じゅう、納屋のわらの上でごろごろしていました。シャーロットはひと休みして、バッタを食べました。シャーロットには、ウィルバーをたすけてあげられる日々も、もう長くはないことがわかっていたのです。もうあと何日かしたら、ほかのことはみんなさしおいて、たまごを産むための小さなたまごぶくろをつくらなければなりません。
草のかげでコオロギが鳴いていました。コオロギたちは、かなしげな一本調子で、夏のおわりの歌をうたっていたのです。「夏がおわる。おわる、おわる。夏がすぎてゆく」と、コオロギはうたっていました。
コオロギたちは、夏がいつまでもつづくわけではないということを知らせるのが、自分たちの仕事だとこころえていました。一年でいちばん美しい季節-夏がおわっ威漱になろうとする時期-なのに、やがてかなしい変化がおとずれることを、コオロギたちはみんなに知らせていたのです。
だれもが、コオロギの歌をきいていました。土ぼこりのたつ道を歩いていたエイヴリーとファーンはそれをきいて、学校がもうすぐはじまることを思いだしました。ガチョウの子どもたちはそれをきいて、自分たちがもう小さなひな鳥ではないのを知りました。シャーロットはそれをきいて、もうあまり時間がのこされていないのだと覚悟しました。台所で働いていたザッカーマンのおばさんは、コオロギの声をきくとわびしくなって、「また夏がいってしまうんだね」と、ため息をつきました。ウィルバー用の木箱をつくっていたラーヴィーは、コオロギの声をきいて、そろそろジャガイモをほりあげなくちゃ、と思っていました。
「夏がすぎてゆく」コオロギはくりかえしました。「霜がおりるのも、もうすぐだ」コオロギはうたいました。「夏よ、さよなら、さよなら、さよなら!」
羊たちはコオロギの声をきくと、不安にかられて牧草地の垣根に穴をあけ、そこをくぐりぬけて道路の向こうの畑までさまよいでていきました。その穴をみつけたガチョウのおじさんは、一家をひきつれて外へでると果樹園までいき、下に落ちていたリンゴを食べました。沼地の小さなカエデの木は、コオロギの歌をきいて胸がしめつけられ、まっ赤な色にかわりました。
ウィルバーは、今では農場のよびものになっていました。おいしい食べものと規則正しい生活のおかげで、ウイルバーはだれもがじまんに思うようなブタに成長していました。ある日、百人以上の人がウィルバーを見にやってきました。シャーロットは『ぴかぴか』という文字を書いておいたのですが、金色の日の光に照らされたウィルバーは、ほんとうにぴかぴかにかがやいていました。このクモと友だちになって以来、ウィルバーは評判をうらぎらないようにがんばってきました。シャーロットが『たいしたブタ』と書いたときには、ウィルバーはたいしたブタに見えるように、いっしょけんめい努力しました。シャーロットの巣に『すばらしい』という文字があらわれたときには、ウィルバーはすばらしく見えるように努力しました。そしてシャーロットの巣に『ぴかぴか』という文字があらわれている今、ウィルバーはじぶんがかがやいて見えるように、できるだけのことをしていました。
ぴかぴかに見せるのは、たやすいことではありませんが、ウィルバーはせいいっぱい努力していました。頭をちょっとかしげて、長いまつげをパチパチさせます。それから大きく息をします。見物客があきてくると、ぴょんととびあがって、半回転ひねりを入れたうしろ宙がえりをしてみせました。これを見た人は、みんな大きな歓声をあげました。すると、ザッカーマンのおじさんは気をよくして、「どんなもんです?このブタはぴっかびかでしょうが?」というのでした。
納屋の動物たちのなかには、これだけ注目をあつめると、ウィルバーがなまいきになるのではないかと心配する者もいました。でも、そんなことにはなりませんでした。ウィルバーはひかえめなブタで、有名になっても、いい気になったりはしなかったのです。それに、先のことがまだ少し心配でした。一ぴきのクモに自分の命を救うことができるなんて半信半疑だったからです。夜になると、わるい夢にうなされることもありました。人間が包丁や銃を持って、おそってくる夢を見るのです。でも、それはただの夢でした。昼間は、ウィルバーはたいていしあわせで、自信にみちていました。こんなに信頼できる友だちをもったブタは、ほかにいません。そして、世の中でいちばんたしかなのは友情だということを、ウィルバーは知っていました。コオロギの歌をきいても、ウィルバーはあまりさびしくなりませんでした。もうすぐ品評会がひらかれるのを知っていて、出場を楽しみにしていたからです。品評会でウィルバーが優秀と認められ、賞金でももらえれば、ザッカーマンさんは自分を生かしておいてくれるでしょう。
シャーロットのほうは心配ごとをかかえていましたが、それをだれにも話しませんでした。ある朝、ウィルバーは品評会のことでシャーロットにたずねました。
「シャーロット、品評会にはついてきてくれるんでしょ?」
「さあ、どうかしら」と、シャーロットはこたえました。「ちょうど時期がわるいのよ。そのころは、たとえ二、三日でも、家をるすにするわけにはいかないんじゃないかしら」
「どうしてなの?」ウィルバーがききました。
「ただ巣をはなれたくないのよ。いそがしい時期なの」
「おねがいだから、いつしょにいってよ!そばにいてくれなきゃ、ぼく、こまっちゃうよ。いっしょじゃなきゃ、品評会なんかでられないよ。どうしたって、いってよね」ウィルバーはたのみました。
「いいえ。きっと家にいて、しなきゃいけないことがあると思うの」
「どんなことしなきゃいけないの?」
「たまごを産むことよ。そろそろたまごぶくろをつくって、そのなかにたまごを産んでおかないとね」
「きみにたまごが産めるなんて、ぼく知らなかったよ」ウィルバーは、びっくりしました。
「もちろん産めるのよ。わたしは多才なの」
「タサイって?たまごをいっぱい持ってるってこと?」ウィルバーがたずねました。
「いいえ、ちがうわ。多才っていうのは、いろいろなことがかんたんにできるってことなの。糸を吐いたり獲物をつかまえたりするだけじゃないってことよ」
「だったら、品評会についてきて、そこでたまごを産むってわけにはいかないの?そうしたら、おもしろいと思うけどな」
シャーロットは網をぐいっとひっぱり、糸がゆれるのをゆううつそうにながめました。
「むりね。あなたは、たまごを産むってことについて、なんにも知らないんでしょ、ウィルバー。家族への義務を、品評会の予定にあわせるわけにはいかないのよ。たまごを産む用意がととのったら、品評会があろうとなかろうと、たまごを産まなくちゃいけないの。でも、心配しないでいいのよ。心配すると、体重がへっちゃうわよ。そうだわ、こうしておきましょうよ。事情がゆるすなら、わたしも品評会にいくっていうことにしておきましょう」
「ああ、よかった!いちばんそばにいてほしいときに、ぼくを見捨てたりしちゃいやだよ」と、ウィルバーはたのみました。
その日、ウィルバーは一日じゅう、納屋のわらの上でごろごろしていました。シャーロットはひと休みして、バッタを食べました。シャーロットには、ウィルバーをたすけてあげられる日々も、もう長くはないことがわかっていたのです。もうあと何日かしたら、ほかのことはみんなさしおいて、たまごを産むための小さなたまごぶくろをつくらなければなりません。
Charlotte's Web 16