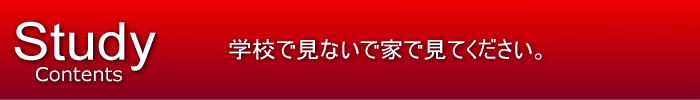Charlotte's Web 6
6.夏の日々
農場では、初夏のころが一年でいちばんさわやかで、しあわせな季節でした。ライラックの花がさいて、あまいかおりをただよわせてから、しぼみます。おなじころにリンゴの花がさき、ミツバチが木のまわりにあつまってきます。日ましにあたたかくなり、おだやかな日がつづきます。学校が休みに入ると、子どもたちは遊んだり、小川でマスを釣ったりする時間が持てるようになります。エイヴリーは、よくポケットにマスを入れて帰ってきました。長いことポケットに入れられていたマスは、なまあたたかく、かたくなっていましたが、フライにすれば夕ごはんのおかずになるのでした。
学校が休みになってからは、ファーンは毎日のようにウィルバーがいる納屋に通い、しずかにいすにすわって見ていました。動物たちはファーンを仲間だと思い、羊もファーンの足もとに、おだやかにねそべっていました。
七月のはじめには、農耕馬をつないだ草刈り機にザッカーマンのおじさんが乗りこみ、草場にでていきます。朝のあいだずっと、草刈り機はカタカタ音をさせながらぐるぐるとまわり、高くのびた草が刈られてバタバタとたおれていきました。翌日は、雷雨がこないかぎり、働き手は全員あつまって、刈った草をかきあつめて荷馬車に山とつみ、納屋まで運ぶのでした。ファーンとエイヴリーは、その干し草の山の上に乗っていっしょに納屋までいきました。納屋につくと、いいにおいのするあたたかい干し草は、広いロフトにつみあげられます。すると納屋じゅうが、牧草やクローバーのすてきなベッドのようになりました。干し草の山は、上にとび乗ってもおもしろいし、かくれるのにもちょうどいいのです。エイヴリーは、ときどき小さなアオヘビをみつけて、ほかのものといっしょにポケットにしまいこみました。
初夏は、小鳥たちにとっても楽しい季節でした。草場も、家のまわりも、納屋も、森も、沼も、小鳥たちの愛と歌と巣とたまごでいっぱいになります。森のはずれでは、ノドジロシトド(はるばるボストンからやってきたのでしょう)が、「ピーボディー、ピーボディー、ピーボディー!」とさけびます。リンゴの木の枝では、フェーベがしつぼをふって体をゆらしながら「フィービー、フィービー!」とうたいます。ウタヒメドリは、命がはかなく美しいのを知っているので、「スイート、スイート、スイート、インタールード!」(つかの間の楽しさ)と唱えます。納屋に入れば、巣からヒューッとおりてきたツバメに、「チーキー、チーキー!」(いたずらっ子)としかられます。
初夏には、子どもが食べたりのんだり、吸ったりかんだりするものが、たくさんありました。タンポポの茎にはミルクがいっぱいつまっているし、クローバーの花には蜜がたまっているし、冷蔵庫には冷たいのみものが入っています。どこをみても命にあふれていて、草の茎の小さな泡玉をつついても、なかから緑の虫があらわれました。ジャガイモの葉っぱの裏側には、ジャガイモハムシのあざやかなオレンジ色のたまごがついていました。
そんな初夏のある日、ガチョウのたまごがかえりました。納屋の地下室では、これは大事件です。ちょうどファーンもきていて、いすにすわって見ていました。
赤ちゃんが生まれたのに最初に気づいたのは、ガチョウのおばさんとシャーロットでした。ガチョウのおばさんは、まえの日からわかっていました。たまごのなかから、弱々しい声がきこえていたからです。殻のなかはとてもきゅうくつなので、早く外にでたいといっているのがわかりました。そこで、ガチョウのおばさんはじっとすわって、おしゃべりもいつもよりひかえていました。
いちばんはじめの赤ちゃんが、灰色と緑がまざったような色の頭をお母さんの羽のあいだからのぞかせて、あたりを見まわしたとき、シャーロットはそれを見つけていいました。
「ここに影うわたしたち全員は、友人のガチョウさんが、四週間ものたゆまぬ努力と忍耐のすえ、とうとう成果をあげられたことを知って、たいへんよろこばしく思うでしょう。赤ちゃんが生まれましたよ。心からのおよろこびを、わたしは申しあげますよ!」
「ありがとう、がとう、がとう!」
ガチョウのおばさんは、得意そうにうなずいたり、おじぎをしたりしました。
「ありがとさん」と、ガチョウのおじさんもいいました。
「おめでとう!赤ちゃんは何羽いるの?ぼくには一羽しか見えないけど」ウイルバーがさけびました。
「七羽よ」と、ガチョウのおばさんがいいました。
「いいわね!七は幸運の数ですもんね」と、シャーロットがいいました。
「運は関係ないわ。あたしの努力と、じょうずなやりくりのおかげだもの」と、ガチョウのおばさんがいいました。
このとき、ウィルバーのえさ箱の下のかくれ家から、テンプルトンが鼻づらをのぞかせました。テンプルトンはファーンにちらりと目をやり、壁の近くを通って、ガチョウのそばまで用心しいしいやってきました。だれもが、テンプルトンを見ていました。あんまり信用できないやつだと、みんな思っていたからです。
「ねえ、七羽っていったよね。たまごは八こあったじゃないか。もう一つのたまごは、どうなったのさ?どうしてかえらなかったのさ?」テンプルトンはするどい声をはりあけました。
「もともとかえらないたまごだったのよ」と、ガチョウのおばさんがいいました。
「そのたまごは、どうするんだい?」小さなビーズのようなまるい目でガチョウをじつと見ながら、テンプルトンがききました。
「あげてもいいよ。ころがしてって、あんたのへんてこなコレクションに加えたらいいさ」と、ガチョウのおばさんはこたえました。(テンプルトンは、農場にあるかわったものを拾いあつめて、しまっておくくせがありました)
「いいよ、いいよ、いいよ。たまごはやるよ。でも、一ついっとくけど、うちの子どもたちに、そのきたない鼻づらでちょっかいをだすようなことがあったら、これまでネズミがいちども経験したこともないようなひどい目にあわせてやるからな」
ガチョウのおじさんはそういうと、がんじょうなつばさをひろげてバサバサとゆらし、力を見せつけました。たしかに、ガチョウのおじさんは強くて勇敢でしたが、じつのところ、ガチョウ夫婦はテンプルトンに不安を感じていたのです。それも、むりのないことでした。このネズミは、よいこととわるいことの区別もつかなければ、良心も、気のとがめも、思いやりも、礼儀も、人情ならぬネズミの情けも、反省も、高次の感覚も、しんせつ心も、なんにも持ちあわせていなかったからです。テンプルトンが、見つかりさえしなければ平気で赤ちゃんをころすだろうことを、ガチョウは知っていました。それくらいのことは、誰でも知っていたのです。
ガチョウのおばさんは、かえらなかったたまごを大きなくちばしで巣からおしだしました。それをネズミがころがしていくのを、納屋のみんなはあきれ顔で見ていました。ほとんどなんでもすききらいなく食べるウィルバーでさえ、ぞっとしてつぶやきました。
「しょうもない、くさったたまごがほしいだなんて!」
「ネズミはネズミなのよね」とシャーロットはいい、けらけらと笑いました。「だけど、あの古いたまごが割れたりしたら、この納屋には住めなくなるわよ」
「どういう意味?」と、ウィルバーがたずねました。
「たまごがくさくて、ここにはだれも住めなくなるってことよ。くさったたまごは、におい爆弾みたいなものだからね」
「割ったりしないさ」と、テンプルトンがどなりかえしました。「自分のやってることくらいわかってるよ。こういうの、いつもあつかってるんだからさ」
テンプルトンは、ガチョウのたまごを前足でころがしながら、トンネルのなかに消えていきました。そして、おしたり、こづいたりしながら、えさ箱の下にある巣穴まで運んでいきました。
その日の午後、風がおさまると、納屋の前庭はしずかでぽかぽかとあたたかくなりました。灰色のガチョウのおばさんは、七羽のひなをつれて、外の世界へでていきました。ウィルバーの夕ごはんを運んできたザッカーマンのおじさんが、そのようすを見ていました。
「やあ、生まれたんだね!」おじさんはそういうと、にっこり笑いました。「さてと……一、二、三、四、五、六、七羽だな。ガチョウのひなが七羽。けっこう、けっこう!」
英文のみです。
日本語訳のみです。
Charlotte's Web 7
農場では、初夏のころが一年でいちばんさわやかで、しあわせな季節でした。ライラックの花がさいて、あまいかおりをただよわせてから、しぼみます。おなじころにリンゴの花がさき、ミツバチが木のまわりにあつまってきます。日ましにあたたかくなり、おだやかな日がつづきます。学校が休みに入ると、子どもたちは遊んだり、小川でマスを釣ったりする時間が持てるようになります。エイヴリーは、よくポケットにマスを入れて帰ってきました。長いことポケットに入れられていたマスは、なまあたたかく、かたくなっていましたが、フライにすれば夕ごはんのおかずになるのでした。
学校が休みになってからは、ファーンは毎日のようにウィルバーがいる納屋に通い、しずかにいすにすわって見ていました。動物たちはファーンを仲間だと思い、羊もファーンの足もとに、おだやかにねそべっていました。
七月のはじめには、農耕馬をつないだ草刈り機にザッカーマンのおじさんが乗りこみ、草場にでていきます。朝のあいだずっと、草刈り機はカタカタ音をさせながらぐるぐるとまわり、高くのびた草が刈られてバタバタとたおれていきました。翌日は、雷雨がこないかぎり、働き手は全員あつまって、刈った草をかきあつめて荷馬車に山とつみ、納屋まで運ぶのでした。ファーンとエイヴリーは、その干し草の山の上に乗っていっしょに納屋までいきました。納屋につくと、いいにおいのするあたたかい干し草は、広いロフトにつみあげられます。すると納屋じゅうが、牧草やクローバーのすてきなベッドのようになりました。干し草の山は、上にとび乗ってもおもしろいし、かくれるのにもちょうどいいのです。エイヴリーは、ときどき小さなアオヘビをみつけて、ほかのものといっしょにポケットにしまいこみました。
初夏は、小鳥たちにとっても楽しい季節でした。草場も、家のまわりも、納屋も、森も、沼も、小鳥たちの愛と歌と巣とたまごでいっぱいになります。森のはずれでは、ノドジロシトド(はるばるボストンからやってきたのでしょう)が、「ピーボディー、ピーボディー、ピーボディー!」とさけびます。リンゴの木の枝では、フェーベがしつぼをふって体をゆらしながら「フィービー、フィービー!」とうたいます。ウタヒメドリは、命がはかなく美しいのを知っているので、「スイート、スイート、スイート、インタールード!」(つかの間の楽しさ)と唱えます。納屋に入れば、巣からヒューッとおりてきたツバメに、「チーキー、チーキー!」(いたずらっ子)としかられます。
初夏には、子どもが食べたりのんだり、吸ったりかんだりするものが、たくさんありました。タンポポの茎にはミルクがいっぱいつまっているし、クローバーの花には蜜がたまっているし、冷蔵庫には冷たいのみものが入っています。どこをみても命にあふれていて、草の茎の小さな泡玉をつついても、なかから緑の虫があらわれました。ジャガイモの葉っぱの裏側には、ジャガイモハムシのあざやかなオレンジ色のたまごがついていました。
そんな初夏のある日、ガチョウのたまごがかえりました。納屋の地下室では、これは大事件です。ちょうどファーンもきていて、いすにすわって見ていました。
赤ちゃんが生まれたのに最初に気づいたのは、ガチョウのおばさんとシャーロットでした。ガチョウのおばさんは、まえの日からわかっていました。たまごのなかから、弱々しい声がきこえていたからです。殻のなかはとてもきゅうくつなので、早く外にでたいといっているのがわかりました。そこで、ガチョウのおばさんはじっとすわって、おしゃべりもいつもよりひかえていました。
いちばんはじめの赤ちゃんが、灰色と緑がまざったような色の頭をお母さんの羽のあいだからのぞかせて、あたりを見まわしたとき、シャーロットはそれを見つけていいました。
「ここに影うわたしたち全員は、友人のガチョウさんが、四週間ものたゆまぬ努力と忍耐のすえ、とうとう成果をあげられたことを知って、たいへんよろこばしく思うでしょう。赤ちゃんが生まれましたよ。心からのおよろこびを、わたしは申しあげますよ!」
「ありがとう、がとう、がとう!」
ガチョウのおばさんは、得意そうにうなずいたり、おじぎをしたりしました。
「ありがとさん」と、ガチョウのおじさんもいいました。
「おめでとう!赤ちゃんは何羽いるの?ぼくには一羽しか見えないけど」ウイルバーがさけびました。
「七羽よ」と、ガチョウのおばさんがいいました。
「いいわね!七は幸運の数ですもんね」と、シャーロットがいいました。
「運は関係ないわ。あたしの努力と、じょうずなやりくりのおかげだもの」と、ガチョウのおばさんがいいました。
このとき、ウィルバーのえさ箱の下のかくれ家から、テンプルトンが鼻づらをのぞかせました。テンプルトンはファーンにちらりと目をやり、壁の近くを通って、ガチョウのそばまで用心しいしいやってきました。だれもが、テンプルトンを見ていました。あんまり信用できないやつだと、みんな思っていたからです。
「ねえ、七羽っていったよね。たまごは八こあったじゃないか。もう一つのたまごは、どうなったのさ?どうしてかえらなかったのさ?」テンプルトンはするどい声をはりあけました。
「もともとかえらないたまごだったのよ」と、ガチョウのおばさんがいいました。
「そのたまごは、どうするんだい?」小さなビーズのようなまるい目でガチョウをじつと見ながら、テンプルトンがききました。
「あげてもいいよ。ころがしてって、あんたのへんてこなコレクションに加えたらいいさ」と、ガチョウのおばさんはこたえました。(テンプルトンは、農場にあるかわったものを拾いあつめて、しまっておくくせがありました)
「いいよ、いいよ、いいよ。たまごはやるよ。でも、一ついっとくけど、うちの子どもたちに、そのきたない鼻づらでちょっかいをだすようなことがあったら、これまでネズミがいちども経験したこともないようなひどい目にあわせてやるからな」
ガチョウのおじさんはそういうと、がんじょうなつばさをひろげてバサバサとゆらし、力を見せつけました。たしかに、ガチョウのおじさんは強くて勇敢でしたが、じつのところ、ガチョウ夫婦はテンプルトンに不安を感じていたのです。それも、むりのないことでした。このネズミは、よいこととわるいことの区別もつかなければ、良心も、気のとがめも、思いやりも、礼儀も、人情ならぬネズミの情けも、反省も、高次の感覚も、しんせつ心も、なんにも持ちあわせていなかったからです。テンプルトンが、見つかりさえしなければ平気で赤ちゃんをころすだろうことを、ガチョウは知っていました。それくらいのことは、誰でも知っていたのです。
ガチョウのおばさんは、かえらなかったたまごを大きなくちばしで巣からおしだしました。それをネズミがころがしていくのを、納屋のみんなはあきれ顔で見ていました。ほとんどなんでもすききらいなく食べるウィルバーでさえ、ぞっとしてつぶやきました。
「しょうもない、くさったたまごがほしいだなんて!」
「ネズミはネズミなのよね」とシャーロットはいい、けらけらと笑いました。「だけど、あの古いたまごが割れたりしたら、この納屋には住めなくなるわよ」
「どういう意味?」と、ウィルバーがたずねました。
「たまごがくさくて、ここにはだれも住めなくなるってことよ。くさったたまごは、におい爆弾みたいなものだからね」
「割ったりしないさ」と、テンプルトンがどなりかえしました。「自分のやってることくらいわかってるよ。こういうの、いつもあつかってるんだからさ」
テンプルトンは、ガチョウのたまごを前足でころがしながら、トンネルのなかに消えていきました。そして、おしたり、こづいたりしながら、えさ箱の下にある巣穴まで運んでいきました。
その日の午後、風がおさまると、納屋の前庭はしずかでぽかぽかとあたたかくなりました。灰色のガチョウのおばさんは、七羽のひなをつれて、外の世界へでていきました。ウィルバーの夕ごはんを運んできたザッカーマンのおじさんが、そのようすを見ていました。
「やあ、生まれたんだね!」おじさんはそういうと、にっこり笑いました。「さてと……一、二、三、四、五、六、七羽だな。ガチョウのひなが七羽。けっこう、けっこう!」
英文のみです。
日本語訳のみです。
6.夏の日々
農場では、初夏のころが一年でいちばんさわやかで、しあわせな季節でした。ライラックの花がさいて、あまいかおりをただよわせてから、しぼみます。おなじころにリンゴの花がさき、ミツバチが木のまわりにあつまってきます。日ましにあたたかくなり、おだやかな日がつづきます。学校が休みに入ると、子どもたちは遊んだり、小川でマスを釣ったりする時間が持てるようになります。エイヴリーは、よくポケットにマスを入れて帰ってきました。長いことポケットに入れられていたマスは、なまあたたかく、かたくなっていましたが、フライにすれば夕ごはんのおかずになるのでした。
学校が休みになってからは、ファーンは毎日のようにウィルバーがいる納屋に通い、しずかにいすにすわって見ていました。動物たちはファーンを仲間だと思い、羊もファーンの足もとに、おだやかにねそべっていました。
七月のはじめには、農耕馬をつないだ草刈り機にザッカーマンのおじさんが乗りこみ、草場にでていきます。朝のあいだずっと、草刈り機はカタカタ音をさせながらぐるぐるとまわり、高くのびた草が刈られてバタバタとたおれていきました。翌日は、雷雨がこないかぎり、働き手は全員あつまって、刈った草をかきあつめて荷馬車に山とつみ、納屋まで運ぶのでした。ファーンとエイヴリーは、その干し草の山の上に乗っていっしょに納屋までいきました。納屋につくと、いいにおいのするあたたかい干し草は、広いロフトにつみあげられます。すると納屋じゅうが、牧草やクローバーのすてきなベッドのようになりました。干し草の山は、上にとび乗ってもおもしろいし、かくれるのにもちょうどいいのです。エイヴリーは、ときどき小さなアオヘビをみつけて、ほかのものといっしょにポケットにしまいこみました。
初夏は、小鳥たちにとっても楽しい季節でした。草場も、家のまわりも、納屋も、森も、沼も、小鳥たちの愛と歌と巣とたまごでいっぱいになります。森のはずれでは、ノドジロシトド(はるばるボストンからやってきたのでしょう)が、「ピーボディー、ピーボディー、ピーボディー!」とさけびます。リンゴの木の枝では、フェーベがしつぼをふって体をゆらしながら「フィービー、フィービー!」とうたいます。ウタヒメドリは、命がはかなく美しいのを知っているので、「スイート、スイート、スイート、インタールード!」(つかの間の楽しさ)と唱えます。納屋に入れば、巣からヒューッとおりてきたツバメに、「チーキー、チーキー!」(いたずらっ子)としかられます。
初夏には、子どもが食べたりのんだり、吸ったりかんだりするものが、たくさんありました。タンポポの茎にはミルクがいっぱいつまっているし、クローバーの花には蜜がたまっているし、冷蔵庫には冷たいのみものが入っています。どこをみても命にあふれていて、草の茎の小さな泡玉をつついても、なかから緑の虫があらわれました。ジャガイモの葉っぱの裏側には、ジャガイモハムシのあざやかなオレンジ色のたまごがついていました。
そんな初夏のある日、ガチョウのたまごがかえりました。納屋の地下室では、これは大事件です。ちょうどファーンもきていて、いすにすわって見ていました。
赤ちゃんが生まれたのに最初に気づいたのは、ガチョウのおばさんとシャーロットでした。ガチョウのおばさんは、まえの日からわかっていました。たまごのなかから、弱々しい声がきこえていたからです。殻のなかはとてもきゅうくつなので、早く外にでたいといっているのがわかりました。そこで、ガチョウのおばさんはじっとすわって、おしゃべりもいつもよりひかえていました。
いちばんはじめの赤ちゃんが、灰色と緑がまざったような色の頭をお母さんの羽のあいだからのぞかせて、あたりを見まわしたとき、シャーロットはそれを見つけていいました。
「ここに影うわたしたち全員は、友人のガチョウさんが、四週間ものたゆまぬ努力と忍耐のすえ、とうとう成果をあげられたことを知って、たいへんよろこばしく思うでしょう。赤ちゃんが生まれましたよ。心からのおよろこびを、わたしは申しあげますよ!」
「ありがとう、がとう、がとう!」
ガチョウのおばさんは、得意そうにうなずいたり、おじぎをしたりしました。
「ありがとさん」と、ガチョウのおじさんもいいました。
「おめでとう!赤ちゃんは何羽いるの?ぼくには一羽しか見えないけど」ウイルバーがさけびました。
「七羽よ」と、ガチョウのおばさんがいいました。
「いいわね!七は幸運の数ですもんね」と、シャーロットがいいました。
「運は関係ないわ。あたしの努力と、じょうずなやりくりのおかげだもの」と、ガチョウのおばさんがいいました。
このとき、ウィルバーのえさ箱の下のかくれ家から、テンプルトンが鼻づらをのぞかせました。テンプルトンはファーンにちらりと目をやり、壁の近くを通って、ガチョウのそばまで用心しいしいやってきました。だれもが、テンプルトンを見ていました。あんまり信用できないやつだと、みんな思っていたからです。
「ねえ、七羽っていったよね。たまごは八こあったじゃないか。もう一つのたまごは、どうなったのさ?どうしてかえらなかったのさ?」テンプルトンはするどい声をはりあけました。
「もともとかえらないたまごだったのよ」と、ガチョウのおばさんがいいました。
「そのたまごは、どうするんだい?」小さなビーズのようなまるい目でガチョウをじつと見ながら、テンプルトンがききました。
「あげてもいいよ。ころがしてって、あんたのへんてこなコレクションに加えたらいいさ」と、ガチョウのおばさんはこたえました。(テンプルトンは、農場にあるかわったものを拾いあつめて、しまっておくくせがありました)
「いいよ、いいよ、いいよ。たまごはやるよ。でも、一ついっとくけど、うちの子どもたちに、そのきたない鼻づらでちょっかいをだすようなことがあったら、これまでネズミがいちども経験したこともないようなひどい目にあわせてやるからな」
ガチョウのおじさんはそういうと、がんじょうなつばさをひろげてバサバサとゆらし、力を見せつけました。たしかに、ガチョウのおじさんは強くて勇敢でしたが、じつのところ、ガチョウ夫婦はテンプルトンに不安を感じていたのです。それも、むりのないことでした。このネズミは、よいこととわるいことの区別もつかなければ、良心も、気のとがめも、思いやりも、礼儀も、人情ならぬネズミの情けも、反省も、高次の感覚も、しんせつ心も、なんにも持ちあわせていなかったからです。テンプルトンが、見つかりさえしなければ平気で赤ちゃんをころすだろうことを、ガチョウは知っていました。それくらいのことは、誰でも知っていたのです。
ガチョウのおばさんは、かえらなかったたまごを大きなくちばしで巣からおしだしました。それをネズミがころがしていくのを、納屋のみんなはあきれ顔で見ていました。ほとんどなんでもすききらいなく食べるウィルバーでさえ、ぞっとしてつぶやきました。
「しょうもない、くさったたまごがほしいだなんて!」
「ネズミはネズミなのよね」とシャーロットはいい、けらけらと笑いました。「だけど、あの古いたまごが割れたりしたら、この納屋には住めなくなるわよ」
「どういう意味?」と、ウィルバーがたずねました。
「たまごがくさくて、ここにはだれも住めなくなるってことよ。くさったたまごは、におい爆弾みたいなものだからね」
「割ったりしないさ」と、テンプルトンがどなりかえしました。「自分のやってることくらいわかってるよ。こういうの、いつもあつかってるんだからさ」
テンプルトンは、ガチョウのたまごを前足でころがしながら、トンネルのなかに消えていきました。そして、おしたり、こづいたりしながら、えさ箱の下にある巣穴まで運んでいきました。
その日の午後、風がおさまると、納屋の前庭はしずかでぽかぽかとあたたかくなりました。灰色のガチョウのおばさんは、七羽のひなをつれて、外の世界へでていきました。ウィルバーの夕ごはんを運んできたザッカーマンのおじさんが、そのようすを見ていました。
「やあ、生まれたんだね!」おじさんはそういうと、にっこり笑いました。「さてと……一、二、三、四、五、六、七羽だな。ガチョウのひなが七羽。けっこう、けっこう!」
農場では、初夏のころが一年でいちばんさわやかで、しあわせな季節でした。ライラックの花がさいて、あまいかおりをただよわせてから、しぼみます。おなじころにリンゴの花がさき、ミツバチが木のまわりにあつまってきます。日ましにあたたかくなり、おだやかな日がつづきます。学校が休みに入ると、子どもたちは遊んだり、小川でマスを釣ったりする時間が持てるようになります。エイヴリーは、よくポケットにマスを入れて帰ってきました。長いことポケットに入れられていたマスは、なまあたたかく、かたくなっていましたが、フライにすれば夕ごはんのおかずになるのでした。
学校が休みになってからは、ファーンは毎日のようにウィルバーがいる納屋に通い、しずかにいすにすわって見ていました。動物たちはファーンを仲間だと思い、羊もファーンの足もとに、おだやかにねそべっていました。
七月のはじめには、農耕馬をつないだ草刈り機にザッカーマンのおじさんが乗りこみ、草場にでていきます。朝のあいだずっと、草刈り機はカタカタ音をさせながらぐるぐるとまわり、高くのびた草が刈られてバタバタとたおれていきました。翌日は、雷雨がこないかぎり、働き手は全員あつまって、刈った草をかきあつめて荷馬車に山とつみ、納屋まで運ぶのでした。ファーンとエイヴリーは、その干し草の山の上に乗っていっしょに納屋までいきました。納屋につくと、いいにおいのするあたたかい干し草は、広いロフトにつみあげられます。すると納屋じゅうが、牧草やクローバーのすてきなベッドのようになりました。干し草の山は、上にとび乗ってもおもしろいし、かくれるのにもちょうどいいのです。エイヴリーは、ときどき小さなアオヘビをみつけて、ほかのものといっしょにポケットにしまいこみました。
初夏は、小鳥たちにとっても楽しい季節でした。草場も、家のまわりも、納屋も、森も、沼も、小鳥たちの愛と歌と巣とたまごでいっぱいになります。森のはずれでは、ノドジロシトド(はるばるボストンからやってきたのでしょう)が、「ピーボディー、ピーボディー、ピーボディー!」とさけびます。リンゴの木の枝では、フェーベがしつぼをふって体をゆらしながら「フィービー、フィービー!」とうたいます。ウタヒメドリは、命がはかなく美しいのを知っているので、「スイート、スイート、スイート、インタールード!」(つかの間の楽しさ)と唱えます。納屋に入れば、巣からヒューッとおりてきたツバメに、「チーキー、チーキー!」(いたずらっ子)としかられます。
初夏には、子どもが食べたりのんだり、吸ったりかんだりするものが、たくさんありました。タンポポの茎にはミルクがいっぱいつまっているし、クローバーの花には蜜がたまっているし、冷蔵庫には冷たいのみものが入っています。どこをみても命にあふれていて、草の茎の小さな泡玉をつついても、なかから緑の虫があらわれました。ジャガイモの葉っぱの裏側には、ジャガイモハムシのあざやかなオレンジ色のたまごがついていました。
そんな初夏のある日、ガチョウのたまごがかえりました。納屋の地下室では、これは大事件です。ちょうどファーンもきていて、いすにすわって見ていました。
赤ちゃんが生まれたのに最初に気づいたのは、ガチョウのおばさんとシャーロットでした。ガチョウのおばさんは、まえの日からわかっていました。たまごのなかから、弱々しい声がきこえていたからです。殻のなかはとてもきゅうくつなので、早く外にでたいといっているのがわかりました。そこで、ガチョウのおばさんはじっとすわって、おしゃべりもいつもよりひかえていました。
いちばんはじめの赤ちゃんが、灰色と緑がまざったような色の頭をお母さんの羽のあいだからのぞかせて、あたりを見まわしたとき、シャーロットはそれを見つけていいました。
「ここに影うわたしたち全員は、友人のガチョウさんが、四週間ものたゆまぬ努力と忍耐のすえ、とうとう成果をあげられたことを知って、たいへんよろこばしく思うでしょう。赤ちゃんが生まれましたよ。心からのおよろこびを、わたしは申しあげますよ!」
「ありがとう、がとう、がとう!」
ガチョウのおばさんは、得意そうにうなずいたり、おじぎをしたりしました。
「ありがとさん」と、ガチョウのおじさんもいいました。
「おめでとう!赤ちゃんは何羽いるの?ぼくには一羽しか見えないけど」ウイルバーがさけびました。
「七羽よ」と、ガチョウのおばさんがいいました。
「いいわね!七は幸運の数ですもんね」と、シャーロットがいいました。
「運は関係ないわ。あたしの努力と、じょうずなやりくりのおかげだもの」と、ガチョウのおばさんがいいました。
このとき、ウィルバーのえさ箱の下のかくれ家から、テンプルトンが鼻づらをのぞかせました。テンプルトンはファーンにちらりと目をやり、壁の近くを通って、ガチョウのそばまで用心しいしいやってきました。だれもが、テンプルトンを見ていました。あんまり信用できないやつだと、みんな思っていたからです。
「ねえ、七羽っていったよね。たまごは八こあったじゃないか。もう一つのたまごは、どうなったのさ?どうしてかえらなかったのさ?」テンプルトンはするどい声をはりあけました。
「もともとかえらないたまごだったのよ」と、ガチョウのおばさんがいいました。
「そのたまごは、どうするんだい?」小さなビーズのようなまるい目でガチョウをじつと見ながら、テンプルトンがききました。
「あげてもいいよ。ころがしてって、あんたのへんてこなコレクションに加えたらいいさ」と、ガチョウのおばさんはこたえました。(テンプルトンは、農場にあるかわったものを拾いあつめて、しまっておくくせがありました)
「いいよ、いいよ、いいよ。たまごはやるよ。でも、一ついっとくけど、うちの子どもたちに、そのきたない鼻づらでちょっかいをだすようなことがあったら、これまでネズミがいちども経験したこともないようなひどい目にあわせてやるからな」
ガチョウのおじさんはそういうと、がんじょうなつばさをひろげてバサバサとゆらし、力を見せつけました。たしかに、ガチョウのおじさんは強くて勇敢でしたが、じつのところ、ガチョウ夫婦はテンプルトンに不安を感じていたのです。それも、むりのないことでした。このネズミは、よいこととわるいことの区別もつかなければ、良心も、気のとがめも、思いやりも、礼儀も、人情ならぬネズミの情けも、反省も、高次の感覚も、しんせつ心も、なんにも持ちあわせていなかったからです。テンプルトンが、見つかりさえしなければ平気で赤ちゃんをころすだろうことを、ガチョウは知っていました。それくらいのことは、誰でも知っていたのです。
ガチョウのおばさんは、かえらなかったたまごを大きなくちばしで巣からおしだしました。それをネズミがころがしていくのを、納屋のみんなはあきれ顔で見ていました。ほとんどなんでもすききらいなく食べるウィルバーでさえ、ぞっとしてつぶやきました。
「しょうもない、くさったたまごがほしいだなんて!」
「ネズミはネズミなのよね」とシャーロットはいい、けらけらと笑いました。「だけど、あの古いたまごが割れたりしたら、この納屋には住めなくなるわよ」
「どういう意味?」と、ウィルバーがたずねました。
「たまごがくさくて、ここにはだれも住めなくなるってことよ。くさったたまごは、におい爆弾みたいなものだからね」
「割ったりしないさ」と、テンプルトンがどなりかえしました。「自分のやってることくらいわかってるよ。こういうの、いつもあつかってるんだからさ」
テンプルトンは、ガチョウのたまごを前足でころがしながら、トンネルのなかに消えていきました。そして、おしたり、こづいたりしながら、えさ箱の下にある巣穴まで運んでいきました。
その日の午後、風がおさまると、納屋の前庭はしずかでぽかぽかとあたたかくなりました。灰色のガチョウのおばさんは、七羽のひなをつれて、外の世界へでていきました。ウィルバーの夕ごはんを運んできたザッカーマンのおじさんが、そのようすを見ていました。
「やあ、生まれたんだね!」おじさんはそういうと、にっこり笑いました。「さてと……一、二、三、四、五、六、七羽だな。ガチョウのひなが七羽。けっこう、けっこう!」
Charlotte's Web 7