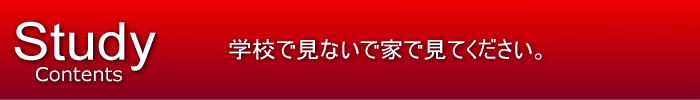Charlotte's Web 13
ⅩⅢ.Good Progress
(13.進歩)
Far into the night, while the other creatures slept, Charlotte worked on her web. First she ripped out a few of the orb lines near the center. She left the radial lines alone, as they were nedded for support. As she worked, her eight legs were a great help to her. So were her teeth. She loved to weave and she was an expert at it. When she was finished ripping things out, her web looked something like this:
(夜、ほかの動物たちがねしずまってからも、シャーロットはずっと文字を織りこむ仕事に精をだしていました。最初にまず、網のまんなかにあるぐるっと円をかくように張った糸を何本もとりのぞきました。放射状の糸は、全体をささえるのに必要なので、のこしておきます。シャーロットの八本の足は、とても役に立ちました。歯も大活躍です。シャーロットは網をつくるのが大すきだし、とてもじょうずでした。まんなかの部分をとりのぞくと、シャーロットの巣は左の絵のようになりました。)
A spider can produce several kinds of thread. She uses a dry, tough thread for foundation lines, and she uses a sticky thread for snare lines--the ones that catch and hold insects. Charlotte decided to use her dry thread for writing the new message.
(クモは、何種類かの糸をくりだすことができます。シャーロットは、ねばつかないじょうぶな糸で土台をつくり、虫をつかまえるわなの部分には、ねばねばした糸を使いました。新しいことばを織りこむのには、ねばつかない糸を使うことに決めました。)
"If I write the word 'Terrific' with sticky thread," she thought, "every bug that comes along will get stuck in it and spoil the effect."
(「もし、ねばねばの糸で『すばらしい』って書くとすると、とびこんできた虫がひっかかったら、だいなしになっちゃうもの」と、思ったのです。)
"Now let's see, the first letter is T."
(「さてと、最初はTの字ね」)
Charlotte climbed to a point at the top of the left hand side of the web. Swinging her spinnerets into position, she attached her thread and then dropped down. As she dropped, her spinning tubes went into action and she let out thread. At the bottom, she attached the thread. This formed the upright part of the letter T. Charlotte was not satisfied, however. She clombed up and made another attachment, right next to the first. Then she carried the line down, so that she had a double line instead of a single line. "It will show up better if I make the whole thing with double lines."
(シャーロットは網の左側のてっぺんまでのぼりました。紡績突起をゆらして糸を固定すると、下にさがります。さがると同時に紡績管が働いて、糸がでてきました。下までたどりつくと、また糸を固定します。これで、Tの字のたての線ができました。でも、シャーロットはまだ満足しませんでした。もういちど上までのぼり、さつきのすぐとなりに糸を固定し、またすーっと下におります。これで、たての線が二重になりました。「二重線で書いておけば、はっきりめだつわ」)
She climbed back up, moved over about an inch to the left, touched her spinnerets to the web, and then carried a line across to the right, forming the top of the T. She repeated this, making it double. Her eight legs were very busy helping.
(シャーロットはまた上までいき、さっきのところから二・五センチばかり左に糸を固定し、こんどは右に動きました。Tの字の横線ができました。同じ動きをくりかえして二重にします。八本の足がいそがしく動きまわります。)
"Now for the E !"
(「つぎはEの字よ」)
Charlotte got so interested in her work, she began to talk to herself, as though to cheer herself on. If you had been sitting quietly in the barn cellar that evening, you would have heard something like this:
(シャーロットはこの仕事に夢中になり、自分を元気づけるみたいに、ひとりごとをいいはじめました。その夜、納屋の地下にしずかにすわっていれば、こんな声がきこえたはずです。)
"Now for the R! Up we go! Attach! Descend! Pay out line! Whoa! Attach! Good! Up you go! Repeat! Attach! Descend! Pay out line. Whoa, girl! Steady now! Attach! Now right and down and swing that loop and around and around! Now in to the left! Attach! Climb! Repeat! O.K! Easy, keep those lines together! Now, then, out and down for the leg of the R! Pay out line! Whoa! Attach! Ascend! Repeat! Good girl!"
(「さあ、こんどはR!上へいって、糸をくっつけて、さがって、糸をくりだして、とまって糸をくっつけて。できたわ!上へいって、くりかえすのよ。糸をくっつけて、さがって糸をくりだして、とまって、おちついて糸をくつける。もういちど上へいって、こんどは右へ糸をくりだして、とまってくっつける。こんどは右ね。糸をくりだして、くっつける。それから右下へおりて、くるっとまわる。さあ、こんどは左よ。くっつけて、ヒへいって、くりかえして、いいわ!さてと、この二本をたばねて、つぎはRの字の足ね。糸をくりだして、とまって、くっつけて、上へいって、くりかえし。うまくいったわ!」)
And so, talking to herself, the spider worked at her difficult task. When it was completed, she felt hungry. She ate a small bug that she had been saving. Then she slept.
(シャーロットは、こんなふうにひとりごとをいいながら、むずかしい仕事を進めていきました。ようやく文字を書きおわったときには、おなかがぺこぺこになっていました。そこで、とっておいた虫を食べて、ねむりました。)
Next morning, Wilbur arose and stood beneath the web. He breathed the morning air into his lungs. Drops of dew, catching the sun, made the web stand out clearly. When Lurvy arrived with breakfast, there was the handsome pig, and over him, woven neatly in block letters, was the word TERRIFIC. Another miracle.
(つぎの朝、起きあがったウィルバーは、クモの巣の下に立ちました。朝の空気を胸いっぱいに吸いこみます。朝露が口の光をうけて、クモの巣ははっきり見えていました。ラーヴィーが朝ごはんをもってやってきたとき、納屋にはころころしたブタがいて、その頭上には、きれいな活字体の文字で『すばらしい』と書いてありました。また奇跡が起こったのです。)
Lurvy rushed and called Mr. Zuckerman. Mr. Zuckerman rushed and called Mrs. Zuckerman. Mrs. Zuckerman ran to the phone and called the Arables. The Arables climbed into their truck and hurried over. Everybody stood at the pigpen and stared at the web ans read the word, over and over, while Wilbur, who really felt terrific, stood quietly swelling out his chest and swinging his snout from from side to side.
(ラーヴィーは、いそいでザッカーマンのおじさんに知らせました。おじさんは、いそいでおばさんをよびにいきました。おばさんは、いそいでエラブルさんに電話をしました。エラブル一家がトラックに乗って、いそいでやってきました。みんなブタ小屋のまえに立ち、クモの巣をながめ、何度も何度も文字を読みました。そのあいだ、すばらしく気分がよかったウィルバーはしずかに立って胸をつきだし、鼻先を右へ左へとゆらしていました。)
"Terrific!" breathed Zuckerman, in joyful admiration. "Edith, you better phone the reporter on the Weekly Chronicle and tell him what has happened. He will want to know about this. He may want to bring a photographer. There isn't a pig in the whole state that is as terrific as our pig."
(「『すばらしい』だと!」ザッカーマンのおじさんが、感心した声でいいました。「イーディス、週刊新聞の記者に電話をして、なにが起こったか、話してやるといい。記事にしたがるぞ。もしかしたら、カメラマンもつれてくるかもしれん。なにしろ、うちのブタほどすばらしいのは、州のどこをさがしたっていないんだからな」)
The news spread. People who had journeyed to see Wilbur when he was "some pig" came back again to see him now that he was "terrific."
(ニュースはすぐに知れわたりました。ウィルバーが「たいしたブタ」だったときに見にきた人たちが、こんどは「すばらしい」ブタを見るために、またやってきました。)
Rhat afternoon, when Mr. Zuckerman went to milk the cows and clean out the tie-ups, he was still thinking about what a wondrous pig he owned.
(その午後、乳しぼりとそうじのために牛小屋にでかけたザッカーマンのおじさんは、自分がすばらしいブタを持っている幸運について考えつづけていました。)
"Lurvy!" he called. "There is to be no more cow manure thrown down into that pigpen. I have a terrific pig. I want that pig to have clean, bright straw every day for his bedding. Understand?"
(「ラーヴイー!牛のふんは、もうブタのかこいに入れなくていいからな。うちのは、すばらしいブタなんだ。寝床には、きれいなわらを毎日入れてやってくれ。わかったかい?」ザッカーマンさんがいいました。)
"Yes, sir," said Lurvy.
(「わかりました」ラーヴィーがこたえました。)
"Furthermore," said Mr. Zuckerman, "I want you to start building a crate for Wilbur. I have decided to take the pig to the Country Fair on September sixth. Make the crate large and paint it green with gold letters!"
(「それから」と、ザッカーマンさんはつづけました。「ウィルバーを入れる木箱をつくってくれ。あのブタを、九月六日の品評会にだすことにしたからな。大きな木箱をつくって緑色にぬり、金色の文字を入れるんだ」)
"What will the letters say?" asked Lurvy.
(「文字はなんと?」ラーヴィーがたずねました。)
"They should say Zuckerman's Famous Pig."
(「『ザッカーマンの有名なブタ』と書いてくれ」)
Lurvy picked up a pitchfork and walked away to get some clean straw. Having such an important pig was going to mean plenty of extra work, he could see that.
(ラーヴイーは、くまでをかついで、きれいなわらをとりにいきました。りっぱなブタがいると、いろいろと用事がふえるものです。)
Below the apple orchard, at the end of a path, was the dump where Mr. Zuckerman threw all sorts of trash and stuff that nobody wanted any more. Here, in a small clearing hidden by young alders and wild raspberry bushes, was an astonishing pile of old bottles and empty tin cans and dirty rags and bits of metal and broken bottles and broken hinges and broken springs and dead batteries and last month's magazines and old discarded dishmops and tattered overalls and rusty spikes and leaky pails and forgotten stoppers and useless junk of all kinds, including a wrong-size crank for a broken ice-cream freezer.
(リンゴ畑のむこうの、小道のつきあたりにはゴミ捨て場があって、ザッカーマンさんは、もうだれも使わなくなったゴミをそこに捨てていました。ハンノキの若木と野生のキイチゴのかげになったそのゴミ捨て場には、古いびん、あき缶、ぼろきれ、金属の破片、割れたびん、こわれたちょうつがい、こわれたばね、きれた乾電池、古雑誌、用ずみになった鵬灘いのモップ、すりきれた作業ズボン、さびたくぎ、水がもるバケツ、使えなくなったおふろの襟といった、あらゆる働郷の役に立たないガラクタがつみかさなっていました。なかには、こわれたアイスクリーム製造器についていたサイズちがいのハンドルなんていうものもありました。)
Templeton knew the dump and liked it. There were good hiding places there--excellent cover for a rat. And there was usually a tin can with food still clinging to the inside.
(このゴミ捨て場は、テンプルトンがなわばりにしているお気に入りの場所でした。かくれる場所もたくさんあって、ネズミにとっては、とても都合がよかったんどえす。それに、空き缶の内側には、たいていまだ食べ物がくっついていました。)
Templeton was down there now, rummanging around. When he returned to the barn, he carried in his mouth an advertisement he had torn from a crumpled magazine.
(テンプルトンはゴミ捨て場にいって、あちこちかきまわしました。そして納屋に戻ってきたときには、しわくちゃの雑誌から切りとった広告を口にくわえていました。)
"How's this?" he asked, showing the ad to Charlotte. "It says 'Crunchy.' 'Crunchy' would be a good word to write in your web."
(「これは、どうだい?」テンプルトンはそういいながら、広告をシャーロットに見せました。「『ぱりっとした』って書いてあるんだ。これを網のなかに書いたらいいよ」)
"Just the wrong idea," replied Charlotte. "Couldn't be worse. We don't want Zuckerman to think Wilbur is crunchy. He might start thinking about crisp, crunchy bacon and tasty ham. That would put ideas into his head. We must advertise Wilbur's noble qualities, not his tastiness. Go get another word, please, Templeton!"
(「あらだめよ。それはまずいわ。ウィルバーの肉が、焼いたらパリッとおいしいかもしれないなんて、ザッカーマンさんが思ったらこまるでしょ。パリパリに焼いたベーコンやソーセージを連想しちゃうかもしれないもの。そんな文字にしたらヒントをあげるようなものだわ。わたしたちは、ウィルバーがおいしいかどうかじゃなくて、ウィルバーカすばらしいブタだってことを宣伝しなくちゃいけないのよ。ほかのことばをさがしてきてちょうだい。おねがいよ、テンプルトン」シャーロットがいいました。)
The rat looked disgusted. But he sneaked away to the dump and was back in a while with a strip of cotton cloth. "How's this?" he asked. "It's a label off an old shirt."
(ネズミは、うんざりした顔をしました。けれども、またでていって、こんどはもめんの布きれを持ってきました。「これは、どうだい?古いシャツのラベルなんだ」)
Charlotte examined the label. It said PRE-SHRUNK.
(シャーロットは、ラベルを見てみました。防縮加工と書いてあります。)
I'm sorry,Templeton," she said, "but 'Pre-shrunk' is out of the question. We want Zuckerman to think Wilbur is nicely filled out, not all shrunk up. I'll have to ask you to try again."
(「わるいけど、『防縮加工』は使えないわ。ウィルバーは縮むんじゃなくて、はちきれんばかりに大きくなってるって、ザッカーマンさんに思わせなくちゃ。もういちど、いってきてちょうだいな」)
"What do you think I am, a messager boy?" grumbled the rat. "I'm not going to spend all my time chasing down to the dump after advertising material."
(「おれのこと、つかいっぱしりのこぞうかなんかだと思ってるな」と、ネズミは文句をいいました。「一日中広告をさがして、ゴミ捨て場をうろつくわけにはいかないんだぞ」)
"Just once more--please!" said Charlotte.
(「おねがいよ、もう一度だけいってきて、ね」と、シャーロットはたのみました。)
"I'll tell you what I'll do," said Templeton. "I know where there's a package of soap flakes in the woodshed. It has writing on it. I'll bring you a piece of the package."
(「じゃあ、こうしよう」と、テンプルトンがいいました。「薪小屋に粉せっけんの箱がある。その箱に字が書いてあったから、それを持ってきてやるよ」)
He climbed the rope that hung on the wall and disappeared through a hole in the celing. When he came back he had a strip of blue-and-white cardboard in his teeth.
(テンプルトンは、壁ぎわにさがったロープをよじのぼると、天井の穴にすがたを消しました。もどってきたときには、青と白のボール紙の破片をくわえていました。)
"There!" he said, triumphantly. "How's that?"
(「そら!どうだい?」テンプルトンは、勝ちほこったようにいいました。)
Charlotte read the words: "With New Radiant Action."
(シャーロットは、書いてある文字を読みました。「すばやくぴかぴか」)
"What does it mean?" asked Charlotte, who had never used any soap flakes in her life.
(「どういう意味なの?」粉せっけんなど、これまでにいちども使ワたことのないシャーロットはききました。)
"How should I know?" said Templeton. "You asked for words and I brought them. I suppose the next thing you'll want me to fetch is a dictionary."
(「おれにわかるはずないだろう。宣伝文句がほしいっていうから、持ってきてやっただけさ。このぶんじゃ、つぎは辞書を持ってきてくれっていうんじゃないのか?」)
Together they studied the soap ad. "'With new radiant action,'" repeated Charlotte, slowly. "Wilbur!" she called.
(ふたりは、粉せっけんの宣伝文句をじっくりと研究してみました。「すばやくぴかぴか……。ねえ、ウィルバー!」シャーロットがウィルバーをよびました。)
Wilbur, who was asleep in the straw, jumped up.
(わらのなかでねむっていたウィルバーは、とび起きました。)
"Run around!" commanded Charlotte. "I want to see you in action, to see if you are radiant."
(「そこらを走ってみて!」シャーロットが命令しました。「動いたら、ぴかぴかに見えるかしら?」)
Wilbur raced to the end of his yard.
(ウィルバーは、かこいのはしまで走りました。)
"Now back again, faster!" said Charlotte.
(「もどってきて、もっとはやく!」シャーロットはいいました。)
Wilbur galloped back. His skin shone. His tail had a fine, tight curl in it.
(ウィルバーは駆けもどりました。はだがつやつやして、しつぼはきゅつとまるまっています。)
"Jump into the air!" cried Charlotte.
(「とびあがってみて!」シャーロットがさけびました。)
Wilbur jumped as high as he could.
(ウィルバーは、できるだけ高くとびあがってみました。)
"Keep your knees straight and touch the ground with your ears!" called Charlotte.
(「ひざをまげないで、耳を地面につけてみて!」と、シャーロット。)
Wilbur obeyed.
(ウィルバーは、いわれたとおりにしました。)
"Do a back flip with a half twist in it!" cried Charlotte.
(「うしろ宙がえりで体を半分ひねってみて!」)
Wilbur went over backwards, writhing and twisting as he went.
(ウィルバーは、体をよじったりひねったりしながら、うしろ宙がえりをしてみせました。)
"O.K.,Wilbur," said Charlotte. "You can go back to sleep. O.K., Templeton, the soap ad will do, I guess. I'm not sure Wilbur's action is exactly radiant, but it's interesting."
(「オーケー、ウィルバー。もう寝床にもどっていいわ」と、シャーロットがいいました。「テンプルトン、粉せっけんの広告でいいみたいね。ウィルバーの動きがぴかぴかかどうかはわからないけど、なかなかおもしろかったわ」)
"Actuallu," said Wilbur, "I feel radiant."
(「ぼく、なんだかぴかぴかのかんじがしてきたよ」と、ウィルバーはいいました。)
"Do you?" said Charlotte, looking at him with affection. "Well, you're a good little pig, and radiant you shall be. I'm in this thing pretty deep now--I might as well go the limit."
(「ほんとに?」シャーロットは、いとおしそうに子ブタを見ながらいいました。「あなたは、すてきな子ブタだし、そのうちぴかぴかになるわ、きっと。どうせこの計画は進めなくちゃならないんだから、少しおおげさにいったっていいわよね」)
Tired from his romp, Wilbur lay down in the clean straw. He closed his eyes. The straw seemed scratchy--not as comfortable as the cow manure, which was always delightfully soft to lie in. So he pushed the straw to one side and stretched out in the manure. Wilbur sighed. It had been a busy day--his first day of being terrific. Dozens of people had visited his yard during the afternoon, and he had had to stand and pose, looking as terrific as he could. Now he was tired. Fern had arrived and seated herself quietly on her stool in the corner.
(はねまわってつかれたウィルバーは、きれいなわらの上に横になり、目をつぶりました。わらは、ちくちくしました。やわらかい牛のふんほど気持ちがよくありません。そこで、ウィルバーはわらをどけて、牛ふんの上にねそべりました。ウィルバーは、ため息をつきました。「すばらしい」ブタの最初の日も、いそがしい}日でした。午後には、何十人もの人間がやってきたので、できるだけすばらしいかっこうをして、立っていなければならなかったのです。そんなこんなでウィルバーはくたびれていました。いつのまにかファーンがやってきて、すみのこしかけにそっとすわっていました。)
"Tell me a story, Charlotte!" said Wilbur, as he lay waiting for sleep to come. "Tell me a story!"
(「ねえ、シャーロット、お話ししてよ。お話がききたいよ」ねる用意ができたウィルバーがたのみました。)
So Charlotte, although she, too, was tired, did what Wilbur wanted.
(そこでシャーロットは、自分もくたびれていたのですが、ウィルバーのねがいをきいてやりました。)
"Once upon a time," she began, "I had a beautiful cousin who managed to build her web across a small stream. One day a tiny fish leaped into the air and got tangled in the web. My cousin was very much surprised, of course. The fish was thrashing wildly. My cousin hardly dared tackle it. But she did. She swooped down and threw great masses of wrapping material around the fish and fought bravely to capture it."
(「むかしむかし、わたしのいとこで、とても美しいクモがいました。そのクモは、小川の上に巣をかけました。ある日、水からぴょんととびあがった小さな魚が、その巣にひっかかってしまいました。わたしのいとこは、びつくりしました。魚は、バタバタとあばれました。いとこは、その魚をなかなかおさえられませんでした。でも、なんとかしなくてはなりません。いとこは、下までおりていって網をどんどんくりだし、魚をがんじがらめにして、つかまえようとしました」)
"Did she succeed?" asked Wilbur.
(「うまくいったの?」と、ウィルバーはたずねました。)
"It was a never-to-be-forgotten battle," said Charlotte. "There was the fish, caught only by one fin, and its tail wildly thrashing and shining in the sun. There was the web, sagging dangerously under the weight of the fish.
(「わすれようとしても、わすれられない戦いになったのよ」と、シャーロットは話をつづけました。「魚はひれの一つが網にひっかかっていたのですが、うろこをきらめかせながら、しっぽをバタバタふっていました。魚の重みで、網はやぶけそうでした」)
"How much did the fish weigh?" asked Wilbur eagerly.
(「その魚はどれくらいの重さだったの?」と、ウィルバーは興味しんしんでたずねました。 )
"I don't know," said Charlotte. "There was my cousin, slipping in, dodging out, beaten mercilessly over the head by the wildly thrashing fish, dancing in, dancing out, throwing her threads and fighting hard. First she threw a left around the tail. The fish lashed back. Then a left to the tail and a right to the midsection. The fish lashed back. Then she dodged to one side and threw a right, and another right to the fin. Then a hard left to the head, while the web swayed and stretched."
(「さあ、わからないわ。わたしのいとこは、しのびよるかと思うと、さっと攻撃をかわし、あばれる魚に頭を容赦なくたたかれても、かろやかに近づいたりはなれたりしながら糸をくりだして、勇敢に戦いました。まずは魚のしっぽをめがけて、左のパンチ。魚も打ちかえします。つぎに左のパンチをしつぼにあびせたと思うと、右のパンチで胴体攻撃。魚が打ちかえす。いとこは、すばやくその攻撃をかわし、右のパンチ。そして、ひれにも、もう一発。つづいて、強烈な左のパンチを頭にくらわせたので、網がゆれて、ビヨーンとのびました」)
"Then what happened?" asked Wilbur.
(「それから、どうなったの?」と、ウィルバーはたずねました。)
"Nothing," said Charlotte. "The fish lost the fight. My cousin wrapped it up so tight it couldn't budge."
(「どうもしないわ。魚が負けたのよ。わたしのいとこが魚をぐるぐるまきにしたので、身動きがとれなくなっちゃったの」)
"Then what happened?" asked Wilbur.
(「それから、どうなったの?」)
"Nothing," said Charlotte. "My cousin kept the fish for a while, and then, when she got good and ready, she ate it."
(「どうもしないわ。いとこは、しばらく魚をそのままおいといたんだけど、そのうちちょうどいいころあいになったから、食べちゃったのよ」)
"Tell me another story!" begged Wilbur.
(「もう一つ、お話ししてよ!」ウィルバーがせがみました。)
So Charlotte told him about another cousin of hers who was an aeronaut.
(そこでシャーロットは、またべつのいとこの話をしました。こんどのいとこは、気球乗りでした。)
"What is an aeronaut?" asked Wilbur.
(「それ、どんな仕事なの?」と、ウィルバーがたずねました。)
"A balloonist," said Charlotte. "My cousin used to stand on her head and let out enough thread to form a balloon. Then she'd let go and be lifted into the air and carried upward on the warm wind."
(「気球に乗って空をとぶのよ。このいとこは、さかだちをして、いっぱい糸をくりだし、気球をつくったの。それからその気球といっしょに、あたたかい風に乗って旅をしたの」)
"Is that true?" asked Wilbur. "Or are you just making it up?"
(「それって、ほんとの話なの?それとも、つくり話なの?」ウィルバーはたずねました。
)
"It's true," replied Charlotte. "I have some very remarkable cousins. And now, Wilbur, it's time you went to sleep."
(「ほんとの話よ。わたしには、すごいいとこが何人もいるのよ。さあ、ウィルバー、もうねる時間よ」)
"Sing something!" begged Wilbur, closing his eyes.
(「だったら、なにかうたってよ」目をつぶりながら、ウィルバーはせがみました。)
So Charlotte sang a lullaby, while crickets chirped in the grass and the barn grew dark. This was the song she sang.
(そこでシャーロットは、こもり歌をうたってくれました。草のなかではコオロギが鳴き、納屋は暗くなっていました。シャーロットがうたったのは、こんな歌でした。)
"Sleep, sleep, my love, my only,
(おやすみ、おやすみ、いい子だね)
Deep, deep, in the dung and the dark;
(暗闇につつまれて、牛ふんの上で)
Be not afraid and be not lonely!
(心配しないで、さびしがらないで)
This is the hour when frogs and thrushes
(カエルやツグミは森や草地で)
Praise the world from the woods and the rushes.
(美しい世界をたたえているよ)
Rest from care, my one and only,
(ぐっすりおやすみ、やすらかに)
Deep in the dung and the dark!"
(暗闇に包まれて、牛ふんの上で )
But Wilbur was already asleep. When the song ended, Fern got up and went home.
(けれども、歌がおわらないうちに、ウィルバーは、もうぐっすりねむっていました。シャーロットの歌がおわると、ファーンは立ちあがって家に帰りました。)
英文のみです。
日本語訳のみです。
Charlotte's Web 14
(13.進歩)
Far into the night, while the other creatures slept, Charlotte worked on her web. First she ripped out a few of the orb lines near the center. She left the radial lines alone, as they were nedded for support. As she worked, her eight legs were a great help to her. So were her teeth. She loved to weave and she was an expert at it. When she was finished ripping things out, her web looked something like this:
(夜、ほかの動物たちがねしずまってからも、シャーロットはずっと文字を織りこむ仕事に精をだしていました。最初にまず、網のまんなかにあるぐるっと円をかくように張った糸を何本もとりのぞきました。放射状の糸は、全体をささえるのに必要なので、のこしておきます。シャーロットの八本の足は、とても役に立ちました。歯も大活躍です。シャーロットは網をつくるのが大すきだし、とてもじょうずでした。まんなかの部分をとりのぞくと、シャーロットの巣は左の絵のようになりました。)
A spider can produce several kinds of thread. She uses a dry, tough thread for foundation lines, and she uses a sticky thread for snare lines--the ones that catch and hold insects. Charlotte decided to use her dry thread for writing the new message.
(クモは、何種類かの糸をくりだすことができます。シャーロットは、ねばつかないじょうぶな糸で土台をつくり、虫をつかまえるわなの部分には、ねばねばした糸を使いました。新しいことばを織りこむのには、ねばつかない糸を使うことに決めました。)
"If I write the word 'Terrific' with sticky thread," she thought, "every bug that comes along will get stuck in it and spoil the effect."
(「もし、ねばねばの糸で『すばらしい』って書くとすると、とびこんできた虫がひっかかったら、だいなしになっちゃうもの」と、思ったのです。)
"Now let's see, the first letter is T."
(「さてと、最初はTの字ね」)
Charlotte climbed to a point at the top of the left hand side of the web. Swinging her spinnerets into position, she attached her thread and then dropped down. As she dropped, her spinning tubes went into action and she let out thread. At the bottom, she attached the thread. This formed the upright part of the letter T. Charlotte was not satisfied, however. She clombed up and made another attachment, right next to the first. Then she carried the line down, so that she had a double line instead of a single line. "It will show up better if I make the whole thing with double lines."
(シャーロットは網の左側のてっぺんまでのぼりました。紡績突起をゆらして糸を固定すると、下にさがります。さがると同時に紡績管が働いて、糸がでてきました。下までたどりつくと、また糸を固定します。これで、Tの字のたての線ができました。でも、シャーロットはまだ満足しませんでした。もういちど上までのぼり、さつきのすぐとなりに糸を固定し、またすーっと下におります。これで、たての線が二重になりました。「二重線で書いておけば、はっきりめだつわ」)
She climbed back up, moved over about an inch to the left, touched her spinnerets to the web, and then carried a line across to the right, forming the top of the T. She repeated this, making it double. Her eight legs were very busy helping.
(シャーロットはまた上までいき、さっきのところから二・五センチばかり左に糸を固定し、こんどは右に動きました。Tの字の横線ができました。同じ動きをくりかえして二重にします。八本の足がいそがしく動きまわります。)
"Now for the E !"
(「つぎはEの字よ」)
Charlotte got so interested in her work, she began to talk to herself, as though to cheer herself on. If you had been sitting quietly in the barn cellar that evening, you would have heard something like this:
(シャーロットはこの仕事に夢中になり、自分を元気づけるみたいに、ひとりごとをいいはじめました。その夜、納屋の地下にしずかにすわっていれば、こんな声がきこえたはずです。)
"Now for the R! Up we go! Attach! Descend! Pay out line! Whoa! Attach! Good! Up you go! Repeat! Attach! Descend! Pay out line. Whoa, girl! Steady now! Attach! Now right and down and swing that loop and around and around! Now in to the left! Attach! Climb! Repeat! O.K! Easy, keep those lines together! Now, then, out and down for the leg of the R! Pay out line! Whoa! Attach! Ascend! Repeat! Good girl!"
(「さあ、こんどはR!上へいって、糸をくっつけて、さがって、糸をくりだして、とまって糸をくっつけて。できたわ!上へいって、くりかえすのよ。糸をくっつけて、さがって糸をくりだして、とまって、おちついて糸をくつける。もういちど上へいって、こんどは右へ糸をくりだして、とまってくっつける。こんどは右ね。糸をくりだして、くっつける。それから右下へおりて、くるっとまわる。さあ、こんどは左よ。くっつけて、ヒへいって、くりかえして、いいわ!さてと、この二本をたばねて、つぎはRの字の足ね。糸をくりだして、とまって、くっつけて、上へいって、くりかえし。うまくいったわ!」)
And so, talking to herself, the spider worked at her difficult task. When it was completed, she felt hungry. She ate a small bug that she had been saving. Then she slept.
(シャーロットは、こんなふうにひとりごとをいいながら、むずかしい仕事を進めていきました。ようやく文字を書きおわったときには、おなかがぺこぺこになっていました。そこで、とっておいた虫を食べて、ねむりました。)
Next morning, Wilbur arose and stood beneath the web. He breathed the morning air into his lungs. Drops of dew, catching the sun, made the web stand out clearly. When Lurvy arrived with breakfast, there was the handsome pig, and over him, woven neatly in block letters, was the word TERRIFIC. Another miracle.
(つぎの朝、起きあがったウィルバーは、クモの巣の下に立ちました。朝の空気を胸いっぱいに吸いこみます。朝露が口の光をうけて、クモの巣ははっきり見えていました。ラーヴィーが朝ごはんをもってやってきたとき、納屋にはころころしたブタがいて、その頭上には、きれいな活字体の文字で『すばらしい』と書いてありました。また奇跡が起こったのです。)
Lurvy rushed and called Mr. Zuckerman. Mr. Zuckerman rushed and called Mrs. Zuckerman. Mrs. Zuckerman ran to the phone and called the Arables. The Arables climbed into their truck and hurried over. Everybody stood at the pigpen and stared at the web ans read the word, over and over, while Wilbur, who really felt terrific, stood quietly swelling out his chest and swinging his snout from from side to side.
(ラーヴィーは、いそいでザッカーマンのおじさんに知らせました。おじさんは、いそいでおばさんをよびにいきました。おばさんは、いそいでエラブルさんに電話をしました。エラブル一家がトラックに乗って、いそいでやってきました。みんなブタ小屋のまえに立ち、クモの巣をながめ、何度も何度も文字を読みました。そのあいだ、すばらしく気分がよかったウィルバーはしずかに立って胸をつきだし、鼻先を右へ左へとゆらしていました。)
"Terrific!" breathed Zuckerman, in joyful admiration. "Edith, you better phone the reporter on the Weekly Chronicle and tell him what has happened. He will want to know about this. He may want to bring a photographer. There isn't a pig in the whole state that is as terrific as our pig."
(「『すばらしい』だと!」ザッカーマンのおじさんが、感心した声でいいました。「イーディス、週刊新聞の記者に電話をして、なにが起こったか、話してやるといい。記事にしたがるぞ。もしかしたら、カメラマンもつれてくるかもしれん。なにしろ、うちのブタほどすばらしいのは、州のどこをさがしたっていないんだからな」)
The news spread. People who had journeyed to see Wilbur when he was "some pig" came back again to see him now that he was "terrific."
(ニュースはすぐに知れわたりました。ウィルバーが「たいしたブタ」だったときに見にきた人たちが、こんどは「すばらしい」ブタを見るために、またやってきました。)
Rhat afternoon, when Mr. Zuckerman went to milk the cows and clean out the tie-ups, he was still thinking about what a wondrous pig he owned.
(その午後、乳しぼりとそうじのために牛小屋にでかけたザッカーマンのおじさんは、自分がすばらしいブタを持っている幸運について考えつづけていました。)
"Lurvy!" he called. "There is to be no more cow manure thrown down into that pigpen. I have a terrific pig. I want that pig to have clean, bright straw every day for his bedding. Understand?"
(「ラーヴイー!牛のふんは、もうブタのかこいに入れなくていいからな。うちのは、すばらしいブタなんだ。寝床には、きれいなわらを毎日入れてやってくれ。わかったかい?」ザッカーマンさんがいいました。)
"Yes, sir," said Lurvy.
(「わかりました」ラーヴィーがこたえました。)
"Furthermore," said Mr. Zuckerman, "I want you to start building a crate for Wilbur. I have decided to take the pig to the Country Fair on September sixth. Make the crate large and paint it green with gold letters!"
(「それから」と、ザッカーマンさんはつづけました。「ウィルバーを入れる木箱をつくってくれ。あのブタを、九月六日の品評会にだすことにしたからな。大きな木箱をつくって緑色にぬり、金色の文字を入れるんだ」)
"What will the letters say?" asked Lurvy.
(「文字はなんと?」ラーヴィーがたずねました。)
"They should say Zuckerman's Famous Pig."
(「『ザッカーマンの有名なブタ』と書いてくれ」)
Lurvy picked up a pitchfork and walked away to get some clean straw. Having such an important pig was going to mean plenty of extra work, he could see that.
(ラーヴイーは、くまでをかついで、きれいなわらをとりにいきました。りっぱなブタがいると、いろいろと用事がふえるものです。)
Below the apple orchard, at the end of a path, was the dump where Mr. Zuckerman threw all sorts of trash and stuff that nobody wanted any more. Here, in a small clearing hidden by young alders and wild raspberry bushes, was an astonishing pile of old bottles and empty tin cans and dirty rags and bits of metal and broken bottles and broken hinges and broken springs and dead batteries and last month's magazines and old discarded dishmops and tattered overalls and rusty spikes and leaky pails and forgotten stoppers and useless junk of all kinds, including a wrong-size crank for a broken ice-cream freezer.
(リンゴ畑のむこうの、小道のつきあたりにはゴミ捨て場があって、ザッカーマンさんは、もうだれも使わなくなったゴミをそこに捨てていました。ハンノキの若木と野生のキイチゴのかげになったそのゴミ捨て場には、古いびん、あき缶、ぼろきれ、金属の破片、割れたびん、こわれたちょうつがい、こわれたばね、きれた乾電池、古雑誌、用ずみになった鵬灘いのモップ、すりきれた作業ズボン、さびたくぎ、水がもるバケツ、使えなくなったおふろの襟といった、あらゆる働郷の役に立たないガラクタがつみかさなっていました。なかには、こわれたアイスクリーム製造器についていたサイズちがいのハンドルなんていうものもありました。)
Templeton knew the dump and liked it. There were good hiding places there--excellent cover for a rat. And there was usually a tin can with food still clinging to the inside.
(このゴミ捨て場は、テンプルトンがなわばりにしているお気に入りの場所でした。かくれる場所もたくさんあって、ネズミにとっては、とても都合がよかったんどえす。それに、空き缶の内側には、たいていまだ食べ物がくっついていました。)
Templeton was down there now, rummanging around. When he returned to the barn, he carried in his mouth an advertisement he had torn from a crumpled magazine.
(テンプルトンはゴミ捨て場にいって、あちこちかきまわしました。そして納屋に戻ってきたときには、しわくちゃの雑誌から切りとった広告を口にくわえていました。)
"How's this?" he asked, showing the ad to Charlotte. "It says 'Crunchy.' 'Crunchy' would be a good word to write in your web."
(「これは、どうだい?」テンプルトンはそういいながら、広告をシャーロットに見せました。「『ぱりっとした』って書いてあるんだ。これを網のなかに書いたらいいよ」)
"Just the wrong idea," replied Charlotte. "Couldn't be worse. We don't want Zuckerman to think Wilbur is crunchy. He might start thinking about crisp, crunchy bacon and tasty ham. That would put ideas into his head. We must advertise Wilbur's noble qualities, not his tastiness. Go get another word, please, Templeton!"
(「あらだめよ。それはまずいわ。ウィルバーの肉が、焼いたらパリッとおいしいかもしれないなんて、ザッカーマンさんが思ったらこまるでしょ。パリパリに焼いたベーコンやソーセージを連想しちゃうかもしれないもの。そんな文字にしたらヒントをあげるようなものだわ。わたしたちは、ウィルバーがおいしいかどうかじゃなくて、ウィルバーカすばらしいブタだってことを宣伝しなくちゃいけないのよ。ほかのことばをさがしてきてちょうだい。おねがいよ、テンプルトン」シャーロットがいいました。)
The rat looked disgusted. But he sneaked away to the dump and was back in a while with a strip of cotton cloth. "How's this?" he asked. "It's a label off an old shirt."
(ネズミは、うんざりした顔をしました。けれども、またでていって、こんどはもめんの布きれを持ってきました。「これは、どうだい?古いシャツのラベルなんだ」)
Charlotte examined the label. It said PRE-SHRUNK.
(シャーロットは、ラベルを見てみました。防縮加工と書いてあります。)
I'm sorry,Templeton," she said, "but 'Pre-shrunk' is out of the question. We want Zuckerman to think Wilbur is nicely filled out, not all shrunk up. I'll have to ask you to try again."
(「わるいけど、『防縮加工』は使えないわ。ウィルバーは縮むんじゃなくて、はちきれんばかりに大きくなってるって、ザッカーマンさんに思わせなくちゃ。もういちど、いってきてちょうだいな」)
"What do you think I am, a messager boy?" grumbled the rat. "I'm not going to spend all my time chasing down to the dump after advertising material."
(「おれのこと、つかいっぱしりのこぞうかなんかだと思ってるな」と、ネズミは文句をいいました。「一日中広告をさがして、ゴミ捨て場をうろつくわけにはいかないんだぞ」)
"Just once more--please!" said Charlotte.
(「おねがいよ、もう一度だけいってきて、ね」と、シャーロットはたのみました。)
"I'll tell you what I'll do," said Templeton. "I know where there's a package of soap flakes in the woodshed. It has writing on it. I'll bring you a piece of the package."
(「じゃあ、こうしよう」と、テンプルトンがいいました。「薪小屋に粉せっけんの箱がある。その箱に字が書いてあったから、それを持ってきてやるよ」)
He climbed the rope that hung on the wall and disappeared through a hole in the celing. When he came back he had a strip of blue-and-white cardboard in his teeth.
(テンプルトンは、壁ぎわにさがったロープをよじのぼると、天井の穴にすがたを消しました。もどってきたときには、青と白のボール紙の破片をくわえていました。)
"There!" he said, triumphantly. "How's that?"
(「そら!どうだい?」テンプルトンは、勝ちほこったようにいいました。)
Charlotte read the words: "With New Radiant Action."
(シャーロットは、書いてある文字を読みました。「すばやくぴかぴか」)
"What does it mean?" asked Charlotte, who had never used any soap flakes in her life.
(「どういう意味なの?」粉せっけんなど、これまでにいちども使ワたことのないシャーロットはききました。)
"How should I know?" said Templeton. "You asked for words and I brought them. I suppose the next thing you'll want me to fetch is a dictionary."
(「おれにわかるはずないだろう。宣伝文句がほしいっていうから、持ってきてやっただけさ。このぶんじゃ、つぎは辞書を持ってきてくれっていうんじゃないのか?」)
Together they studied the soap ad. "'With new radiant action,'" repeated Charlotte, slowly. "Wilbur!" she called.
(ふたりは、粉せっけんの宣伝文句をじっくりと研究してみました。「すばやくぴかぴか……。ねえ、ウィルバー!」シャーロットがウィルバーをよびました。)
Wilbur, who was asleep in the straw, jumped up.
(わらのなかでねむっていたウィルバーは、とび起きました。)
"Run around!" commanded Charlotte. "I want to see you in action, to see if you are radiant."
(「そこらを走ってみて!」シャーロットが命令しました。「動いたら、ぴかぴかに見えるかしら?」)
Wilbur raced to the end of his yard.
(ウィルバーは、かこいのはしまで走りました。)
"Now back again, faster!" said Charlotte.
(「もどってきて、もっとはやく!」シャーロットはいいました。)
Wilbur galloped back. His skin shone. His tail had a fine, tight curl in it.
(ウィルバーは駆けもどりました。はだがつやつやして、しつぼはきゅつとまるまっています。)
"Jump into the air!" cried Charlotte.
(「とびあがってみて!」シャーロットがさけびました。)
Wilbur jumped as high as he could.
(ウィルバーは、できるだけ高くとびあがってみました。)
"Keep your knees straight and touch the ground with your ears!" called Charlotte.
(「ひざをまげないで、耳を地面につけてみて!」と、シャーロット。)
Wilbur obeyed.
(ウィルバーは、いわれたとおりにしました。)
"Do a back flip with a half twist in it!" cried Charlotte.
(「うしろ宙がえりで体を半分ひねってみて!」)
Wilbur went over backwards, writhing and twisting as he went.
(ウィルバーは、体をよじったりひねったりしながら、うしろ宙がえりをしてみせました。)
"O.K.,Wilbur," said Charlotte. "You can go back to sleep. O.K., Templeton, the soap ad will do, I guess. I'm not sure Wilbur's action is exactly radiant, but it's interesting."
(「オーケー、ウィルバー。もう寝床にもどっていいわ」と、シャーロットがいいました。「テンプルトン、粉せっけんの広告でいいみたいね。ウィルバーの動きがぴかぴかかどうかはわからないけど、なかなかおもしろかったわ」)
"Actuallu," said Wilbur, "I feel radiant."
(「ぼく、なんだかぴかぴかのかんじがしてきたよ」と、ウィルバーはいいました。)
"Do you?" said Charlotte, looking at him with affection. "Well, you're a good little pig, and radiant you shall be. I'm in this thing pretty deep now--I might as well go the limit."
(「ほんとに?」シャーロットは、いとおしそうに子ブタを見ながらいいました。「あなたは、すてきな子ブタだし、そのうちぴかぴかになるわ、きっと。どうせこの計画は進めなくちゃならないんだから、少しおおげさにいったっていいわよね」)
Tired from his romp, Wilbur lay down in the clean straw. He closed his eyes. The straw seemed scratchy--not as comfortable as the cow manure, which was always delightfully soft to lie in. So he pushed the straw to one side and stretched out in the manure. Wilbur sighed. It had been a busy day--his first day of being terrific. Dozens of people had visited his yard during the afternoon, and he had had to stand and pose, looking as terrific as he could. Now he was tired. Fern had arrived and seated herself quietly on her stool in the corner.
(はねまわってつかれたウィルバーは、きれいなわらの上に横になり、目をつぶりました。わらは、ちくちくしました。やわらかい牛のふんほど気持ちがよくありません。そこで、ウィルバーはわらをどけて、牛ふんの上にねそべりました。ウィルバーは、ため息をつきました。「すばらしい」ブタの最初の日も、いそがしい}日でした。午後には、何十人もの人間がやってきたので、できるだけすばらしいかっこうをして、立っていなければならなかったのです。そんなこんなでウィルバーはくたびれていました。いつのまにかファーンがやってきて、すみのこしかけにそっとすわっていました。)
"Tell me a story, Charlotte!" said Wilbur, as he lay waiting for sleep to come. "Tell me a story!"
(「ねえ、シャーロット、お話ししてよ。お話がききたいよ」ねる用意ができたウィルバーがたのみました。)
So Charlotte, although she, too, was tired, did what Wilbur wanted.
(そこでシャーロットは、自分もくたびれていたのですが、ウィルバーのねがいをきいてやりました。)
"Once upon a time," she began, "I had a beautiful cousin who managed to build her web across a small stream. One day a tiny fish leaped into the air and got tangled in the web. My cousin was very much surprised, of course. The fish was thrashing wildly. My cousin hardly dared tackle it. But she did. She swooped down and threw great masses of wrapping material around the fish and fought bravely to capture it."
(「むかしむかし、わたしのいとこで、とても美しいクモがいました。そのクモは、小川の上に巣をかけました。ある日、水からぴょんととびあがった小さな魚が、その巣にひっかかってしまいました。わたしのいとこは、びつくりしました。魚は、バタバタとあばれました。いとこは、その魚をなかなかおさえられませんでした。でも、なんとかしなくてはなりません。いとこは、下までおりていって網をどんどんくりだし、魚をがんじがらめにして、つかまえようとしました」)
"Did she succeed?" asked Wilbur.
(「うまくいったの?」と、ウィルバーはたずねました。)
"It was a never-to-be-forgotten battle," said Charlotte. "There was the fish, caught only by one fin, and its tail wildly thrashing and shining in the sun. There was the web, sagging dangerously under the weight of the fish.
(「わすれようとしても、わすれられない戦いになったのよ」と、シャーロットは話をつづけました。「魚はひれの一つが網にひっかかっていたのですが、うろこをきらめかせながら、しっぽをバタバタふっていました。魚の重みで、網はやぶけそうでした」)
"How much did the fish weigh?" asked Wilbur eagerly.
(「その魚はどれくらいの重さだったの?」と、ウィルバーは興味しんしんでたずねました。 )
"I don't know," said Charlotte. "There was my cousin, slipping in, dodging out, beaten mercilessly over the head by the wildly thrashing fish, dancing in, dancing out, throwing her threads and fighting hard. First she threw a left around the tail. The fish lashed back. Then a left to the tail and a right to the midsection. The fish lashed back. Then she dodged to one side and threw a right, and another right to the fin. Then a hard left to the head, while the web swayed and stretched."
(「さあ、わからないわ。わたしのいとこは、しのびよるかと思うと、さっと攻撃をかわし、あばれる魚に頭を容赦なくたたかれても、かろやかに近づいたりはなれたりしながら糸をくりだして、勇敢に戦いました。まずは魚のしっぽをめがけて、左のパンチ。魚も打ちかえします。つぎに左のパンチをしつぼにあびせたと思うと、右のパンチで胴体攻撃。魚が打ちかえす。いとこは、すばやくその攻撃をかわし、右のパンチ。そして、ひれにも、もう一発。つづいて、強烈な左のパンチを頭にくらわせたので、網がゆれて、ビヨーンとのびました」)
"Then what happened?" asked Wilbur.
(「それから、どうなったの?」と、ウィルバーはたずねました。)
"Nothing," said Charlotte. "The fish lost the fight. My cousin wrapped it up so tight it couldn't budge."
(「どうもしないわ。魚が負けたのよ。わたしのいとこが魚をぐるぐるまきにしたので、身動きがとれなくなっちゃったの」)
"Then what happened?" asked Wilbur.
(「それから、どうなったの?」)
"Nothing," said Charlotte. "My cousin kept the fish for a while, and then, when she got good and ready, she ate it."
(「どうもしないわ。いとこは、しばらく魚をそのままおいといたんだけど、そのうちちょうどいいころあいになったから、食べちゃったのよ」)
"Tell me another story!" begged Wilbur.
(「もう一つ、お話ししてよ!」ウィルバーがせがみました。)
So Charlotte told him about another cousin of hers who was an aeronaut.
(そこでシャーロットは、またべつのいとこの話をしました。こんどのいとこは、気球乗りでした。)
"What is an aeronaut?" asked Wilbur.
(「それ、どんな仕事なの?」と、ウィルバーがたずねました。)
"A balloonist," said Charlotte. "My cousin used to stand on her head and let out enough thread to form a balloon. Then she'd let go and be lifted into the air and carried upward on the warm wind."
(「気球に乗って空をとぶのよ。このいとこは、さかだちをして、いっぱい糸をくりだし、気球をつくったの。それからその気球といっしょに、あたたかい風に乗って旅をしたの」)
"Is that true?" asked Wilbur. "Or are you just making it up?"
(「それって、ほんとの話なの?それとも、つくり話なの?」ウィルバーはたずねました。
)
"It's true," replied Charlotte. "I have some very remarkable cousins. And now, Wilbur, it's time you went to sleep."
(「ほんとの話よ。わたしには、すごいいとこが何人もいるのよ。さあ、ウィルバー、もうねる時間よ」)
"Sing something!" begged Wilbur, closing his eyes.
(「だったら、なにかうたってよ」目をつぶりながら、ウィルバーはせがみました。)
So Charlotte sang a lullaby, while crickets chirped in the grass and the barn grew dark. This was the song she sang.
(そこでシャーロットは、こもり歌をうたってくれました。草のなかではコオロギが鳴き、納屋は暗くなっていました。シャーロットがうたったのは、こんな歌でした。)
"Sleep, sleep, my love, my only,
(おやすみ、おやすみ、いい子だね)
Deep, deep, in the dung and the dark;
(暗闇につつまれて、牛ふんの上で)
Be not afraid and be not lonely!
(心配しないで、さびしがらないで)
This is the hour when frogs and thrushes
(カエルやツグミは森や草地で)
Praise the world from the woods and the rushes.
(美しい世界をたたえているよ)
Rest from care, my one and only,
(ぐっすりおやすみ、やすらかに)
Deep in the dung and the dark!"
(暗闇に包まれて、牛ふんの上で )
But Wilbur was already asleep. When the song ended, Fern got up and went home.
(けれども、歌がおわらないうちに、ウィルバーは、もうぐっすりねむっていました。シャーロットの歌がおわると、ファーンは立ちあがって家に帰りました。)
英文のみです。
ⅩⅢ.Good Progress
Far into the night, while the other creatures slept, Charlotte worked on her web. First she ripped out a few of the orb lines near the center. She left the radial lines alone, as they were nedded for support. As she worked, her eight legs were a great help to her. So were her teeth. She loved to weave and she was an expert at it. When she was finished ripping things out, her web looked something like this:
A spider can produce several kinds of thread. She uses a dry, tough thread for foundation lines, and she uses a sticky thread for snare lines--the ones that catch and hold insects. Charlotte decided to use her dry thread for writing the new message.
"If I write the word 'Terrific' with sticky thread," she thought, "every bug that comes along will get stuck in it and spoil the effect."
"Now let's see, the first letter is T."
Charlotte climbed to a point at the top of the left hand side of the web. Swinging her spinnerets into position, she attached her thread and then dropped down. As she dropped, her spinning tubes went into action and she let out thread. At the bottom, she attached the thread. This formed the upright part of the letter T. Charlotte was not satisfied, however. She clombed up and made another attachment, right next to the first. Then she carried the line down, so that she had a double line instead of a single line. "It will show up better if I make the whole thing with double lines."
She climbed back up, moved over about an inch to the left, touched her spinnerets to the web, and then carried a line across to the right, forming the top of the T. She repeated this, making it double. Her eight legs were very busy helping.
"Now for the E !"
Charlotte got so interested in her work, she began to talk to herself, as though to cheer herself on. If you had been sitting quietly in the barn cellar that evening, you would have heard something like this:
"Now for the R! Up we go! Attach! Descend! Pay out line! Whoa! Attach! Good! Up you go! Repeat! Attach! Descend! Pay out line. Whoa, girl! Steady now! Attach! Now right and down and swing that loop and around and around! Now in to the left! Attach! Climb! Repeat! O.K! Easy, keep those lines together! Now, then, out and down for the leg of the R! Pay out line! Whoa! Attach! Ascend! Repeat! Good girl!"
And so, talking to herself, the spider worked at her difficult task. When it was completed, she felt hungry. She ate a small bug that she had been saving. Then she slept.
Next morning, Wilbur arose and stood beneath the web. He breathed the morning air into his lungs. Drops of dew, catching the sun, made the web stand out clearly. When Lurvy arrived with breakfast, there was the handsome pig, and over him, woven neatly in block letters, was the word TERRIFIC. Another miracle.
Lurvy rushed and called Mr. Zuckerman. Mr. Zuckerman rushed and called Mrs. Zuckerman. Mrs. Zuckerman ran to the phone and called the Arables. The Arables climbed into their truck and hurried over. Everybody stood at the pigpen and stared at the web ans read the word, over and over, while Wilbur, who really felt terrific, stood quietly swelling out his chest and swinging his snout from from side to side.
"Terrific!" breathed Zuckerman, in joyful admiration. "Edith, you better phone the reporter on the Weekly Chronicle and tell him what has happened. He will want to know about this. He may want to bring a photographer. There isn't a pig in the whole state that is as terrific as our pig."
The news spread. People who had journeyed to see Wilbur when he was "some pig" came back again to see him now that he was "terrific."
Rhat afternoon, when Mr. Zuckerman went to milk the cows and clean out the tie-ups, he was still thinking about what a wondrous pig he owned.
"Lurvy!" he called. "There is to be no more cow manure thrown down into that pigpen. I have a terrific pig. I want that pig to have clean, bright straw every day for his bedding. Understand?"
"Yes, sir," said Lurvy.
"Furthermore," said Mr. Zuckerman, "I want you to start building a crate for Wilbur. I have decided to take the pig to the Country Fair on September sixth. Make the crate large and paint it green with gold letters!"
"What will the letters say?" asked Lurvy.
"They should say Zuckerman's Famous Pig."
Lurvy picked up a pitchfork and walked away to get some clean straw. Having such an important pig was going to mean plenty of extra work, he could see that.
Below the apple orchard, at the end of a path, was the dump where Mr. Zuckerman threw all sorts of trash and stuff that nobody wanted any more. Here, in a small clearing hidden by young alders and wild raspberry bushes, was an astonishing pile of old bottles and empty tin cans and dirty rags and bits of metal and broken bottles and broken hinges and broken springs and dead batteries and last month's magazines and old discarded dishmops and tattered overalls and rusty spikes and leaky pails and forgotten stoppers and useless junk of all kinds, including a wrong-size crank for a broken ice-cream freezer.
Templeton knew the dump and liked it. There were good hiding places there--excellent cover for a rat. And there was usually a tin can with food still clinging to the inside.
Templeton was down there now, rummanging around. When he returned to the barn, he carried in his mouth an advertisement he had torn from a crumpled magazine.
"How's this?" he asked, showing the ad to Charlotte. "It says 'Crunchy.' 'Crunchy' would be a good word to write in your web."
"Just the wrong idea," replied Charlotte. "Couldn't be worse. We don't want Zuckerman to think Wilbur is crunchy. He might start thinking about crisp, crunchy bacon and tasty ham. That would put ideas into his head. We must advertise Wilbur's noble qualities, not his tastiness. Go get another word, please, Templeton!"
The rat looked disgusted. But he sneaked away to the dump and was back in a while with a strip of cotton cloth. "How's this?" he asked. "It's a label off an old shirt."
Charlotte examined the label. It said PRE-SHRUNK.
I'm sorry,Templeton," she said, "but 'Pre-shrunk' is out of the question. We want Zuckerman to think Wilbur is nicely filled out, not all shrunk up. I'll have to ask you to try again."
"What do you think I am, a messager boy?" grumbled the rat. "I'm not going to spend all my time chasing down to the dump after advertising material."
"Just once more--please!" said Charlotte.
"I'll tell you what I'll do," said Templeton. "I know where there's a package of soap flakes in the woodshed. It has writing on it. I'll bring you a piece of the package."
He climbed the rope that hung on the wall and disappeared through a hole in the celing. When he came back he had a strip of blue-and-white cardboard in his teeth.
"There!" he said, triumphantly. "How's that?"
Charlotte read the words: "With New Radiant Action."
"What does it mean?" asked Charlotte, who had never used any soap flakes in her life.
"How should I know?" said Templeton. "You asked for words and I brought them. I suppose the next thing you'll want me to fetch is a dictionary."
Together they studied the soap ad. "'With new radiant action,'" repeated Charlotte, slowly. "Wilbur!" she called.
Wilbur, who was asleep in the straw, jumped up.
"Run around!" commanded Charlotte. "I want to see you in action, to see if you are radiant."
Wilbur raced to the end of his yard.
"Now back again, faster!" said Charlotte.
Wilbur galloped back. His skin shone. His tail had a fine, tight curl in it.
"Jump into the air!" cried Charlotte.
Wilbur jumped as high as he could.
"Keep your knees straight and touch the ground with your ears!" called Charlotte.
Wilbur obeyed.
"Do a back flip with a half twist in it!" cried Charlotte.
Wilbur went over backwards, writhing and twisting as he went.
"O.K.,Wilbur," said Charlotte. "You can go back to sleep. O.K., Templeton, the soap ad will do, I guess. I'm not sure Wilbur's action is exactly radiant, but it's interesting."
"Actuallu," said Wilbur, "I feel radiant."
"Do you?" said Charlotte, looking at him with affection. "Well, you're a good little pig, and radiant you shall be. I'm in this thing pretty deep now--I might as well go the limit."
Tired from his romp, Wilbur lay down in the clean straw. He closed his eyes. The straw seemed scratchy--not as comfortable as the cow manure, which was always delightfully soft to lie in. So he pushed the straw to one side and stretched out in the manure. Wilbur sighed. It had been a busy day--his first day of being terrific. Dozens of people had visited his yard during the afternoon, and he had had to stand and pose, looking as terrific as he could. Now he was tired. Fern had arrived and seated herself quietly on her stool in the corner.
"Tell me a story, Charlotte!" said Wilbur, as he lay waiting for sleep to come. "Tell me a story!"
So Charlotte, although she, too, was tired, did what Wilbur wanted.
"Once upon a time," she began, "I had a beautiful cousin who managed to build her web across a small stream. One day a tiny fish leaped into the air and got tangled in the web. My cousin was very much surprised, of course. The fish was thrashing wildly. My cousin hardly dared tackle it. But she did. She swooped down and threw great masses of wrapping material around the fish and fought bravely to capture it."
"Did she succeed?" asked Wilbur.
"It was a never-to-be-forgotten battle," said Charlotte. "There was the fish, caught only by one fin, and its tail wildly thrashing and shining in the sun. There was the web, sagging dangerously under the weight of the fish.
"How much did the fish weigh?" asked Wilbur eagerly.
"I don't know," said Charlotte. "There was my cousin, slipping in, dodging out, beaten mercilessly over the head by the wildly thrashing fish, dancing in, dancing out, throwing her threads and fighting hard. First she threw a left around the tail. The fish lashed back. Then a left to the tail and a right to the midsection. The fish lashed back. Then she dodged to one side and threw a right, and another right to the fin. Then a hard left to the head, while the web swayed and stretched."
"Then what happened?" asked Wilbur.
"Nothing," said Charlotte. "The fish lost the fight. My cousin wrapped it up so tight it couldn't budge."
"Then what happened?" asked Wilbur.
"Nothing," said Charlotte. "My cousin kept the fish for a while, and then, when she got good and ready, she ate it."
"Tell me another story!" begged Wilbur.
So Charlotte told him about another cousin of hers who was an aeronaut.
"What is an aeronaut?" asked Wilbur.
"A balloonist," said Charlotte. "My cousin used to stand on her head and let out enough thread to form a balloon. Then she'd let go and be lifted into the air and carried upward on the warm wind."
"Is that true?" asked Wilbur. "Or are you just making it up?"
"It's true," replied Charlotte. "I have some very remarkable cousins. And now, Wilbur, it's time you went to sleep."
"Sing something!" begged Wilbur, closing his eyes.
So Charlotte sang a lullaby, while crickets chirped in the grass and the barn grew dark. This was the song she sang.
"Sleep, sleep, my love, my only,
Deep, deep, in the dung and the dark;
Be not afraid and be not lonely!
This is the hour when frogs and thrushes
Praise the world from the woods and the rushes.
Rest from care, my one and only,
Deep in the dung and the dark!"
But Wilbur was already asleep. When the song ended, Fern got up and went home.
Far into the night, while the other creatures slept, Charlotte worked on her web. First she ripped out a few of the orb lines near the center. She left the radial lines alone, as they were nedded for support. As she worked, her eight legs were a great help to her. So were her teeth. She loved to weave and she was an expert at it. When she was finished ripping things out, her web looked something like this:
A spider can produce several kinds of thread. She uses a dry, tough thread for foundation lines, and she uses a sticky thread for snare lines--the ones that catch and hold insects. Charlotte decided to use her dry thread for writing the new message.
"If I write the word 'Terrific' with sticky thread," she thought, "every bug that comes along will get stuck in it and spoil the effect."
"Now let's see, the first letter is T."
Charlotte climbed to a point at the top of the left hand side of the web. Swinging her spinnerets into position, she attached her thread and then dropped down. As she dropped, her spinning tubes went into action and she let out thread. At the bottom, she attached the thread. This formed the upright part of the letter T. Charlotte was not satisfied, however. She clombed up and made another attachment, right next to the first. Then she carried the line down, so that she had a double line instead of a single line. "It will show up better if I make the whole thing with double lines."
She climbed back up, moved over about an inch to the left, touched her spinnerets to the web, and then carried a line across to the right, forming the top of the T. She repeated this, making it double. Her eight legs were very busy helping.
"Now for the E !"
Charlotte got so interested in her work, she began to talk to herself, as though to cheer herself on. If you had been sitting quietly in the barn cellar that evening, you would have heard something like this:
"Now for the R! Up we go! Attach! Descend! Pay out line! Whoa! Attach! Good! Up you go! Repeat! Attach! Descend! Pay out line. Whoa, girl! Steady now! Attach! Now right and down and swing that loop and around and around! Now in to the left! Attach! Climb! Repeat! O.K! Easy, keep those lines together! Now, then, out and down for the leg of the R! Pay out line! Whoa! Attach! Ascend! Repeat! Good girl!"
And so, talking to herself, the spider worked at her difficult task. When it was completed, she felt hungry. She ate a small bug that she had been saving. Then she slept.
Next morning, Wilbur arose and stood beneath the web. He breathed the morning air into his lungs. Drops of dew, catching the sun, made the web stand out clearly. When Lurvy arrived with breakfast, there was the handsome pig, and over him, woven neatly in block letters, was the word TERRIFIC. Another miracle.
Lurvy rushed and called Mr. Zuckerman. Mr. Zuckerman rushed and called Mrs. Zuckerman. Mrs. Zuckerman ran to the phone and called the Arables. The Arables climbed into their truck and hurried over. Everybody stood at the pigpen and stared at the web ans read the word, over and over, while Wilbur, who really felt terrific, stood quietly swelling out his chest and swinging his snout from from side to side.
"Terrific!" breathed Zuckerman, in joyful admiration. "Edith, you better phone the reporter on the Weekly Chronicle and tell him what has happened. He will want to know about this. He may want to bring a photographer. There isn't a pig in the whole state that is as terrific as our pig."
The news spread. People who had journeyed to see Wilbur when he was "some pig" came back again to see him now that he was "terrific."
Rhat afternoon, when Mr. Zuckerman went to milk the cows and clean out the tie-ups, he was still thinking about what a wondrous pig he owned.
"Lurvy!" he called. "There is to be no more cow manure thrown down into that pigpen. I have a terrific pig. I want that pig to have clean, bright straw every day for his bedding. Understand?"
"Yes, sir," said Lurvy.
"Furthermore," said Mr. Zuckerman, "I want you to start building a crate for Wilbur. I have decided to take the pig to the Country Fair on September sixth. Make the crate large and paint it green with gold letters!"
"What will the letters say?" asked Lurvy.
"They should say Zuckerman's Famous Pig."
Lurvy picked up a pitchfork and walked away to get some clean straw. Having such an important pig was going to mean plenty of extra work, he could see that.
Below the apple orchard, at the end of a path, was the dump where Mr. Zuckerman threw all sorts of trash and stuff that nobody wanted any more. Here, in a small clearing hidden by young alders and wild raspberry bushes, was an astonishing pile of old bottles and empty tin cans and dirty rags and bits of metal and broken bottles and broken hinges and broken springs and dead batteries and last month's magazines and old discarded dishmops and tattered overalls and rusty spikes and leaky pails and forgotten stoppers and useless junk of all kinds, including a wrong-size crank for a broken ice-cream freezer.
Templeton knew the dump and liked it. There were good hiding places there--excellent cover for a rat. And there was usually a tin can with food still clinging to the inside.
Templeton was down there now, rummanging around. When he returned to the barn, he carried in his mouth an advertisement he had torn from a crumpled magazine.
"How's this?" he asked, showing the ad to Charlotte. "It says 'Crunchy.' 'Crunchy' would be a good word to write in your web."
"Just the wrong idea," replied Charlotte. "Couldn't be worse. We don't want Zuckerman to think Wilbur is crunchy. He might start thinking about crisp, crunchy bacon and tasty ham. That would put ideas into his head. We must advertise Wilbur's noble qualities, not his tastiness. Go get another word, please, Templeton!"
The rat looked disgusted. But he sneaked away to the dump and was back in a while with a strip of cotton cloth. "How's this?" he asked. "It's a label off an old shirt."
Charlotte examined the label. It said PRE-SHRUNK.
I'm sorry,Templeton," she said, "but 'Pre-shrunk' is out of the question. We want Zuckerman to think Wilbur is nicely filled out, not all shrunk up. I'll have to ask you to try again."
"What do you think I am, a messager boy?" grumbled the rat. "I'm not going to spend all my time chasing down to the dump after advertising material."
"Just once more--please!" said Charlotte.
"I'll tell you what I'll do," said Templeton. "I know where there's a package of soap flakes in the woodshed. It has writing on it. I'll bring you a piece of the package."
He climbed the rope that hung on the wall and disappeared through a hole in the celing. When he came back he had a strip of blue-and-white cardboard in his teeth.
"There!" he said, triumphantly. "How's that?"
Charlotte read the words: "With New Radiant Action."
"What does it mean?" asked Charlotte, who had never used any soap flakes in her life.
"How should I know?" said Templeton. "You asked for words and I brought them. I suppose the next thing you'll want me to fetch is a dictionary."
Together they studied the soap ad. "'With new radiant action,'" repeated Charlotte, slowly. "Wilbur!" she called.
Wilbur, who was asleep in the straw, jumped up.
"Run around!" commanded Charlotte. "I want to see you in action, to see if you are radiant."
Wilbur raced to the end of his yard.
"Now back again, faster!" said Charlotte.
Wilbur galloped back. His skin shone. His tail had a fine, tight curl in it.
"Jump into the air!" cried Charlotte.
Wilbur jumped as high as he could.
"Keep your knees straight and touch the ground with your ears!" called Charlotte.
Wilbur obeyed.
"Do a back flip with a half twist in it!" cried Charlotte.
Wilbur went over backwards, writhing and twisting as he went.
"O.K.,Wilbur," said Charlotte. "You can go back to sleep. O.K., Templeton, the soap ad will do, I guess. I'm not sure Wilbur's action is exactly radiant, but it's interesting."
"Actuallu," said Wilbur, "I feel radiant."
"Do you?" said Charlotte, looking at him with affection. "Well, you're a good little pig, and radiant you shall be. I'm in this thing pretty deep now--I might as well go the limit."
Tired from his romp, Wilbur lay down in the clean straw. He closed his eyes. The straw seemed scratchy--not as comfortable as the cow manure, which was always delightfully soft to lie in. So he pushed the straw to one side and stretched out in the manure. Wilbur sighed. It had been a busy day--his first day of being terrific. Dozens of people had visited his yard during the afternoon, and he had had to stand and pose, looking as terrific as he could. Now he was tired. Fern had arrived and seated herself quietly on her stool in the corner.
"Tell me a story, Charlotte!" said Wilbur, as he lay waiting for sleep to come. "Tell me a story!"
So Charlotte, although she, too, was tired, did what Wilbur wanted.
"Once upon a time," she began, "I had a beautiful cousin who managed to build her web across a small stream. One day a tiny fish leaped into the air and got tangled in the web. My cousin was very much surprised, of course. The fish was thrashing wildly. My cousin hardly dared tackle it. But she did. She swooped down and threw great masses of wrapping material around the fish and fought bravely to capture it."
"Did she succeed?" asked Wilbur.
"It was a never-to-be-forgotten battle," said Charlotte. "There was the fish, caught only by one fin, and its tail wildly thrashing and shining in the sun. There was the web, sagging dangerously under the weight of the fish.
"How much did the fish weigh?" asked Wilbur eagerly.
"I don't know," said Charlotte. "There was my cousin, slipping in, dodging out, beaten mercilessly over the head by the wildly thrashing fish, dancing in, dancing out, throwing her threads and fighting hard. First she threw a left around the tail. The fish lashed back. Then a left to the tail and a right to the midsection. The fish lashed back. Then she dodged to one side and threw a right, and another right to the fin. Then a hard left to the head, while the web swayed and stretched."
"Then what happened?" asked Wilbur.
"Nothing," said Charlotte. "The fish lost the fight. My cousin wrapped it up so tight it couldn't budge."
"Then what happened?" asked Wilbur.
"Nothing," said Charlotte. "My cousin kept the fish for a while, and then, when she got good and ready, she ate it."
"Tell me another story!" begged Wilbur.
So Charlotte told him about another cousin of hers who was an aeronaut.
"What is an aeronaut?" asked Wilbur.
"A balloonist," said Charlotte. "My cousin used to stand on her head and let out enough thread to form a balloon. Then she'd let go and be lifted into the air and carried upward on the warm wind."
"Is that true?" asked Wilbur. "Or are you just making it up?"
"It's true," replied Charlotte. "I have some very remarkable cousins. And now, Wilbur, it's time you went to sleep."
"Sing something!" begged Wilbur, closing his eyes.
So Charlotte sang a lullaby, while crickets chirped in the grass and the barn grew dark. This was the song she sang.
"Sleep, sleep, my love, my only,
Deep, deep, in the dung and the dark;
Be not afraid and be not lonely!
This is the hour when frogs and thrushes
Praise the world from the woods and the rushes.
Rest from care, my one and only,
Deep in the dung and the dark!"
But Wilbur was already asleep. When the song ended, Fern got up and went home.
日本語訳のみです。
13.進歩
夜、ほかの動物たちがねしずまってからも、シャーロットはずっと文字を織りこむ仕事に精をだしていました。最初にまず、網のまんなかにあるぐるっと円をかくように張った糸を何本もとりのぞきました。放射状の糸は、全体をささえるのに必要なので、のこしておきます。シャーロットの八本の足は、とても役に立ちました。歯も大活躍です。シャーロットは網をつくるのが大すきだし、とてもじょうずでした。まんなかの部分をとりのぞくと、シャーロットの巣は左の絵のようになりました。
クモは、何種類かの糸をくりだすことができます。シャーロットは、ねばつかないじょうぶな糸で土台をつくり、虫をつかまえるわなの部分には、ねばねばした糸を使いました。新しいことばを織りこむのには、ねばつかない糸を使うことに決めました。
「もし、ねばねばの糸で『すばらしい』って書くとすると、とびこんできた虫がひっかかったら、だいなしになっちゃうもの」と、思ったのです。
「さてと、最初はTの字ね」
シャーロットは網の左側のてっぺんまでのぼりました。紡績突起をゆらして糸を固定すると、下にさがります。さがると同時に紡績管が働いて、糸がでてきました。下までたどりつくと、また糸を固定します。これで、Tの字のたての線ができました。でも、シャーロットはまだ満足しませんでした。もういちど上までのぼり、さつきのすぐとなりに糸を固定し、またすーっと下におります。これで、たての線が二重になりました。
「二重線で書いておけば、はっきりめだつわ」
シャーロットはまた上までいき、さっきのところから二・五センチばかり左に糸を固定し、こんどは右に動きました。Tの字の横線ができました。同じ動きをくりかえして二重にします。八本の足がいそがしく動きまわります。
「つぎはEの字よ」
シャーロットはこの仕事に夢中になり、自分を元気づけるみたいに、ひとりごとをいいはじめました。その夜、納屋の地下にしずかにすわっていれば、こんな声がきこえたはずです。
「さあ、こんどはR!上へいって、糸をくっつけて、さがって、糸をくりだして、とまって糸をくっつけて。できたわ!上へいって、くりかえすのよ。糸をくっつけて、さがって糸をくりだして、とまって、おちついて糸をくつける。もういちど上へいって、こんどは右へ糸をくりだして、とまってくっつける。こんどは右ね。糸をくりだして、くっつける。それから右下へおりて、くるっとまわる。さあ、こんどは左よ。くっつけて、ヒへいって、くりかえして、いいわ!さてと、この二本をたばねて、つぎはRの字の足ね。糸をくりだして、とまって、くっつけて、上へいって、くりかえし。うまくいったわ!」
シャーロットは、こんなふうにひとりごとをいいながら、むずかしい仕事を進めていきました。ようやく文字を書きおわったときには、おなかがぺこぺこになっていました。そこで、とっておいた虫を食べて、ねむりました。
つぎの朝、起きあがったウィルバーは、クモの巣の下に立ちました。朝の空気を胸いっぱいに吸いこみます。朝露が口の光をうけて、クモの巣ははっきり見えていました。ラーヴィーが朝ごはんをもってやってきたとき、納屋にはころころしたブタがいて、その頭上には、きれいな活字体の文字で『すばらしい』と書いてありました。また奇跡が起こったのです。
ラーヴィーは、いそいでザッカーマンのおじさんに知らせました。おじさんは、いそいでおばさんをよびにいきました。おばさんは、いそいでエラブルさんに電話をしました。
エラブル一家がトラックに乗って、いそいでやってきました。みんなブタ小屋のまえに立ち、クモの巣をながめ、何度も何度も文字を読みました。そのあいだ、すばらしく気分がよかったウィルバーはしずかに立って胸をつきだし、鼻先を右へ左へとゆらしていました。
「『すばらしい』だと!」ザッカーマンのおじさんが、感心した声でいいました。「イーディス、週刊新聞の記者に電話をして、なにが起こったか、話してやるといい。記事にしたがるぞ。もしかしたら、カメラマンもつれてくるかもしれん。なにしろ、うちのブタほどすばらしいのは、州のどこをさがしたっていないんだからな」
ニュースはすぐに知れわたりました。ウィルバーが「たいしたブタ」だったときに見にきた人たちが、こんどは「すばらしい」ブタを見るために、またやってきました。
その午後、乳しぼりとそうじのために牛小屋にでかけたザッカーマンのおじさんは、自分がすばらしいブタを持っている幸運について考えつづけていました。
「ラーヴイー!牛のふんは、もうブタのかこいに入れなくていいからな。うちのは、すばらしいブタなんだ。寝床には、きれいなわらを毎日入れてやってくれ。わかったかい?」ザッカーマンさんがいいました。
「わかりました」ラーヴィーがこたえました。
「それから」と、ザッカーマンさんはつづけました。「ウィルバーを入れる木箱をつくってくれ。あのブタを、九月六日の品評会にだすことにしたからな。大きな木箱をつくって緑色にぬり、金色の文字を入れるんだ」
「文字はなんと?」ラーヴィーがたずねました。
「『ザッカーマンの有名なブタ』と書いてくれ」
ラーヴイーは、くまでをかついで、きれいなわらをとりにいきました。りっぱなブタがいると、いろいろと用事がふえるものです。
リンゴ畑のむこうの、小道のつきあたりにはゴミ捨て場があって、ザッカーマンさんは、もうだれも使わなくなったゴミをそこに捨てていました。ハンノキの若木と野生のキイチゴのかげになったそのゴミ捨て場には、古いびん、あき缶、ぼろきれ、金属の破片、割れたびん、こわれたちょうつがい、こわれたばね、きれた乾電池、古雑誌、用ずみになった鵬灘いのモップ、すりきれた作業ズボン、さびたくぎ、水がもるバケツ、使えなくなったおふろの襟といった、あらゆる働郷の役に立たないガラクタがつみかさなっていました。なかには、こわれたアイスクリーム製造器についていたサイズちがいのハンドルなんていうものもありました。
このゴミ捨て場は、テンプルトンがなわばりにしているお気に入りの場所でした。かくれる場所もたくさんあって、ネズミにとっては、とても都合がよかったんどえす。それに、空き缶の内側には、たいていまだ食べ物がくっついていました。
テンプルトンはゴミ捨て場にいって、あちこちかきまわしました。そして納屋に戻ってきたときには、しわくちゃの雑誌から切りとった広告を口にくわえていました。
「これは、どうだい?」テンプルトンはそういいながら、広告をシャーロットに見せました。
「『ぱりっとした』って書いてあるんだ。これを網のなかに書いたらいいよ」
「あらだめよ。それはまずいわ。ウィルバーの肉が、焼いたらパリッとおいしいかもしれないなんて、ザッカーマンさんが思ったらこまるでしょ。パリパリに焼いたベーコンやソーセージを連想しちゃうかもしれないもの。そんな文字にしたらヒントをあげるようなものだわ。わたしたちは、ウィルバーがおいしいかどうかじゃなくて、ウィルバーカすばらしいブタだってことを宣伝しなくちゃいけないのよ。ほかのことばをさがしてきてちょうだい。おねがいよ、テンプルトン」シャーロットがいいました。
ネズミは、うんざりした顔をしました。けれども、またでていって、こんどはもめんの布きれを持ってきました。
「これは、どうだい?古いシャツのラベルなんだ」
シャーロットは、ラベルを見てみました。防縮加工と書いてあります。
「わるいけど、『防縮加工』は使えないわ。ウィルバーは縮むんじゃなくて、はちきれんばかりに大きくなってるって、ザッカーマンさんに思わせなくちゃ。もういちど、いってきてちょうだいな」
「おれのこと、つかいっぱしりのこぞうかなんかだと思ってるな」と、ネズミは文句をいいました。「一日中広告をさがして、ゴミ捨て場をうろつくわけにはいかないんだぞ」
「おねがいよ、もう一度だけいってきて、ね」と、シャーロットはたのみました。
「じゃあ、こうしよう」と、テンプルトンがいいました。「薪小屋に粉せっけんの箱がある。その箱に字が書いてあったから、それを持ってきてやるよ」
テンプルトンは、壁ぎわにさがったロープをよじのぼると、天井の穴にすがたを消しました。もどってきたときには、青と白のボール紙の破片をくわえていました。
「そら!どうだい?」テンプルトンは、勝ちほこったようにいいました。
シャーロットは、書いてある文字を読みました。「すばやくぴかぴか」
「どういう意味なの?」粉せっけんなど、これまでにいちども使ワたことのないシャーロットはききました。
「おれにわかるはずないだろう。宣伝文句がほしいっていうから、持ってきてやっただけさ。このぶんじゃ、つぎは辞書を持ってきてくれっていうんじゃないのか?」
ふたりは、粉せっけんの宣伝文句をじっくりと研究してみました。「すばやくぴかぴか……。ねえ、ウィルバー!」シャーロットがウィルバーをよびました。
わらのなかでねむっていたウィルバーは、とび起きました。
「そこらを走ってみて!」シャーロットが命令しました。「動いたら、ぴかぴかに見えるかしら?」
ウィルバーは、かこいのはしまで走りました。
「もどってきて、もっとはやく!」シャーロットはいいました。
ウィルバーは駆けもどりました。はだがつやつやして、しつぼはきゅつとまるまっています。
「とびあがってみて!」シャーロットがさけびました。
ウィルバーは、できるだけ高くとびあがってみました。
「ひざをまげないで、耳を地面につけてみて!」と、シャーロット。
ウィルバーは、いわれたとおりにしました。
「うしろ宙がえりで体を半分ひねってみて!」
ウィルバーは、体をよじったりひねったりしながら、うしろ宙がえりをしてみせました。
「オーケー、ウィルバー。もう寝床にもどっていいわ」と、シャーロットがいいました。「テンプルトン、粉せっけんの広告でいいみたいね。ウィルバーの動きがぴかぴかかどうかはわからないけど、なかなかおもしろかったわ」
「ぼく、なんだかぴかぴかのかんじがしてきたよ」と、ウィルバーはいいました。
「ほんとに?」シャーロットは、いとおしそうに子ブタを見ながらいいました。「あなたは、すてきな子ブタだし、そのうちぴかぴかになるわ、きっと。どうせこの計画は進めなくちゃならないんだから、少しおおげさにいったっていいわよね」
はねまわってつかれたウィルバーは、きれいなわらの上に横になり、目をつぶりました。わらは、ちくちくしました。やわらかい牛のふんほど気持ちがよくありません。そこで、ウィルバーはわらをどけて、牛ふんの上にねそべりました。ウィルバーは、ため息をつきました。「すばらしい」ブタの最初の日も、いそがしい}日でした。午後には、何十人もの人間がやってきたので、できるだけすばらしいかっこうをして、立っていなければならなかったのです。そんなこんなでウィルバーはくたびれていました。いつのまにかファーンがやってきて、すみのこしかけにそっとすわっていました。
「ねえ、シャーロット、お話ししてよ。お話がききたいよ」ねる用意ができたウィルバーがたのみました。
そこでシャーロットは、自分もくたびれていたのですが、ウィルバーのねがいをきいてやりました。
「むかしむかし、わたしのいとこで、とても美しいクモがいました。そのクモは、小川の上に巣をかけました。ある日、水からぴょんととびあがった小さな魚が、その巣にひっかかってしまいました。わたしのいとこは、びつくりしました。魚は、バタバタとあばれました。いとこは、その魚をなかなかおさえられませんでした。でも、なんとかしなくてはなりません。いとこは、下までおりていって網をどんどんくりだし、魚をがんじがらめにして、つかまえようとしました」
「うまくいったの?」と、ウィルバーはたずねました。
「わすれようとしても、わすれられない戦いになったのよ」と、シャーロットは話をつづけました。「魚はひれの一つが網にひっかかっていたのですが、うろこをきらめかせながら、しっぽをバタバタふっていました。魚の重みで、網はやぶけそうでした」
「その魚はどれくらいの重さだったの?」と、ウィルバーは興味しんしんでたずねました。
「さあ、わからないわ。わたしのいとこは、しのびよるかと思うと、さっと攻撃をかわし、あばれる魚に頭を容赦なくたたかれても、かろやかに近づいたりはなれたりしながら糸をくりだして、勇敢に戦いました。まずは魚のしっぽをめがけて、左のパンチ。魚も打ちかえします。つぎに左のパンチをしつぼにあびせたと思うと、右のパンチで胴体攻撃。魚が打ちかえす。いとこは、すばやくその攻撃をかわし、右のパンチ。そして、ひれにも、もう一発。つづいて、強烈な左のパンチを頭にくらわせたので、網がゆれて、ビヨーンとのびました」
「それから、どうなったの?」と、ウィルバーはたずねました。
「どうもしないわ。魚が負けたのよ。わたしのいとこが魚をぐるぐるまきにしたので、身動きがとれなくなっちゃったの」
「それから、どうなったの?」
「どうもしないわ。いとこは、しばらく魚をそのままおいといたんだけど、そのうちちょうどいいころあいになったから、食べちゃったのよ」
「もう一つ、お話ししてよ!」ウィルバーがせがみました。
そこでシャーロットは、またべつのいとこの話をしました。こんどのいとこは、気球乗りでした。
「それ、どんな仕事なの?」と、ウィルバーがたずねました。
「気球に乗って空をとぶのよ。このいとこは、さかだちをして、いっぱい糸をくりだし、気球をつくったの。それからその気球といっしょに、あたたかい風に乗って旅をしたの」
「それって、ほんとの話なの?それとも、つくり話なの?」ウィルバーはたずねました。
「ほんとの話よ。わたしには、すごいいとこが何人もいるのよ。さあ、ウィルバー、もうねる時間よ」
「だったら、なにかうたってよ」目をつぶりながら、ウィルバーはせがみました。
そこでシャーロットは、こもり歌をうたってくれました。草のなかではコオロギが鳴き、納屋は暗くなっていました。シャーロットがうたったのは、こんな歌でした。
おやすみ、おやすみ、いい子だね
暗闇につつまれて、牛ふんの上で
心配しないで、さびしがらないで
カエルやツグミは森や草地で
美しい世界をたたえているよ
ぐっすりおやすみ、やすらかに
暗闇に包まれて、牛ふんの上で
けれども、歌がおわらないうちに、ウィルバーは、もうぐっすりねむっていました。シャーロットの歌がおわると、ファーンは立ちあがって家に帰りました。
夜、ほかの動物たちがねしずまってからも、シャーロットはずっと文字を織りこむ仕事に精をだしていました。最初にまず、網のまんなかにあるぐるっと円をかくように張った糸を何本もとりのぞきました。放射状の糸は、全体をささえるのに必要なので、のこしておきます。シャーロットの八本の足は、とても役に立ちました。歯も大活躍です。シャーロットは網をつくるのが大すきだし、とてもじょうずでした。まんなかの部分をとりのぞくと、シャーロットの巣は左の絵のようになりました。
クモは、何種類かの糸をくりだすことができます。シャーロットは、ねばつかないじょうぶな糸で土台をつくり、虫をつかまえるわなの部分には、ねばねばした糸を使いました。新しいことばを織りこむのには、ねばつかない糸を使うことに決めました。
「もし、ねばねばの糸で『すばらしい』って書くとすると、とびこんできた虫がひっかかったら、だいなしになっちゃうもの」と、思ったのです。
「さてと、最初はTの字ね」
シャーロットは網の左側のてっぺんまでのぼりました。紡績突起をゆらして糸を固定すると、下にさがります。さがると同時に紡績管が働いて、糸がでてきました。下までたどりつくと、また糸を固定します。これで、Tの字のたての線ができました。でも、シャーロットはまだ満足しませんでした。もういちど上までのぼり、さつきのすぐとなりに糸を固定し、またすーっと下におります。これで、たての線が二重になりました。
「二重線で書いておけば、はっきりめだつわ」
シャーロットはまた上までいき、さっきのところから二・五センチばかり左に糸を固定し、こんどは右に動きました。Tの字の横線ができました。同じ動きをくりかえして二重にします。八本の足がいそがしく動きまわります。
「つぎはEの字よ」
シャーロットはこの仕事に夢中になり、自分を元気づけるみたいに、ひとりごとをいいはじめました。その夜、納屋の地下にしずかにすわっていれば、こんな声がきこえたはずです。
「さあ、こんどはR!上へいって、糸をくっつけて、さがって、糸をくりだして、とまって糸をくっつけて。できたわ!上へいって、くりかえすのよ。糸をくっつけて、さがって糸をくりだして、とまって、おちついて糸をくつける。もういちど上へいって、こんどは右へ糸をくりだして、とまってくっつける。こんどは右ね。糸をくりだして、くっつける。それから右下へおりて、くるっとまわる。さあ、こんどは左よ。くっつけて、ヒへいって、くりかえして、いいわ!さてと、この二本をたばねて、つぎはRの字の足ね。糸をくりだして、とまって、くっつけて、上へいって、くりかえし。うまくいったわ!」
シャーロットは、こんなふうにひとりごとをいいながら、むずかしい仕事を進めていきました。ようやく文字を書きおわったときには、おなかがぺこぺこになっていました。そこで、とっておいた虫を食べて、ねむりました。
つぎの朝、起きあがったウィルバーは、クモの巣の下に立ちました。朝の空気を胸いっぱいに吸いこみます。朝露が口の光をうけて、クモの巣ははっきり見えていました。ラーヴィーが朝ごはんをもってやってきたとき、納屋にはころころしたブタがいて、その頭上には、きれいな活字体の文字で『すばらしい』と書いてありました。また奇跡が起こったのです。
ラーヴィーは、いそいでザッカーマンのおじさんに知らせました。おじさんは、いそいでおばさんをよびにいきました。おばさんは、いそいでエラブルさんに電話をしました。
エラブル一家がトラックに乗って、いそいでやってきました。みんなブタ小屋のまえに立ち、クモの巣をながめ、何度も何度も文字を読みました。そのあいだ、すばらしく気分がよかったウィルバーはしずかに立って胸をつきだし、鼻先を右へ左へとゆらしていました。
「『すばらしい』だと!」ザッカーマンのおじさんが、感心した声でいいました。「イーディス、週刊新聞の記者に電話をして、なにが起こったか、話してやるといい。記事にしたがるぞ。もしかしたら、カメラマンもつれてくるかもしれん。なにしろ、うちのブタほどすばらしいのは、州のどこをさがしたっていないんだからな」
ニュースはすぐに知れわたりました。ウィルバーが「たいしたブタ」だったときに見にきた人たちが、こんどは「すばらしい」ブタを見るために、またやってきました。
その午後、乳しぼりとそうじのために牛小屋にでかけたザッカーマンのおじさんは、自分がすばらしいブタを持っている幸運について考えつづけていました。
「ラーヴイー!牛のふんは、もうブタのかこいに入れなくていいからな。うちのは、すばらしいブタなんだ。寝床には、きれいなわらを毎日入れてやってくれ。わかったかい?」ザッカーマンさんがいいました。
「わかりました」ラーヴィーがこたえました。
「それから」と、ザッカーマンさんはつづけました。「ウィルバーを入れる木箱をつくってくれ。あのブタを、九月六日の品評会にだすことにしたからな。大きな木箱をつくって緑色にぬり、金色の文字を入れるんだ」
「文字はなんと?」ラーヴィーがたずねました。
「『ザッカーマンの有名なブタ』と書いてくれ」
ラーヴイーは、くまでをかついで、きれいなわらをとりにいきました。りっぱなブタがいると、いろいろと用事がふえるものです。
リンゴ畑のむこうの、小道のつきあたりにはゴミ捨て場があって、ザッカーマンさんは、もうだれも使わなくなったゴミをそこに捨てていました。ハンノキの若木と野生のキイチゴのかげになったそのゴミ捨て場には、古いびん、あき缶、ぼろきれ、金属の破片、割れたびん、こわれたちょうつがい、こわれたばね、きれた乾電池、古雑誌、用ずみになった鵬灘いのモップ、すりきれた作業ズボン、さびたくぎ、水がもるバケツ、使えなくなったおふろの襟といった、あらゆる働郷の役に立たないガラクタがつみかさなっていました。なかには、こわれたアイスクリーム製造器についていたサイズちがいのハンドルなんていうものもありました。
このゴミ捨て場は、テンプルトンがなわばりにしているお気に入りの場所でした。かくれる場所もたくさんあって、ネズミにとっては、とても都合がよかったんどえす。それに、空き缶の内側には、たいていまだ食べ物がくっついていました。
テンプルトンはゴミ捨て場にいって、あちこちかきまわしました。そして納屋に戻ってきたときには、しわくちゃの雑誌から切りとった広告を口にくわえていました。
「これは、どうだい?」テンプルトンはそういいながら、広告をシャーロットに見せました。
「『ぱりっとした』って書いてあるんだ。これを網のなかに書いたらいいよ」
「あらだめよ。それはまずいわ。ウィルバーの肉が、焼いたらパリッとおいしいかもしれないなんて、ザッカーマンさんが思ったらこまるでしょ。パリパリに焼いたベーコンやソーセージを連想しちゃうかもしれないもの。そんな文字にしたらヒントをあげるようなものだわ。わたしたちは、ウィルバーがおいしいかどうかじゃなくて、ウィルバーカすばらしいブタだってことを宣伝しなくちゃいけないのよ。ほかのことばをさがしてきてちょうだい。おねがいよ、テンプルトン」シャーロットがいいました。
ネズミは、うんざりした顔をしました。けれども、またでていって、こんどはもめんの布きれを持ってきました。
「これは、どうだい?古いシャツのラベルなんだ」
シャーロットは、ラベルを見てみました。防縮加工と書いてあります。
「わるいけど、『防縮加工』は使えないわ。ウィルバーは縮むんじゃなくて、はちきれんばかりに大きくなってるって、ザッカーマンさんに思わせなくちゃ。もういちど、いってきてちょうだいな」
「おれのこと、つかいっぱしりのこぞうかなんかだと思ってるな」と、ネズミは文句をいいました。「一日中広告をさがして、ゴミ捨て場をうろつくわけにはいかないんだぞ」
「おねがいよ、もう一度だけいってきて、ね」と、シャーロットはたのみました。
「じゃあ、こうしよう」と、テンプルトンがいいました。「薪小屋に粉せっけんの箱がある。その箱に字が書いてあったから、それを持ってきてやるよ」
テンプルトンは、壁ぎわにさがったロープをよじのぼると、天井の穴にすがたを消しました。もどってきたときには、青と白のボール紙の破片をくわえていました。
「そら!どうだい?」テンプルトンは、勝ちほこったようにいいました。
シャーロットは、書いてある文字を読みました。「すばやくぴかぴか」
「どういう意味なの?」粉せっけんなど、これまでにいちども使ワたことのないシャーロットはききました。
「おれにわかるはずないだろう。宣伝文句がほしいっていうから、持ってきてやっただけさ。このぶんじゃ、つぎは辞書を持ってきてくれっていうんじゃないのか?」
ふたりは、粉せっけんの宣伝文句をじっくりと研究してみました。「すばやくぴかぴか……。ねえ、ウィルバー!」シャーロットがウィルバーをよびました。
わらのなかでねむっていたウィルバーは、とび起きました。
「そこらを走ってみて!」シャーロットが命令しました。「動いたら、ぴかぴかに見えるかしら?」
ウィルバーは、かこいのはしまで走りました。
「もどってきて、もっとはやく!」シャーロットはいいました。
ウィルバーは駆けもどりました。はだがつやつやして、しつぼはきゅつとまるまっています。
「とびあがってみて!」シャーロットがさけびました。
ウィルバーは、できるだけ高くとびあがってみました。
「ひざをまげないで、耳を地面につけてみて!」と、シャーロット。
ウィルバーは、いわれたとおりにしました。
「うしろ宙がえりで体を半分ひねってみて!」
ウィルバーは、体をよじったりひねったりしながら、うしろ宙がえりをしてみせました。
「オーケー、ウィルバー。もう寝床にもどっていいわ」と、シャーロットがいいました。「テンプルトン、粉せっけんの広告でいいみたいね。ウィルバーの動きがぴかぴかかどうかはわからないけど、なかなかおもしろかったわ」
「ぼく、なんだかぴかぴかのかんじがしてきたよ」と、ウィルバーはいいました。
「ほんとに?」シャーロットは、いとおしそうに子ブタを見ながらいいました。「あなたは、すてきな子ブタだし、そのうちぴかぴかになるわ、きっと。どうせこの計画は進めなくちゃならないんだから、少しおおげさにいったっていいわよね」
はねまわってつかれたウィルバーは、きれいなわらの上に横になり、目をつぶりました。わらは、ちくちくしました。やわらかい牛のふんほど気持ちがよくありません。そこで、ウィルバーはわらをどけて、牛ふんの上にねそべりました。ウィルバーは、ため息をつきました。「すばらしい」ブタの最初の日も、いそがしい}日でした。午後には、何十人もの人間がやってきたので、できるだけすばらしいかっこうをして、立っていなければならなかったのです。そんなこんなでウィルバーはくたびれていました。いつのまにかファーンがやってきて、すみのこしかけにそっとすわっていました。
「ねえ、シャーロット、お話ししてよ。お話がききたいよ」ねる用意ができたウィルバーがたのみました。
そこでシャーロットは、自分もくたびれていたのですが、ウィルバーのねがいをきいてやりました。
「むかしむかし、わたしのいとこで、とても美しいクモがいました。そのクモは、小川の上に巣をかけました。ある日、水からぴょんととびあがった小さな魚が、その巣にひっかかってしまいました。わたしのいとこは、びつくりしました。魚は、バタバタとあばれました。いとこは、その魚をなかなかおさえられませんでした。でも、なんとかしなくてはなりません。いとこは、下までおりていって網をどんどんくりだし、魚をがんじがらめにして、つかまえようとしました」
「うまくいったの?」と、ウィルバーはたずねました。
「わすれようとしても、わすれられない戦いになったのよ」と、シャーロットは話をつづけました。「魚はひれの一つが網にひっかかっていたのですが、うろこをきらめかせながら、しっぽをバタバタふっていました。魚の重みで、網はやぶけそうでした」
「その魚はどれくらいの重さだったの?」と、ウィルバーは興味しんしんでたずねました。
「さあ、わからないわ。わたしのいとこは、しのびよるかと思うと、さっと攻撃をかわし、あばれる魚に頭を容赦なくたたかれても、かろやかに近づいたりはなれたりしながら糸をくりだして、勇敢に戦いました。まずは魚のしっぽをめがけて、左のパンチ。魚も打ちかえします。つぎに左のパンチをしつぼにあびせたと思うと、右のパンチで胴体攻撃。魚が打ちかえす。いとこは、すばやくその攻撃をかわし、右のパンチ。そして、ひれにも、もう一発。つづいて、強烈な左のパンチを頭にくらわせたので、網がゆれて、ビヨーンとのびました」
「それから、どうなったの?」と、ウィルバーはたずねました。
「どうもしないわ。魚が負けたのよ。わたしのいとこが魚をぐるぐるまきにしたので、身動きがとれなくなっちゃったの」
「それから、どうなったの?」
「どうもしないわ。いとこは、しばらく魚をそのままおいといたんだけど、そのうちちょうどいいころあいになったから、食べちゃったのよ」
「もう一つ、お話ししてよ!」ウィルバーがせがみました。
そこでシャーロットは、またべつのいとこの話をしました。こんどのいとこは、気球乗りでした。
「それ、どんな仕事なの?」と、ウィルバーがたずねました。
「気球に乗って空をとぶのよ。このいとこは、さかだちをして、いっぱい糸をくりだし、気球をつくったの。それからその気球といっしょに、あたたかい風に乗って旅をしたの」
「それって、ほんとの話なの?それとも、つくり話なの?」ウィルバーはたずねました。
「ほんとの話よ。わたしには、すごいいとこが何人もいるのよ。さあ、ウィルバー、もうねる時間よ」
「だったら、なにかうたってよ」目をつぶりながら、ウィルバーはせがみました。
そこでシャーロットは、こもり歌をうたってくれました。草のなかではコオロギが鳴き、納屋は暗くなっていました。シャーロットがうたったのは、こんな歌でした。
おやすみ、おやすみ、いい子だね
暗闇につつまれて、牛ふんの上で
心配しないで、さびしがらないで
カエルやツグミは森や草地で
美しい世界をたたえているよ
ぐっすりおやすみ、やすらかに
暗闇に包まれて、牛ふんの上で
けれども、歌がおわらないうちに、ウィルバーは、もうぐっすりねむっていました。シャーロットの歌がおわると、ファーンは立ちあがって家に帰りました。
Charlotte's Web 14