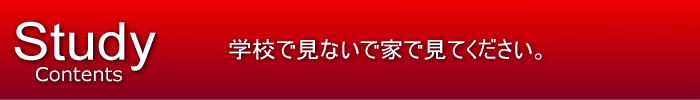Ⅹ. An Explosion
( 10. 破裂したたまご)
Day after day the spider waited, head-down, for an idea to come to her. Hour by hour she sat motionless, deep in thought. Having promised Wilbur that she would save his life, she was determined to keep her promise.
(クモのシャーロットは、くる日もくる日も頭をさかさにして、いい考えが浮かぶのを待っていました。何時間もじっと動かないまま、考えに考えていたのです。命を助けてあげるとウィルバーに約束したからには、どうあってもその約束を守らなければなりません。)
Charlotte was naturally patient. She knew from experience that if she waited long enough, a fly would come to her web; and she sure that if she thought long enough about Wilbur's problem, an idea would come to her mind.
(シャーロットは、もともと我慢強いたちでした。これまでの経験から、じっと待っていれば、そのうち網にハエが飛び込んでくることを、シャーロットは知っていました、だから、ウィルバーの事だって、ずっと考えていれば、きっと名案が浮かぶだろうと思っていたのです。)
Finally, one morning toward the middle of July, the idea came. "Why, how perfectly simple!" she said to herself. "The way to save Wilbur's life is to play a trick on Zuckerman. If I can fool a bug," thought Charlotte, "I can surely fool a man. People are not as smart as bugs."
(そして、7月のなかばごろのある朝、とうとう名案がうかびました。「まあ、ほんとうにかんたんなことじゃにゃぁーの!」シャーロットは、ひとり言をいいました。「ウィルバーの命を救うためには、ザッカーマンさんをうまくだませばいいんだわ。虫をごまかすことが出来るんなら、人間だってごまかすことが出来るはず。人間なんて、虫ほど利口じゃないんですもの」)
Wilbur walked into his yard at that moment.
(そのときちょうど、ウィルバーが庭に出てきました。)
"What are you rhinking about, Charlotte?" he asked.
(「何を考えてるの、シャーロット?」)
"I was just thinking," said the spider, "that people are very gullible."
(「人間をあざむくのは、簡単だってかんがえてたとこよ」)
"What does 'gullible' mean?"
(「『あざむく』ってどういうこと?」)
"Easy to fool," said Charlotte.
(「だますってことよ」)
"That's a mercy," replied Wilbur, and he lay down in the shade of his fence and went fast asleep. The spider, however, stayed wide awake, gazing affectionately at him and making plans plans for his future. Summer was half gone. She knew she didn't have much time.
(「それならよかった」ウィルバーはそういうと、へいのかげにごろんと横になり、ぐっすりと眠り込んでしまいました。けれども、クモのシャーロットはパッチリと大きな目でウィルバーをいとおしげに見やりながら、これから先の計画を練っていました。夏はもう半分しかのこってはいません。ぐずぐずしていられないのです。)
That morning, just as Wilbur fell asleep, Avery Arable wanderd into the Zuckerman's front yard, followed by Fern. Avery carried a live frog in his hand. Fern had a crown of daisies in her hair. The children ran for the kitchen.
(その朝、ウィルバーがひとねむりしているとき、エイヴリー・エラブルが、ザッカーマンさんの前庭にやってきました。ファーンも、うしろからついてきま,す。エイヴリーは、生きたカエルを手に持ち、ファーンは、ヒナギクでつくったかんむりを、頭にかぶっていました。子どもたちは、走って台所に入ってきました。)
"Just in time for a piece of blueberry pie," said Mrs. Zuckerman.
(「ブルーベリーパイにちょうどまにあったわね」ザッカーマンのおばさんがいいました。)
"Look at my frog!" said Avery, placing the frog on the drainboard and holding out his hand for pie.
(「ぼくのカエル、見てよ!」エイヴリーは、カエルを流しの横の水きり板の上におき、パイをもらおうと手をのばしました。)
"Take that thing out of here!" said Mrs. Zuckerman.
(「それ、流しからどかしてちょうだい!」ザッカーマンのおばさんがいいました。)
"He's hot," said Fern. "He's almost dead, that frog."
(「このカエル、暑さにぐったりして、死にそうなの」ファーンがいいました。)
"He is hot," said Avery. "He lets me scratch him between the eyes." The frog jumped and landed in Mrs. Zuckerman's dishpan full of soapy water.
(「そんなことないよ。こいつは、目のあいだをなでても平気なんだ」エイヴリーがいいました。カエルがぴょんとはねて、洗剤を入れた洗いおけのなかにとびこみました。)
"You're getting your pie on you," said Fern. "Can I look for eggs in the henhouse, Aunt Edith?"
(「お兄ちゃん、顔にパイがついてるわよ。ねえ、イーディスおばさん、ニワトリ小屋にたまごをさがしにいってもいい?」ファーンがいいました。)
"Run outdoors, both of you! And don't bother the hens!"
(「ふたりとも、外で遊んできなさい!ニワトリにはかまうんじゃないよ!」)
"It's getting all over everything," shouted Fern. "His pie is all over his front."
(「そこらじゅうにパイのくずがついてるわ」ファーンが大声でいいました。「お兄ちゃんの服、パイだらけになっちゃってる」)
"Come on, frog!" cried Avery. He scooped up his frog. The frog kicked, splashing soapy water onto the blueberry pie.
(「おいカエル、いくぞ!」エイヴリーはそういうと、ヵエルをすくいあげました。カエルがあばれたので、お皿を洗う水がブルーベリーパイにはねました。)
"Another crisis!" groaned Fern.
(「あらあら!」ファーンが、うめき声をあげました。)
"Let's swing in the swing!" said Avery.
(「ブランコで遊ぼう!」エイヴリーがいいました。)
The children ran to the barn.
(子どもたちは、納屋まで走っていきました。)
Mr. Zuckerman had the best swing in the county. It was a single long piece of heavy rope tied to the beam over the north doorway. At the bottom end of the rope was a fat knot to sit on. It was arranged so that you could swing without being pushed.
(ザッカーマンさんの納屋には、群いちばんといってもいいブランコがありました。それは一本の太いロープで、北側の戸口の梁にゆわえつけてありました。ロープのはしには結びめがそってあって、その上にまたがることができるのです。このブランコはおしててもらわなくてもいいようにつくってありました。)
You climbed a ladder to the hayloft. Then, holding the rope, you stood at the edge and looked down, and were scared and dizzy. Then you straddled the knot, so that it acted as a seat. Then you got up all your nerve, took a deep breath, and jumped. For a second you seemed to be falling to the barn floor far below, but then suddenly the rope would begin to vatch you, and you would sail through the barn door going a mile a minute, with the wind whistling in your eyes and ears and hair. Then you would zoom upward into the sky, and look up at the clouds, and the rope would twist and you would twist and turn with the rope. Then you would drop down, down, down out of the sky and come sailing back into the barn almost into the hayloft, then sail out again (not quite so far this time), then in again (not quite so high), then out again, then in again, then out, then in; and then you'd jump off and fall down and let somebody else try it.
(まずはしごを使って、屋根裏の干し草おき場までのぼります。それから、ロープをにぎって干草おき場のへりに立って下を見るのですが、このときは頭がくらくらとして、こわくなります。つぎにロープの結びめにまたがります。そうしたら、勇気をふりしぼって、深く息を吸いこみ、とびおりるのです。ちょっとのあいだ、はるか下の納屋の床に墜落しそうな気がしますが、ふいにロープがぴんと張って、納屋の戸口を外に向かって勢いよく飛び出していくことになります。目にも耳にも紙にも風が吹き付けてきます。体が空に向かってどんどんあがっていきます。雲までとどくかと思ったとたん、ロープがくるっとまわり、しがみついている体もくるっとまわります。そして、こんどは空から下へとぐんぐんおりていって、納屋のなかにもどり、干し草おき場にもう少しでとどきそうな高さまでいくと、また向きをかえて、もう一度、外に向かって進んでいき(さっきよりは高くまでいきませんが)、またなかにもどってきて(さっきよりは高くないのですが)、外にいき、なかにもどり、外にいき、なかにもどり、そのうちにぴょんととびおりることができるようになるのです。そうしたら、つぎの人と交代します。)
Mothers for miles around worried about Zuckerman's swing. Then feared some child would fall off. But no child ever did. Children almost always hang onto things tighter than their parents think they will.
(近所のお母さんたちは、ザッカーマンさんのブランコのことで気をもんでいました。そのうちに、ブランコから落ちる子がでるんじゃないかと心配していたのです。でも、これまでに落ちた子はひとりもいませんでした。子どもというのはたいてい、親が思うよりしっかりとしがみついているものなのです。)
Avery put the frog in his pocket and climbed to the hayloft. "The last time I swang in this swing, I almost crashed into a barn swallow," he yelled.
(エイヴリーはカエルをポケットに入れて、干し草おき場までのぼりました。「このあいだ、このブランコで遊んだときは、ツバメにぶつかりそうになったんだ」エイヴリーがどなりました。)
"Take that frog out!" ordered Fern.
(「カエルをだしてあげて!」ファーンがいいました。)
Avery straddled the rope and jumped. He sailed out through the door, frog and all, and into the sky, frog and all. Then he sailed back into the barn.
(エイヴリーは、ロープのこぶにまたがって、とびおりました。カエルといっしょに戸口からビューンととびだし、カエルといっしょに空に向かってあがっていき、また納屋にもどってきます。)
"Your tongue is purple!" screamed Fern.
(「お兄ちゃんの舌ブルーベリーのせいで、むらさき色になってるわよ!」ファーンがどなりました。)
"So is yours!" cried Avery, sailing out again with the frog.
(「おまえのだってさ!」カエルといっしょにまたとびだしていきながら、エイヴリーがどなりかえしました。)
"I have hay inside my dress! It itches!" called Fern.
(「干し草が服の中に入っちゃったの!かゆいわ!」ファーンがどなりました。)
"Scratch it!" yelled Avery, as he sailed back.
(「かけばいいさ!」プランコに乗ったまま、また納屋にもどってきながら、エイヴリーがいいました。)
"It's my turn," said Fern. "Jump off!"
(「こんどはあたしの番でしょ。早くとびおりてよ!」ファーンがいいました。)
"Fern's got the itch!" sang Avery.
(「ファーンかゆい!」エイヴリーが、からかってうたいました。)
When he jumped off, he threw the swing up to his sister. She shut her eyes tight and jumped. She felt the dizzy drop, then the supporting lift of the swing. When she opened her eyes she was looking up into the blue sky and was about to fly back through the door.
(それでもロープからとびおりると、妹に向かってロープを投げあげました。ファーンはそのロープをつかむと、目をぎゅつとつぶったままとびおりました。落ちていくときのくらくらするかんじがおわって、ロープがぴんと張ってささえてくれたので目をあけてみると、青い空が目の前にひろがり、納屋に向かって今にももどろうとしているところでした。)
They took turns for an hour.
(ふたりは、一時間ばかりブランコで遊びました。)
When the children grew tired of swinging, they went down toward the pasture and picked wild raspberries and ate them. Their tongues turned from purple to red. Fern bit into a raspberry that had a bad-tasting bug inside it, and got discouraged. Avery found an empty candy box and put his frog in it. The frog seemed tired after his morning in the swing. The children walked slowly up toward the barn. They, too, were tired and hardly had energy enough to walk.
(ブランコに飽きると、ふたりは野原に出て、野生のキイチゴをつんで食べました。ふたりの舌は、むらさき色から赤にかわりました。そのうちにファーンは、キイチゴのなかにいたまずい味の虫をかじってしまい、つむのをやめました。エイヴリーは、キャンディーのあき箱を見つけて、そのなかにカエルを入れました。さんざんブランコにゆられたカエルは、どうもつかれているようでした。子どもたちは、またゆっくりと納屋までもどっていきました。このふたりもつかれていて、ようやく歩けるくらいの力しかのこってはいませんでした。)
"Let's build a tree house," suggested Avery. "I want to live in a tree, with my frog."
(「木の家をつくろうよ」と、エイヴリーがいいだしました。「カエルといっしょに、木の上でくらすんだ」)
"I'm going to visit Wilbur," Fern announced.
(「あたしは、ウィルバーを見にいくわ」ファーンがいいました。)
They climbed the fence into the lane and walked lazily toward the pigpen. Wilbur heard them coming and got up.
(ふたりはへいをよじのぼって、のろのろとブタのかこいのほうへ歩いていきました。ウィルバーが足音をききつけて、起きあがりました。)
Avery noticed the spider web, and, coming closer, he saw Charlotte.
(エイヴリーは、クモの巣を見て近よっていき、シャーロットを見つけました。)
"Hey, look at that big spider!" he said. "It's tremenjus."
(「わあ、でかいクモがいるぞ!すげえな」)
"Leave it alone!" commanded Fern. "You've got a frog--isn't that enough?"
(「ちょっかいださないで!お兄ちゃんにはカエルがいるでしょ」ファーンがいいました。)
"That's a fine spider and I'm going to capture it." said Avery. He took the cover off the candy box. Then he picked up a stick. "I'm going to knock that ol' spider into this box," he said.
(「りっぱなクモじゃないか。つかまえてやろう」エイヴリーはそういうと、キャンディーの箱のふたを取り、棒きれをつかみました。「この棒でゆすって、くもを箱のなかに落としてやるんだ」)
Wilbur's heart almost stopped when he saw what was going on. Theis might be the end of Charlotte if the boy succeeded in catching her.
(なにが起ころうとしているかがわかると、ウィルバーははっとして、心臓がとまりそうになりました。男の子につかまったら、シャーロットはおしまいです。)
"You stop it, Avery!" cried Fern.
(「やめて、お兄ちゃん!」ファーンが、大声をあげました。)
Avery put one leg over the fence of the pigpen. He was just about to raise his stick to hit Charlotte when he lost his balance. He swayed and toppled and landed on the edge of Wilbur's trough. The trough tipped up and then came down with a slap. The goose egg was right underneath. There was a dull explosion as the egg broke, and then a horrible smell.
(エイヴリーは、片足をブ'タのかこいのへいにかけ、棒きれを持ちあげて、シャーロットをはたき落とそうとしていました。ところがそのとき、エイヴリーはバランスをくずし、ぐらっとよろめくと、ウィルバーのえさ箱の上にドスンと落ちました。えさ箱がバタンとひっくりかえりました。えさ箱の下には、ガチョウのたまごがありました。ブスッと音がして、くさっていたたまごが割れると、なかからとんでもなくくさいにおいがしてきました。)
Fern screamed. Avery jumped to his feet. The air was filled with the terrible gases and smells from the rotten egg. Templeton, who had been resting in his home, scuttled away into the barn.
(ファーンが悲鳴をあげ、エイヴリーはあわてて立ちあがりました。そこらじゅうに、くさったたまごのにおいがただよいます。巣のなかで休んでいたテンプルトンも、納屋のなかににげこみました。)
"Good night!" screamed Avery. "Good night! What a stink! Let's get out of here!"
(「うわっ、たいへんだ!なんてにおいなんだ!早いとこここからでよう!」エイヴリーがさけびました。)
Fern was crying. She held her nose and ran toward the house. Avery ran after her, holding his nose. Charlotte felt greatly relieved to see him go. It had been a narrow escape.
(ファーンが、泣きながら鼻をおさえて、あわてて家まで走ります。エイヴリーも、鼻をおさえて、あとにつづきました。エイヴリーがもどっていくのを見て、シャーロットはほっと息をつきました。あぶないところでした。)
Later on that morning, the animals came up from the pasture--the sheep, the lambs. the gander, the goose, and the seven goslings. There were many complaints about the awful smell, and Wilbur had to tell the story over and over again, of how the Arable boy had tried to caoture Charlotte, and how the smell of the broken egg drove him away just in time. "It was that rotten goose egg that saved Charlotte's life," said Wilbur.
(お昼近くなって、子どもをつれた羊や、七羽のひなをつれたガチョウ一家が野原からもどってきました。ひどいにおいがすると、みんなが文句をいうたびに、ウィルバーは、何度も事件の話をしてきかせました。エラブル家の男の子が、どうやってシャーロットをつかまえようとしたか、そして割れたたまごのくさいにおいが、どうやって男の子を追いはらったか、という話です。「シャーロットの命を救ったのは、ガチョウのくさった卵だったんだ」と、ウィルバーは言いました。)
The goose was proud of her share in the adventure. "I'm delighted that the egg never hatched," she gabbled.
(事件にひと役買ったガチョウのおばさんは、ほこらしげな顔で、「あのたまごがかえらなくて、ほんとによかったね」と、いいまレた。)
Templeton, of course, was miserable over the loss of his beloved egg. But he couldn't resist boasting. "It pays to save things," he said in his surly voice. "A rat never knows when something is going to come in handy. I never throw anything away."
(だいじにしていたたまごをなくしたテンプルトンは、もちろんぜんぜんうれしくはありませんでした。それでも、むっつりした声ながら、こんなふうにじまんしないではいられませんでした。)
"Well," said one of the lambs, "this whole business is all well and good for Charlotte, but what about the rest of us? The smell is unbearable. Who wants to live in a barn that is perfumed with rotten egg?"
(「でもね」と、一ぴきの子羊がいいました。「こんどのことは、シャーロットにとってはよかったけど、ほかのみんなにとってはどうなの?このにおいは、たまらないわ。くさったたまごのにおいがぷんぷんする納屋になんて、だれが住もうと思うもんですか」)
"Don't worry, you'll get used to it," said Templeton. He sat up and pulled wisely at his long whiskers, then crept away to pay a visit to the dump.
(「心配するなって。すぐに慣れちまうさ」そういうと、テンプルトンは上半身を起こして、長いひげを考えぶかそうにこすり、それからゴミ捨て場をあさりにいきました。)
When Lurvy showed up at lunchtime carrying a pail of food for Wilbur, he stopped short a few paced from the pigpen. He sniffed the air and made a face.
(お昼どきになると、ラーヴィーが、ウィルバーのえさをバケツに入れてやってきました。ラーヴィーは、ブタのかこいから数歩のところまでくると立ちどまり、においをかいで顔をしかめました。)
"What in thunder?" he said. Setting the pail down, he picked up the stick that Avery had dropped and pried the trough up. "Rats!" he said. "Fhew! I might a' known a rat would make a nest under this trough. How I hate a rat!"
(「こりゃ、いったいどうしたんだ?」そういうと、ラーヴィーはバケツを下におき、エイヴリーが落としていった棒きれを拾いあげて、えさ箱を起こしました。「ネズミだな!やれやれ!えさ箱の下に、ネズミが巣をつくってたってわけだ。おれは、ネズミがきらいなんだよ!」)
And Lurvy dragged Wilbur's trough across the yard and kicked some dirt into the rat's nest, burying the broken egg and all Templeton's other possessions. Then he picked up the pail. Wilbur stood in the trough, drooling with hunger. Lurvy poured. The slops ran creamily down around the pig's eyes and ears. Wilbur grunted. He gulped and sucked, and sucked and gulped, making swishing and swooshing noises, anxious to get everything at once. It was a delicious meal--skim milk, wheat middlings, leftover pancakes, half a doughnut, the rind of a summer squash, two pieces of stale toast, a third of a gingersnap, a fish tail, one orange peel, several noodles from a noodle soup, the scum off a cup of cocoa, an ancient jelly roll, a strip of paper from the lining of the garbage pail, and a spoonful of raspberry jello.
(ラーヴィーは、ウィルバーのえさ箱をどかして、足で土をほると、割れたたまごもテンプルトンのほかの持ちものもいっしょくたにして、ネズミの巣をうめてしまいました。それから、バケツをもちあげました。ウィルバーは、よだれをたらしながら、えさ箱のなかに立っていました。ラーヴイーがバケツの中身をあけると、ウィルバーの目や耳に残飯がどろどろとかかりました。ウィルバーは満足の声をあげながら、それをのみこんではすすり、すすってはのみこみ、クチャクチャパクパク音を立てながら、いちどになにもかもを食べようとしました。なんておいしいんでしょう。スキムミルク、小麦飼料、パンケーキの食べのこし、ドーナツが半分、ペポカボチャの皮、ひからびたトーストが二きれ、ショウガ入りクッキーが三分の一、魚のしっぽ、オレンジの皮、スープに入っていたヌードルが数本、ココアの膜、わるくなりかけたゼリーロール、ゴミバケツの内側にはってあった紙の一部、それにラズベリー味のゼリーもひとさじ入っていました。)
Wilbur ate heartily. He planned to leave half a noodle and a few drops of milk for Templeton. Then he remembered that the rat had been useful in saving Charlotte's life, and that Charlotte was trying to save his life. So he left a whole noodle, instead of a half.
(ウィルバーは、お腹一杯になるまで食べました。テンプルトンにはヌードルを半本と、ミルクをほんのちょっとっぴり残しておくつもりでした。でもシャーロットの命を救うのに、テンプルトンが大きな役割をはたしたことを思いだし、そのシャーロットがじぶんの命を救おうとしてくれていることを思いだすと、ヌードルは一本まるごとのこしておくことにしました。)
Now that the broken egg was buried, tha air cleared and the barn smelled good again. The afternoon passed, and evening came. Shadows lengthened. The cool and kindly breath of evening entered through doors and windows. Astride her web, Charlotte sat moodily eating a horsefly and thinking about the future. After a while she bestirred herself.
(割れたたまごがうめられると、くさいにおいも消えて、納屋はまたいいかおりにつつまれました。午後の時間がすぎていき、夕方になりました。かげが長くのびています。夕ぐれに吹くすずしい風が、戸口やまどから入ってきます。シャーロットは、巣のなかでむっつりとアブを食べながら、将来のことを考えていました。しばらくすると、シャーロットが動きだしました。)
She descended to the center of the web and there she began to cut some of her lines. She worked slowly but steadily while the other sreatures drowsed. None of the others, not even the goose, noticed that she was at work. Deep in his soft bed, Wilbur snoozed. Over in their favorite corner, the goslings whistled a night song.
(網の中央までおりていったシャーロットは、糸を何本か切りました。ほかの動物たちがうとうとしているあいだにも、シャーロットはゆっくりと着実に仕事を進めていきました。ほかの動物たちは、ガチョウのおばさんでさえも、シャーロットがしていることに気づきませんでした。ウィルバーは、やわらかい寝床でまどろんでいました。ガチョウのひなたちは、自分たちのお気に入りのすみっこで、夜の歌を口ずさんでいました。)
Charlotte tore quite a section out of her web, leaving an open space in the middle. Then she started weaving something to take the place of the threads she had removed. When Templeton got back from the dump, around midnight, the spider was still at work.
(シャーロットは巣の一部を切りとり、まんなかに文字を書く場所をつくりました。それから、切りとったところをうめるように、糸をくりだしていきました。夜もふけてテンプルトンがゴミ捨て場からもどってきたときも、まだクモはせっせと働いていました。)
Day after day the spider waited, head-down, for an idea to come to her. Hour by hour she sat motionless, deep in thought. Having promised Wilbur that she would save his life, she was determined to keep her promise.
Charlotte was naturally patient. She knew from experience that if she waited long enough, a fly would come to her web; and she sure that if she thought long enough about Wilbur's problem, an idea would come to her mind.
Finally, one morning toward the middle of July, the idea came. "Why, how perfectly simple!" she said to herself. "The way to save Wilbur's life is to play a trick on Zuckerman. If I can fool a bug," thought Charlotte, "I can surely fool a man. People are not as smart as bugs."
Wilbur walked into his yard at that moment.
"What are you rhinking about, Charlotte?" he asked.
"I was just thinking," said the spider, "that people are very gullible."
"What does 'gullible' mean?"
"That's a mercy," replied Wilbur, and he lay down in the shade of his fence and went fast asleep. The spider, however, stayed wide awake, gazing affectionately at him and making plans plans for his future. Summer was half gone. She knew she didn't have much time.
That morning, just as Wilbur fell asleep, Avery Arable wanderd into the Zuckerman's front yard, followed by Fern. Avery carried a live frog in his hand. Fern had a crown of daisies in her hair. The children ran for the kitchen.
"Just in time for a piece of blueberry pie," said Mrs. Zuckerman.
"Look at my frog!" said Avery, placing the frog on the drainboard and holding out his hand for pie.
"Take that thing out of here!" said Mrs. Zuckerman.
"He's hot," said Fern. "He's almost dead, that frog."
"He is hot," said Avery. "He lets me scratch him between the eyes." The frog jumped and landed in Mrs. Zuckerman's dishpan full of soapy water.
"You're getting your pie on you," said Fern. "Can I look for eggs in the henhouse, Aunt Edith?"
"Run outdoors, both of you! And don't bother the hens!"
"It's getting all over everything," shouted Fern. "His pie is all over his front."
"Come on, frog!" cried Avery. He scooped up his frog. The frog kicked, splashing soapy water onto the blueberry pie.
"Another crisis!" groaned Fern.
"Let's swing in the swing!" said Avery.
The children ran to the barn.
Mr. Zuckerman had the best swing in the county. It was a single long piece of heavy rope tied to the beam over the north doorway. At the bottom end of the rope was a fat knot to sit on. It was arranged so that you could swing without being pushed. You climbed a ladder to the hayloft. Then, holding the rope, you stood at the edge and looked down, and were scared and dizzy. Then you straddled the knot, so that it acted as a seat. Then you got up all your nerve, took a deep breath, and jumped. For a second you seemed to be falling to the barn floor far below, but then suddenly the rope would begin to vatch you, and you would sail through the barn door going a mile a minute, with the wind whistling in your eyes and ears and hair. Then you would zoom upward into the sky, and look up at the clouds, and the rope would twist and you would twist and turn with the rope. Then you would drop down, down, down out of the sky and come sailing back into the barn almost into the hayloft, then sail out again (not quite so far this time), then in again (not quite so high), then out again, then in again, then out, then in; and then you'd jump off and fall down and let somebody else try it.
Mothers for miles around worried about Zuckerman's swing. Then feared some child would fall off. But no child ever did. Children almost always hang onto things tighter than their parents think they will.
Avery put the frog in his pocket and climbed to the hayloft. "The last time I swang in this swing, I almost crashed into a barn swallow," he yelled.
"Take that frog out!" ordered Fern.
Avery straddled the rope and jumped. He sailed out through the door, frog and all, and into the sky, frog and all. Then he sailed back into the barn.
"Your tongue is purple!" screamed Fern.
"So is yours!" cried Avery, sailing out again with the frog.
"I have hay inside my dress! It itches!" called Fern.
"Scratch it!" yelled Avery, as he sailed back.
"It's my turn," said Fern. "Jump off!"
"Fern's got the itch!" sang Avery.
When he jumped off, he threw the swing up to his sister. She shut her eyes tight and jumped. She felt the dizzy drop, then the supporting lift of the swing. When she opened her eyes she was looking up into the blue sky and was about to fly back through the door.
They took turns for an hour.
When the children grew tired of swinging, they went down toward the pasture and picked wild raspberries and ate them. Their tongues turned from purple to red. Fern bit into a raspberry that had a bad-tasting bug inside it, and got discouraged. Avery found an empty candy box and put his frog in it. The frog seemed tired after his morning in the swing. The children walked slowly up toward the barn. They, too, were tired and hardly had energy enough to walk.
"Let's build a tree house," suggested Avery. "I want to live in a tree, with my frog."
"I'm going to visit Wilbur," Fern announced.
They climbed the fence into the lane and walked lazily toward the pigpen. Wilbur heard them coming and got up.
Avery noticed the spider web, and, coming closer, he saw Charlotte.
"Hey, look at that big spider!" he said. "It's tremenjus."
"Leave it alone!" commanded Fern. "You've got a frog--isn't that enough?"
"That's a fine spider and I'm going to capture it." said Avery. He took the cover off the candy box. Then he picked up a stick. "I'm going to knock that ol' spider into this box," he said.
Wilbur's heart almost stopped when he saw what was going on. Theis might be the end of Charlotte if the boy succeeded in catching her.
"You stop it, Avery!" cried Fern.
Avery put one leg over the fence of the pigpen. He was just about to raise his stick to hit Charlotte when he lost his balance. He swayed and toppled and landed on the edge of Wilbur's trough. The trough tipped up and then came down with a slap. The goose egg was right underneath. There was a dull explosion as the egg broke, and then a horrible smell.
Fern screamed. Avery jumped to his feet. The air was filled with the terrible gases and smells from the rotten egg. Templeton, who had been resting in his home, scuttled away into the barn.
"Good night!" screamed Avery. "Good night! What a stink! Let's get out of here!"
Fern was crying. She held her nose and ran toward the house. Avery ran after her, holding his nose. Charlotte felt greatly relieved to see him go. It had been a narrow escape.
Later on that morning, the animals came up from the pasture--the sheep, the lambs. the gander, the goose, and the seven goslings. There were many complaints about the awful smell, and Wilbur had to tell the story over and over again, of how the Arable boy had tried to caoture Charlotte, and how the smell of the broken egg drove him away just in time. "It was that rotten goose egg that saved Charlotte's life," said Wilbur.
The goose was proud of her share in the adventure. "I'm delighted that the egg never hatched," she gabbled.
Templeton, of course, was miserable over the loss of his beloved egg. But he couldn't resist boasting. "It pays to save things," he said in his surly voice. "A rat never knows when something is going to come in handy. I never throw anything away."
"Well," said one of the lambs, "this whole business is all well and good for Charlotte, but what about the rest of us? The smell is unbearable. Who wants to live in a barn that is perfumed with rotten egg?"
"Don't worry, you'll get used to it," said Templeton. He sat up and pulled wisely at his long whiskers, then crept away to pay a visit to the dump.
When Lurvy showed up at lunchtime carrying a pail of food for Wilbur, he stopped short a few paced from the pigpen. He sniffed the air and made a face.
"What in thunder?" he said. Setting the pail down, he picked up the stick that Avery had dropped and pried the trough up. "Rats!" he said. "Fhew! I might a' known a rat would make a nest under this trough. How I hate a rat!"
And Lurvy dragged Wilbur's trough across the yard and kicked some dirt into the rat's nest, burying the broken egg and all Templeton's other possessions. Then he picked up the pail. Wilbur stood in the trough, drooling with hunger. Lurvy poured. The slops ran creamily down around the pig's eyes and ears. Wilbur grunted. He gulped and sucked, and sucked and gulped, making swishing and swooshing noises, anxious to get everything at once. It was a delicious meal--skim milk, wheat middlings, leftover pancakes, half a doughnut, the rind of a summer squash, two pieces of stale toast, a third of a gingersnap, a fish tail, one orange peel, several noodles from a noodle soup, the scum off a cup of cocoa, an ancient jelly roll, a strip of paper from the lining of the garbage pail, and a spoonful of raspberry jello.
Wilbur ate heartily. He planned to leave half a noodle and a few drops of milk for Templeton. Then he remembered that the rat had been useful in saving Charlotte's life, and that Charlotte was trying to save his life. So he left a whole noodle, instead of a half.
Now that the broken egg was buried, tha air cleared and the barn smelled good again. The afternoon passed, and evening came. Shadows lengthened. The cool and kindly breath of evening entered through doors and windows. Astride her web, Charlotte sat moodily eating a horsefly and thinking about the future. After a while she bestirred herself.
She descended to the center of the web and there she began to cut some of her lines. She worked slowly but steadily while the other sreatures drowsed. None of the others, not even the goose, noticed that she was at work. Deep in his soft bed, Wilbur snoozed. Over in their favorite corner, the goslings whistled a night song.
Charlotte tore quite a section out of her web, leaving an open space in the middle. Then she started weaving something to take the place of the threads she had removed. When Templeton got back from the dump, around midnight, the spider was still at work.
日本語訳のみです。
クモのシャーロットは、くる日もくる日も頭をさかさにして、いい考えが浮かぶのを待っていました。何時間もじっと動かないまま、考えに考えていたのです。命を助けてあげるとウィルバーに約束したからには、どうあってもその約束を守らなければなりません。
シャーロットは、もともと我慢強いたちでした。これまでの経験から、じっと待っていれば、そのうち網にハエが飛び込んでくることを、シャーロットは知っていました、だから、ウィルバーの事だって、ずっと考えていれば、きっと名案が浮かぶだろうと思っていたのです。
そして、7月のなかばごろのある朝、とうとう名案がうかびました。
「まあ、ほんとうにかんたんなことじゃにゃぁーの!」シャーロットは、ひとり言をいいました。「ウィルバーの命を救うためには、ザッカーマンさんをうまくだませばいいんだわ。虫をごまかすことが出来るんなら、人間だってごまかすことが出来るはず。人間なんて、虫ほど利口じゃないんですもの」
そのときちょうど、ウィルバーが庭に出てきました。
「何を考えてるの、シャーロット?」
「人間をあざむくのは、簡単だってかんがえてたとこよ」
「『あざむく』ってどういうこと?」
「だますってことよ」
「それならよかった」ウィルバーはそういうと、へいのかげにごろんと横になり、ぐっすりと眠り込んでしまいました。けれども、クモのシャーロットはパッチリと大きな目でウィルバーをいとおしげに見やりながら、これから先の計画を練っていました。夏はもう半分しかのこってはいません。ぐずぐずしていられないのです。
その朝、ウィルバーがひとねむりしているとき、エイヴリー・エラブルが、ザッカーマンさんの前庭にやってきました。ファーンも、うしろからついてきま,す。エイヴリーは、生きたカエルを手に持ち、ファーンは、ヒナギクでつくったかんむりを、頭にかぶっていました。子どもたちは、走って台所に入ってきました。
「ブルーベリーパイにちょうどまにあったわね」ザッカーマンのおばさんがいいました。
「ぼくのカエル、見てよ!」エイヴリーは、カエルを流しの横の水きり板の上におき、パイをもらおうと手をのばしました。
「それ、流しからどかしてちょうだい!」ザッカーマンのおばさんがいいました。
「このカエル、暑さにぐったりして、死にそうなの」ファーンがいいました。
「そんなことないよ。こいつは、目のあいだをなでても平気なんだ」エイヴリーがいいました。カエルがぴょんとはねて、洗剤を入れた洗いおけのなかにとびこみました。
「お兄ちゃん、顔にパイがついてるわよ。ねえ、イーディスおばさん、ニワトリ小屋にたまごをさがしにいってもいい?」ファーンがいいました。
「ふたりとも、外で遊んできなさい!ニワトリにはかまうんじゃないよ!」
「そこらじゅうにパイのくずがついてるわ」ファーンが大声でいいました。「お兄ちゃんの服、パイだらけになっちゃってる」
「おいカエル、いくぞ!」エイヴリーはそういうと、ヵエルをすくいあげました。カエルがあばれたので、お皿を洗う水がブルーベリーパイにはねました。
「あらあら!」ファーンが、うめき声をあげました。
「ブランコで遊ぼう!」エイヴリーがいいました。
子どもたちは、納屋まで走っていきました。
ザッカーマンさんの納屋には、群いちばんといってもいいブランコがありました。それは一本の太いロープで、北側の戸口の梁にゆわえつけてありました。ロープのはしには結びめがそってあって、その上にまたがることができるのです。このブランコはおしててもらわなくてもいいようにつくってありました。
まずはしごを使って、屋根裏の干し草おき場までのぼります。それから、ロープをにぎって干草おき場のへりに立って下を見るのですが、このときは頭がくらくらとして、こわくなります。つぎにロープの結びめにまたがります。そうしたら、勇気をふりしぼって、深く息を吸いこみ、とびおりるのです。ちょっとのあいだ、はるか下の納屋の床に墜落しそうな気がしますが、ふいにロープがぴんと張って、納屋の戸口を外に向かって勢いよく飛び出していくことになります。目にも耳にも紙にも風が吹き付けてきます。体が空に向かってどんどんあがっていきます。雲までとどくかと思ったとたん、ロープがくるっとまわり、しがみついている体もくるっとまわります。そして、こんどは空から下へとぐんぐんおりていって、納屋のなかにもどり、干し草おき場にもう少しでとどきそうな高さまでいくと、また向きをかえて、もう一度、外に向かって進んでいき(さっきよりは高くまでいきませんが)、またなかにもどってきて(さっきよりは高くないのですが)、外にいき、なかにもどり、外にいき、なかにもどり、そのうちにぴょんととびおりることができるようになるのです。そうしたら、つぎの人と交代します。
近所のお母さんたちは、ザッカーマンさんのブランコのことで気をもんでいました。そのうちに、ブランコから落ちる子がでるんじゃないかと心配していたのです。でも、これまでに落ちた子はひとりもいませんでした。子どもというのはたいてい、親が思うよりしっかりとしがみついているものなのです。
エイヴリーはカエルをポケットに入れて、干し草おき場までのぼりました。
「このあいだ、このブランコで遊んだときは、ツバメにぶつかりそうになったんだ」エイヴリーがどなりました。
「カエルをだしてあげて!」ファーンがいいました。
エイヴリーは、ロープのこぶにまたがって、とびおりました。カエルといっしょに戸口からビューンととびだし、カエルといっしょに空に向かってあがっていき、また納屋にもどってきます。
「お兄ちゃんの舌ブルーベリーのせいで、むらさき色になってるわよ!」ファーンがどなりました。
「おまえのだってさ!」カエルといっしょにまたとびだしていきながら、エイヴリーがどなりかえしました。
「干し草が服の中に入っちゃったの!かゆいわ!」ファーンがどなりました。
「かけばいいさ!」プランコに乗ったまま、また納屋にもどってきながら、エイヴリーがいいました。
「こんどはあたしの番でしょ。早くとびおりてよ!」ファーンがいいました。
「ファーンかゆい!」エイヴリーが、からかってうたいました。
それでもロープからとびおりると、妹に向かってロープを投げあげました。ファーンはそのロープをつかむと、目をぎゅつとつぶったままとびおりました。落ちていくときのくらくらするかんじがおわって、ロープがぴんと張ってささえてくれたので目をあけてみると、青い空が目の前にひろがり、納屋に向かって今にももどろうとしているところでした。
ふたりは、一時間ばかりブランコで遊びました。
ブランコに飽きると、ふたりは野原に出て、野生のキイチゴをつんで食べました。ふたりの舌は、むらさき色から赤にかわりました。そのうちにファーンは、キイチゴのなかにいたまずい味の虫をかじってしまい、つむのをやめました。エイヴリーは、キャンディーのあき箱を見つけて、そのなかにカエルを入れました。さんざんブランコにゆられたカエルは、どうもつかれているようでした。子どもたちは、またゆっくりと納屋までもどっていきました。このふたりもつかれていて、ようやく歩けるくらいの力しかのこってはいませんでした。
「木の家をつくろうよ」と、エイヴリーがいいだしました。「カエルといっしょに、木の上でくらすんだ」
「あたしは、ウィルバーを見にいくわ」ファーンがいいました。
ふたりはへいをよじのぼって、のろのろとブタのかこいのほうへ歩いていきました。ウィルバーが足音をききつけて、起きあがりました。
エイヴリーは、クモの巣を見て近よっていき、シャーロットを見つけました。
「わあ、でかいクモがいるぞ!すげえな」
「ちょっかいださないで!お兄ちゃんにはカエルがいるでしょ」ファーンがいいました。
「りっぱなクモじゃないか。つかまえてやろう」
エイヴリーはそういうと、キャンディーの箱のふたを取り、棒きれをつかみました。「この棒でゆすって、くもを箱のなかに落としてやるんだ」
なにが起ころうとしているかがわかると、ウィルバーははっとして、心臓がとまりそうになりました。男の子につかまったら、シャーロットはおしまいです。
「やめて、お兄ちゃん!」ファーンが、大声をあげました。
エイヴリーは、片足をブ'タのかこいのへいにかけ、棒きれを持ちあげて、シャーロットをはたき落とそうとしていました。ところがそのとき、エイヴリーはバランスをくずし、ぐらっとよろめくと、ウィルバーのえさ箱の上にドスンと落ちました。えさ箱がバタンとひっくりかえりました。えさ箱の下には、ガチョウのたまごがありました。ブスッと音がして、くさっていたたまごが割れると、なかからとんでもなくくさいにおいがしてきました。
ファーンが悲鳴をあげ、エイヴリーはあわてて立ちあがりました。そこらじゅうに、くさったたまごのにおいがただよいます。巣のなかで休んでいたテンプルトンも、納屋のなかににげこみました。
「うわっ、たいへんだ!なんてにおいなんだ!早いとこここからでよう!」エイヴリーがさけびました。
ファーンが、泣きながら鼻をおさえて、あわてて家まで走ります。エイヴリーも、鼻をおさえて、あとにつづきました。エイヴリーがもどっていくのを見て、シャーロットはほっと息をつきました。あぶないところでした。
お昼近くなって、子どもをつれた羊や、七羽のひなをつれたガチョウ一家が野原からもどってきました。ひどいにおいがすると、みんなが文句をいうたびに、ウィルバーは、何度も事件の話をしてきかせました。エラブル家の男の子が、どうやってシャーロットをつかまえようとしたか、そして割れたたまごのくさいにおいが、どうやって男の子を追いはらったか、という話です。「シャーロットの命を救ったのは、ガチョウのくさった卵だったんだ」と、ウィルバーは言いました。
事件にひと役買ったガチョウのおばさんは、ほこらしげな顔で、「あのたまごがかえらなくて、ほんとによかったね」と、いいまレた。
だいじにしていたたまごをなくしたテンプルトンは、もちろんぜんぜんうれしくはありませんでした。それでも、むっつりした声ながら、こんなふうにじまんしないではいられませんでした。
「なんでも、とっておけば役に立つのさ。そのうちなにが入り用になるか、わかったもんじゃないだろ。だから、捨てないで、なんでもとっておくのさ」
「でもね」と、一ぴきの子羊がいいました。「こんどのことは、シャーロットにとってはよかったけど、ほかのみんなにとってはどうなの?このにおいは、たまらないわ。くさったたまごのにおいがぷんぷんする納屋になんて、だれが住もうと思うもんですか」
「心配するなって。すぐに慣れちまうさ」
そういうと、テンプルトンは上半身を起こして、長いひげを考えぶかそうにこすり、それからゴミ捨て場をあさりにいきました。
お昼どきになると、ラーヴィーが、ウィルバーのえさをバケツに入れてやってきました。
ラーヴィーは、ブタのかこいから数歩のところまでくると立ちどまり、においをかいで顔をしかめました。
「こりゃ、いったいどうしたんだ?」
そういうと、ラーヴィーはバケツを下におき、エイヴリーが落としていった棒きれを拾いあげて、えさ箱を起こしました。
「ネズミだな!やれやれ!えさ箱の下に、ネズミが巣をつくってたってわけだ。おれは、ネズミがきらいなんだよ!」
ラーヴィーは、ウィルバーのえさ箱をどかして、足で土をほると、割れたたまごもテンプルトンのほかの持ちものもいっしょくたにして、ネズミの巣をうめてしまいました。それから、バケツをもちあげました。ウィルバーは、よだれをたらしながら、えさ箱のなかに立っていました。ラーヴイーがバケツの中身をあけると、ウィルバーの目や耳に残飯がどろどろとかかりました。ウィルバーは満足の声をあげながら、それをのみこんではすすり、すすってはのみこみ、クチャクチャパクパク音を立てながら、いちどになにもかもを食べようとしました。なんておいしいんでしょう。スキムミルク、小麦飼料、パンケーキの食べのこし、ドーナツが半分、ペポカボチャの皮、ひからびたトーストが二きれ、ショウガ入りクッキーが三分の一、魚のしっぽ、オレンジの皮、スープに入っていたヌードルが数本、ココアの膜、わるくなりかけたゼリーロール、ゴミバケツの内側にはってあった紙の一部、それにラズベリー味のゼリーもひとさじ入っていました。
ウィルバーは、お腹一杯になるまで食べました。テンプルトンにはヌードルを半本と、ミルクをほんのちょっとっぴり残しておくつもりでした。でもシャーロットの命を救うのに、テンプルトンが大きな役割をはたしたことを思いだし、そのシャーロットがじぶんの命を救おうとしてくれていることを思いだすと、ヌードルは一本まるごとのこしておくことにしました。
割れたたまごがうめられると、くさいにおいも消えて、納屋はまたいいかおりにつつまれました。午後の時間がすぎていき、夕方になりました。かげが長くのびています。夕ぐれに吹くすずしい風が、戸口やまどから入ってきます。シャーロットは、巣のなかでむっつりとアブを食べながら、将来のことを考えていました。しばらくすると、シャーロットが動きだしました。
網の中央までおりていったシャーロットは、糸を何本か切りました。ほかの動物たちがうとうとしているあいだにも、シャーロットはゆっくりと着実に仕事を進めていきました。ほかの動物たちは、ガチョウのおばさんでさえも、シャーロットがしていることに気づきませんでした。ウィルバーは、やわらかい寝床でまどろんでいました。ガチョウのひなたちは、自分たちのお気に入りのすみっこで、夜の歌を口ずさんでいました。
シャーロットは巣の一部を切りとり、まんなかに文字を書く場所をつくりました。それから、切りとったところをうめるように、糸をくりだしていきました。夜もふけてテンプルトンがゴミ捨て場からもどってきたときも、まだクモはせっせと働いていました。
Charlotte's Web 11