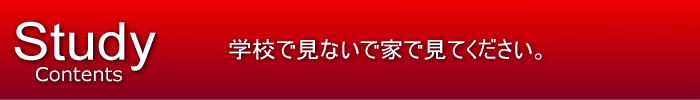Charlotte's Web 3
Ⅲ. Escape
( 3.にげろ!)
The baran was very large. It was very old. It smelled of hey and it smelled of tired horses and the wonderful sweet breath of patient cows. It often had a sort of peaceful smell--as though nothing bad could happen ever again in the world. It smelled of grain and of harness dressing and of axle grease and of rubber boots and of new rope. And whenever the cat was given a fish-head to eat, the barn would smell of fish. But mostly it smelled of hay, for there was always hay in the great loft up overhead. And there was always hay being pitched down to the cows and the horses and the sheep.
(ウィルバーが暮らすことになったのは、とても古く大きな納屋で、干草と堆肥のにおいがしました。くたびれた馬のあせのにおいと、しんぼう強い雌牛のあまやかな息のにおいもしました。たいていは、安らかで平和なにおいに満ちていたので、世の中にはもう2度と悪いことなど起こらないように思えました。それに、穀物や、馬具をみがく油や、車軸につける機械油、ゴム長ぐつや新しいロープのにおいもしていました。ネコが魚の頭をもらうと、納屋は魚くさくもなりました。でも、いちばん強くにおうのは、なんといっても干草でした。というのも、納屋の2階には、干草がどっさりつんであったのです。その干草は、下にいる牝牛や馬や羊に必要とあれば、いつでも上から投げ下ろされるのでした。)
The barn was pleasantly warm in winter when the animals spent most of their time indoors, and it was pleasantly cool in summer when the big doors stood wide open to the breeze. The barn had stalls on the main floor for the work horses, tie-ups on the main floor for the cows, a sheepfold down below for the sheep, a pigpen down below for Wilbur, and it was full of all sorts of things that you find in barns: ladders, grindstones, pitch forks, monkey wrenches, scythes, lawn mowers, snow shovels, ax handles, milk pails, water buckets, empty grain sacks, and rusty rat traps. It was the kind of barn that swallows like to build their neses in. It was the kind of barn that children like to play in. And the whole thing was owned by Fern's uncle, Mr.Homer L.Zuckerman.
(動物たちがほとんどの時間を屋内で過ごす冬でも、納屋の中は暖かでした。そして夏には、大きなとびらがあけはなたれて風が入ってくるので、なかなか涼しいのでした。納屋の1階には、農耕馬や牝牛のための部屋があり、床下には羊の部屋やウィルバーのためのブタの部屋がありました。それに、この納屋の中には、はしごだとか、丸砥石だとか、くまでだとか、モンキースパナだとか、かまだとか、芝刈り機だとか、雪かきシャベルだとか、斧の枝とか、ミルク容器だとか、バケツだとか、からっぽの穀物袋だとか、さびたネズミとりだとか、ふつうの納屋にありそうなものは、なんでもありました。それに、ここは、ツバメが巣を作りたいと思うような納屋でした。そして子供が遊びたいと思うような、そんな納屋でもありました。そして、納屋にあるものはみんな、ホーマー・L・ザッカーマンという名前の、ファーンおおじさんのものでした。)
Wilbur's new home was in the lower part of the barn, directly underneath ihe cows. MrZuckerman knew that a manure pile is a good place to keep a young pig. Pigs need warmth, and it was warm and comfortable down there in the barn cellar on the south side.
(ウィルバーの新しい部屋は、牝牛たちの部屋のすぐ下にありました。ザッカーマンさんは、小さい子ブタを飼うには、堆肥の山がちょうどいいことを知っていたのです。ブタは暖かいのが好きでしたし、納屋の床下の南側は、ぬくぬくとあたたかったのです。)
Fern came slmost every day to visit him. She found an old milking stool that had been discarded, and she placed the stool in the sheepfold next to Wilbur's pen. Here she sat quietly during the long afternoons, thinking and listening and watching Wilbur. The sheep soon got to know her and trust her. So did the geese, who lived with the sheep. All the animals trusted her, she was so quiet and friendly. Mr.Zuckerman did not allow her to take Wilbur out, and he did not allow her to get into the pigpen. But to hold Fern that she could sit on the stool and watch Wilbur as long as she wanted to. It made her happy just to be near the pig, and it made Wilbur happy to know that she was sitting there, right outside his pen. But he never had any fun--no walks, no rides, no swaims.
(ファーンは毎日のようにウィルバーに会いに行きました。父絞りの時に使ういすが捨ててあったので、ファーンはそのいすをウィルバーの部屋の隣にある羊の部屋に置きました。そしてそこに腰を下ろすと、ウィルバーのことを考えたり、ウィルバーの声を聞いたり、ウィルバーのしぐさを眺めたりしながら、昼下がりの長い時間をおとなしく過ごしていたのです。羊はすぐにファーンになじみ、警戒しなくなりました。羊と一緒に暮らしていたガチョウも同じでした。なやの動物はみんな、ものしずかで優しいファーンに気をゆるすようになりました。ザッカーマンさんは、ファーンがウィルバーの囲いの中に入ったり、ウィルバーを外につれだしたりするのは、許してくれませんでした。けれども、いすに腰かけてウィルバーをながめるのは、すきなだけよっていてよかったのです。ファーンは、ウィルバーのそばにいられるだけで満足でしたし、ウィルバーも、自分のへやのすぐ外にファーンが座っているだけで幸せでした。でも、散歩にでかけたり、乳母車に乗ったり、水遊びをしたりする楽しみはありませんでした。)
One afternoon in June, when Wilbur was almost two months old, he wandered out into his small yard outside the barn. Fern had not arrived for her usual visit. Wilbur stood in the sun feeling lonely and bored.
(ウィルバーが生まれてもうすぐ2ヶ月になるという、ある6月の朝のことです。ウィルバーは床下から、外にある小さな囲いの中にでていきました。いつもくるファーンは、まだ顔を見せません。一人ぼっちで退屈してきたウィルバーは、日の光をあびながら、じっと立っていました。「ここには、あんまりやることがないんだよな。」と思いながら、えさ箱のほうに歩いていって、アヒルご飯がひょっとして残っていないかどうか、匂いをかぎました。ジャガイモの皮がちょっぴりのこっていたので、それを食べました。背中がかゆくなってきたので、へいにもたれかかって、板に背中をこすり付けました。それにもあきると、ウィルバーは床下の部屋にもどって、堆肥の山に腰を下ろしました。眠る気にもなれないし、穴を掘る気にも慣れません。かといって、じっと立っているのにもあきたし、横になるのにもあきていました。)
"There's never anything to do around here," he thought. He walked slowly to his food trough and sniffed to see if anything had been overlooked at lunch. He found a small strip of potato skin and ate it. His back itched, climbed to the top of the manure pile, and sat down. He didn't feel like going to sleep, he didn't feel like digging, he was tired of standing still, tired of lying down. "I'm less than two months old and I'm tired of living," he said. He walked out to the yard again.
(「まだうまれて2ヶ月にもならないのに、僕はもう生きているのにうんざりしちゃった。」そういうとウィルバーは、また外のかこいに出て行きました。)
"When I'm out here," he said, "there's no place to go but in. When I'm indoors, there's no place to go but out in the yard."
(「外のかこいに出れば、次は部屋の中に行くしか、いくところがないだろ。部屋の中に入れば、あとは外の囲いしか、行くところがないんだよな。」と、ウィルバーはひとり言をいいました。)
"That's when you're wrong, my friend, my friend," said a voice.
(「ちがう、ちがう、ちがう。」と、声がしました。)
Wilbur looked through the fence and saw the goose standing there.
(へいの向こうを見ると、そこにはガチョウのおばさんが立っていました。)
"You don't have to stay in that dirty-little dirty-tittle yard," said the gooes, who talked rather fast. "One of the boards is loose. Push on it, push-push-push on it, and come on out!"
(「そんなうすぎたない、ちっぽけな、ちっぽけな、ちっぽけなかこいにいることないのよ。」と、ガチョウのおばさんは早口で言いました。「へいのかこいの板が1枚、ぐらぐらになってるのよ。そこを、おして、おして、おして、外にでといで!」)
"What?" said Wilbur. "Say it slower!"
(「なに?もう少しゆっくりいってよ!」と、ウィルバーはいいました。)
"At-at-at, at the risk of repeating myself," said the goose, "I suggest that you come on out. It's wonderful out here."
(「しょうが、しょうが、しょうがないわねえ。でておいでって、いったのよ。外はすてきだよ。」)
"Did you say a board was loose?"
(「ぐらぐらの板があるって、いったの?」)
"That I did, that I did," said the goose.
(「そう、そう、そうよ。」)
Wilbur walked up to the fence and saw that the goose was right--one board was loose. He put his head down, shut his eyes, and pushed. The board gave way. In a minute he had squeezed through the fence and was standing in the long grass outside his yard. The goose chuckled.
(へいのそばまでいってみると、ガチョウのおばさんの言ったとおりだといいうことが分かりました。へい板の1つが、ゆるくなっていました。ウィルバーは頭を下げて、目をとじると、ぐいっと押しました。板の片方がはずれました。そこをくぐった向こうには、草が高くおいしげっていました。ウィルバーは外にでたのです。ガチョウが、くすくす笑いました。)
"How does it feel to be free?" she asked.
(「自由になった気分はどう?」ガチョウのおばさんがたずねました。)
"I like it," said Wilbur. "That is, I guess I like it. Actually, Wilbur felt queer to be outside his fence, with nothing between him and the big world.
(「いいね。」と、ウィルバーはいいました。「たぶん、いいんだと思うんだけど」へいの外にはでたものの、ウィルバーは少し面食らっていました。なにしろ、広い世界と自分とのあいだには板塀も何もないんです。)
"Where do you think I'd better go?"
(「ぼく、どっちへいったらいいんだろう?」)
"Anywhere you like, anywhere you like," said the goose. "Go down through the orchard, root up the sod! Go down through the garden, dig up the radishes! Root up everything! Eat grass! Look for corn! Look for oats! Run all over! Skip and dance, jump and prance! Go down through the orchard and stroll in the woods! The world is a wonderful place when you're young."
(「どこでも、どこでも、おすきなところへ」と、ガチョウのおばさんは言いました。「果樹園に行って、芝土をほってもいい!畑にいって、アカカブをほってもいい!あっちこっちほりかえしたっていいわ!草を食べてもいい!さがせばトウモロコシが見つかるわ!カラス麦も見つかるわ!そこらじゅう走り回りなさいよ!スキップして、おどって、ジャンプして、はねて!果樹園をぬければ、森だって散歩できるわ!若いときなら、この世界はすばらしいものよ。」)
"I can see that," replied Wilbur. He gave a jump in the air, twirled, run a few steps, stopped, looked all around, sniffed the the smells of afternoon, and then set off walking down through the orchard. Pausing in the shade of an apple tree, he put his strong snout into the ground and began pushing, digging, and rooting. He felt very happy. He had plowed up quite a piece of ground before anyone noticed him. Mrs.Zuckerman was the first to see him. She saw him from the kitchen window, and she immediately shouted for the men.
(「そうだろうね。」ウィルバーはそういって、ぴょんととびあがり、くるっとまわり、ちょこちょこっと走り、立ち止まり、あたりを見まわし、昼下がりのにおいをかぎ、それから果樹園のなかを歩き始めました。1本のリンゴの木の下で立ち止まると、丈夫な鼻を地面につっこんで、ほじくりかえしました。なんてすてきなんでしょう!だれも気づかないでいるあいだに、ウィルバーは、あちこちをさんざん掘り返していました。最初に気づいたのは、ザッカーマンのおばさんでした。台所のまどからウィルバーが見えたとたん、大声で叫びました。)
"Ho-mer!" she cried. "Pig's out! Lurvy! Pig's out! Homer! Lurvy! Pig's out. He's down there under that apple tree."
(「ホーマー!ブタが外にでちゃったわよ!ラーヴィー!ブタが逃げたのよ!ホーマー!ラーヴィー!ブタが逃げたわ!リンゴの木の下よ!」)
"Now the trouble starts," through Wilbur. "Now I'll catch it."
(「たいへんだ。つかまっちゃうぞ!」ウィルバーは思いました。)
The goose head the racket and she, too, started hollering. "Run-run-run downhill, make for the woods, the woods!" she shouted to Wilbur. "They'll never-never-never catch you in the woods."
(さわぎを聞きつけたガチョウのおばさんも、大声でウィルバーにどなりました。「坂を下って、走って、走って、走って!森へ、森へ、森へ!森の中に入れば、絶対、絶対、絶対つかまらないからね!」)
The cocker spaniel heard the commotion and he ran out from the barn to join the chase. Mr.Zuckerman heard, and he came out of the machine shed where he was mending a tool. Lurvy, the hired man, heard the noise and came up from the asparagus patch where he was pulling weeds. Everybody walked toward Wilbur and Wilbur didn't know what to do. The woods seemed a long way off, and anyway, he had never been down there in the woods and wasn't sure he would like it.
(コッカースパニエル犬が、ごたごたをききつけて納屋から出てくると、追っ手に加わりました。機械小屋で道具を修理していたザッカーマンのおじさんが、声をきいてでてきました。アスパラガスの畑で草とりをしていた雇い人のラーヴィーも、声を聞きつけてでてきました。みんなが自分のほうへやってくるので、ウィルバーはとまどいました。森はずいぶん遠そうでしたし、1度もいったことがないので、素敵なところかどうかも、わかりません。)
"Get around behind him, Lurvy," said Mr.Zuckerman, "and drive him toward the barn! And take it easy--don't rush him! I'll go and get a bucket of slops."
(「ラーヴィー、うしろへまわってくれ。」ザッカーマンのおじさんが言いました。「納屋のほうへ追い込むんだ!そろそろいけよ。おどかさないでな。わたしは残飯をとってくる。」)
The news of Wilbur's escape spread repidly among the animals on the place. Whenever any creature broke loose on Zuckerman's farm, the event was of great interest to the others. The goose shouted to the nearest cow that Wilbur was free, and soon all the cows knew. Then one of the cows told one of the sheep, and soon all the sheep knew. The lambs learned about it from their mothers. The horses, in their stalls in the barn, pricked up their ears when they heard the goose hollering; and soon the hotses had caught on to what was happening. "Wilbur's out," they said. Every animal sirred and lifted its head and became excited to know that one of his friends had got free and was no konger penned up or tied fast.
(ウィルバーが逃げ出したというニュースは、農場の動物のあいだに、ぱっと広がりました。ザッカーマン農場では、誰かの脱出は、みんなの興味の的でした。ガチョウのおばさんが、すぐ近くにいた雌牛に、ウィルバーが外に出たと大声で告げると、ニュースはたちまち雌牛全員に伝わりました。つぎに、雌牛が1匹の羊に話すと、ニュースはたちまち羊全員に伝わりました。子羊たちは、お母さんからニュースを聞きました。納屋の仕切りの中にいた馬たちは、ガチョウが叫んだときに耳をそばだてて、何が起こったかをたちまち知りました。「ウィルバーが逃げたんだ!」と、馬はいいました。仲間が逃げ出して、もう囲いに閉じ込められたり、綱につながれたりしていないのを知ると、動物たちはみなじっとしていられず、頭を持ち上げてもぞもぞ動き、胸をドキドキさせるのでした。)
Wilbur didn't know what to do or which way to run. It seemed as though everybody was after him. "If this is waht it's like to be free," he thought, "I believe I'd rather be penned up in my own yard."
(ウィルバーは、どうしていいかも分からなければ、どっちににげたらいいのかも知りませんでした。誰かもかれもが追いかけ来るような気がしました。「自由になるっていうのがこういうことなら、納屋の前の囲いの中にいたほうがよかったな。」と、ウィルバーは思いました。)
The cocker spaniel was sneaking up on him from one side, Lurvy the hired man was sneaking up on him from the other side. Mrs.Zuckerman stood ready to head him off if he started for the garden, and now Mr.Zuckerman was coming doen toward him carrying a pail. "This is really awful," thought Wilbur. "Why doesn't Fern come?" He began to cry.
(コッカースパニエル犬が、片側からそろそろとウィルバーに近づいてきました。雇い人のラーヴィーが、反対側からそろそろとウィルバーに近づいてきました。ザッカーマンのおばさんは、畑の前で通せんぼをしていました。そしてザッカーマンのおじさんも、残飯の入ったバケツを持って近づいてきました。「ああ、いやんなっちゃうな。ファーンはどうしてきてくれないのかな?」ウィルバーは、泣き声をあげました。)
The goose took command and began to give orders.
(ガチョウのおばさんが、先にたって命令しました。)
"Don't just stand there, Wilbur! Dodge about, dodge about!" cried the goose. "Skip around, run toward me, slip in and out, in and out, in and out! Make for the woods! Twist and turn!"
(「つっ立ってちゃだめよ、ウィルバー!かわして、かわして!」ガチョウは叫びました。「ぴょんととんで、こっちへくるのよ。すりぬけて、すりぬけて、すりぬけて!森へ行きなさい!くるっと向きを変えるのよ!」)
The cocker spaniel sprang for Wilbur's hind leg. Wilbur jumped and ran. Lurvy reached out and grabbed. Mrs.Zuckerman screamed at Lurvy. The goose cheered for Wilbur. Wilbur dodged between Lurvy's legs. Lurvy missed Wilbur and grabbed the spaniel instead. "Nicely done, nicely done!" cried the goose. "Try it again, try it again!"
(コッカースパニエル犬が、ウィルバーの後足にとびかかりました。ウィルバーはぴょんととびあがって、逃げました。ラーヴィーが手を伸ばして、ウィルバーを捕まえようとしました。ザッカーマンのおばさんが、かなきり声をあげました。ガチョウのおばさんがウィルバーに声援を送りました。ウィルバーは、ラーヴィーの足のあいだをすり抜けました。ラーヴィーはウィルバーを捕まえそこね、かわりにコッカースパニエル犬をつかんでしまいました。「その調子、その調子!」ガチョウのおばさんがさけびました。「もういちど、もういちど!」)
"Run downhill!" suggested the cows.
(「坂をくだるのよ!」雌牛たちが言いました。)
"Run toward me!" yelled the gander.
(「こっちへ逃げて来い!」がちょうのおじさんがどなりました。)
"Run uphill!" cried the sheep.
(「坂をのぼりなさい!」羊たちが叫びました。)
"Turn and twist!" honked the goose.
(「くるっと体をひねって!」ガチョウのおばさんががなりたてました。)
"Jump and dance!" said the rooster.
(「ジャンプしてはねるんだ!」おんどりが言いました。)
"Look out for Lurvy!" called the cows.
(「ラーヴィーに気をつけて!」雌牛たちが言いました。)
"Look out for Zuckerman!" yelled the gander.
(「ザッカーマンに気をつけるんだ!」ガチョウのおじさんが叫びました。)
"Watch out for the dog!" cried the sheep.
(「犬に注意して!」羊たちがどなりました。)
"Listen to me, listen to me!" screamed the goose.
(「あたしのいうとおりに、いうとおりに!」ガチョウのおばさんが声を張り上げました。)
Poor Wilbur was dazed and frightened by this hullabaloo. He didn't like being the center of all this fuss. He tried to follow the instructions his friends were giving him, but he couldn't run downhill and uphill at the same time, and he couldn't turn and twist when he was jumping and dancing and he was crying so hard he could barely see anything that was happening. After all, Wilbur was a very young pig--not much more than a baby, really. He wished Fern were thereto take him in her arms and comfort him. When he looked up and saw Mr.Zuckerman standing quite close to him, holding a pail of warm slope, he felt relieved. He lifted his mose and sniffed. The smell was delicious--warm milk, potato skins, wheat middlings, Kellogg's Corn Flakes, and a popover left from the Zuckermans' breakfast.
(やかましいさわぎに、あわれなウィルバーはすっかりのぼせあがり、怖くなってしまいました。自分のことで、誰もが大騒ぎしているのです。仲間の言うとおりにしようと思っても、坂を下るのと坂をのぼるのを同時にすることはできません。ジャンプしてはねているときに、くるっと体をひねることもできません。それに、ウィルバーは自分でも大声を出していたので、もう何が起こっているのか、よく分からなくなっていました。なんといっても、ウィルバーはまだ赤ちゃんといったっていいくらい、本当に小さいブタだったんですからね。ああ、ファーンがここにいて、だっこしてくれたらいいのになあ。ふと顔をあげると、ザッカーマンのおじさんが、あたたかい残飯の入ったバケツを持って、すぐそばに立っていました。ウィルバーは、ほっとして鼻をもちあげ、クンクンとにおいをかぎました。美味しそうなにおいがします。あったかいミルクと、ジャガイモの皮と、フスマ飼料と、ケロッグのコーンフレークと、ザッカーマンさんたちが朝ごはんのときに食べ残したパンのにおいです。)
"Come, pig!" said Mr.Zuckerman, tapping the pail. "Come pig!"
(「おいで!」と、ザッカーマンのおじさんが、バケツをトントンたたきながらいいました。「さあ、おいで!」)
Wilbur took a step toward the pail.
(ウィルバーは、バケツのほうに1歩足をふみだしました。)
"No-no-no!" said the goose. "It's the old pail trick, Wilbur. Don't fall for it, don't fall it! He's trying to lure you back into captivity-ivity. He's appealing to you stomach."
(「だめ、だめ、だめ!餌でだまそうっていう手なのよ、ウィルバー。だまされないで、だまされないで!えさでさそって、またかこいにとじこめるつもりなのさ。ひっかかっちゃだめだよ。」ガチョウのおばさんがいいました。)
Wilbur didn't care. the food smelled appetizing. He took another step toward the pail.
(ウィルバーは、もうそれでもかまいませんでした。なにしろバケツのなかからは、とてもいいにおいがしていたのです。そこれ、もう1歩バケツに近づきました。)
"Pig, pig!" said Mr.Zuckerman in a kind voice, and began walking slowly toward the barnyard, looking all about him innocently, as if he didn't know that a little white pig was following along behind him.
(「よしよし、ブタくん!」ザッカーマンのおじさんは、やさしい声でよびかけると、ゆっくりと納屋のまえのかこいのほうに歩いていきました。まるで、小さな白いブタが後ろからうしろからついてくるかどうかなど、まったく気にかけていない様子で、まわりを見渡しながら。)
"You'll be sorry-sorry-sorry," called the goose.
(「後悔するよ、後悔、後悔。」ガチョウのおばさんが大声で言いました。)
Wilbur didn't care. He kept walking toward the pail of slops.
(ウィルバーは、それでもかまいませんでした。残飯バケツのあとについて、どんどん歩いていきました。)
"You'll miss your freedom," honked the goose. "An hour of hreedom is worth a barrel of slops."
(「自由がなくなっちゃうんだよ。」ガチョウのおばさんが言いました。「自由な1時間は、バケツ1杯の残飯に負けないくらいすてきなのにさ。」)
Wilbur didn't care.
(ウィルバーはそれでもかまいませんでした。)
When Mr.Zuckerman reached the pigpen, he climbed over the fence and poured the slops into the trough. Then he pulled the loose board away from the fence, so that there was a wide hole for Wilbur to walk through.
(ザッカーマンのおじさんは、ブタのかこいまでやってくると、へいをまたいで、バケツの中の残飯をえさ箱にいれました。それから、ウィルバーをなかに入れるために、ぐらぐらになってぶらさがっていた板をへいからはずしました。)
"Reconsider, reconsider!" cried the goose.
(「考え直して、考え直して!」ガチョウのおばさんがさけびました。)
Wilbur paid no attention. He stepped through the fence into his yard. He walked to the trough and took a long drink of slops, sucking in the milk hungrily and chewing the popover. It was good to be home again.
(ウィルバーは聞いていませんでした。へいにあいた穴から中に入り、えさ箱に近より、ズズズッと残飯をすすり、ミルクを飲み、パンをかみました。家に帰ってこられて、ほっとしていました。)
While Wilbur ate, Lurvy fetched a hammer and some 8-penny nails and nailed the board in place. Then he and Mr.Zuckerman leaned lazily on the fence and Mr.Zuckerman scratched Wilbur's back with a stick.
(ウィルバーが食べているあいだに、ラーヴィーがかなづちと釘を持っていき、へいに板を打ち付けました。それからザッカーマンのおじさんは、ラーヴィーと一緒にへいにゆったりとよりかかり、棒でウィルバーの背中をかいてやりました。)
"He's quite a pig," said Lurvy.
(「こいつはなかなかのブタですね。」と、ラーヴィーはいいました。)
"Yes, he'll make a good pig," said Mr.Zuckerman.
(「そうなだ。いいブタになるぞ。」と、ザッカーマンのおじさんはいいました。)
Wilbur heard the words of praise. He felt the warm milk inside his stomach. He felt the pleasant rubbing of the stick along his itchy back. He felt peaceful and hapy and sleepy. This had been a tiring afternoon. It was still only four o'clock but Wilbur was ready for bed.
(ほめ言葉がウィルバーの耳に入りました。おなかの中には温かいミルクが流れ込んでいました。背中のかゆいとこを棒でかいてもらって、いい気持ちでした。穏やかで、しあわせで、ねむたくなってきました。なんといっても、午後の冒険でウィルバーはぐったり疲れていました。まだ4時にしかなっていませんでしたが、ウィルバーはもう眠かったのです。)
"I'm really too young to go out into the world alone," he thought as he lay down.
(「僕はまだ、ひとりで世界に出て行くには、小さすぎるんだな。」横になりながら、ウィルバーはそう思っていました。)
英文のみです。
日本語訳のみです。
Charlotte's Web 4
( 3.にげろ!)
The baran was very large. It was very old. It smelled of hey and it smelled of tired horses and the wonderful sweet breath of patient cows. It often had a sort of peaceful smell--as though nothing bad could happen ever again in the world. It smelled of grain and of harness dressing and of axle grease and of rubber boots and of new rope. And whenever the cat was given a fish-head to eat, the barn would smell of fish. But mostly it smelled of hay, for there was always hay in the great loft up overhead. And there was always hay being pitched down to the cows and the horses and the sheep.
(ウィルバーが暮らすことになったのは、とても古く大きな納屋で、干草と堆肥のにおいがしました。くたびれた馬のあせのにおいと、しんぼう強い雌牛のあまやかな息のにおいもしました。たいていは、安らかで平和なにおいに満ちていたので、世の中にはもう2度と悪いことなど起こらないように思えました。それに、穀物や、馬具をみがく油や、車軸につける機械油、ゴム長ぐつや新しいロープのにおいもしていました。ネコが魚の頭をもらうと、納屋は魚くさくもなりました。でも、いちばん強くにおうのは、なんといっても干草でした。というのも、納屋の2階には、干草がどっさりつんであったのです。その干草は、下にいる牝牛や馬や羊に必要とあれば、いつでも上から投げ下ろされるのでした。)
The barn was pleasantly warm in winter when the animals spent most of their time indoors, and it was pleasantly cool in summer when the big doors stood wide open to the breeze. The barn had stalls on the main floor for the work horses, tie-ups on the main floor for the cows, a sheepfold down below for the sheep, a pigpen down below for Wilbur, and it was full of all sorts of things that you find in barns: ladders, grindstones, pitch forks, monkey wrenches, scythes, lawn mowers, snow shovels, ax handles, milk pails, water buckets, empty grain sacks, and rusty rat traps. It was the kind of barn that swallows like to build their neses in. It was the kind of barn that children like to play in. And the whole thing was owned by Fern's uncle, Mr.Homer L.Zuckerman.
(動物たちがほとんどの時間を屋内で過ごす冬でも、納屋の中は暖かでした。そして夏には、大きなとびらがあけはなたれて風が入ってくるので、なかなか涼しいのでした。納屋の1階には、農耕馬や牝牛のための部屋があり、床下には羊の部屋やウィルバーのためのブタの部屋がありました。それに、この納屋の中には、はしごだとか、丸砥石だとか、くまでだとか、モンキースパナだとか、かまだとか、芝刈り機だとか、雪かきシャベルだとか、斧の枝とか、ミルク容器だとか、バケツだとか、からっぽの穀物袋だとか、さびたネズミとりだとか、ふつうの納屋にありそうなものは、なんでもありました。それに、ここは、ツバメが巣を作りたいと思うような納屋でした。そして子供が遊びたいと思うような、そんな納屋でもありました。そして、納屋にあるものはみんな、ホーマー・L・ザッカーマンという名前の、ファーンおおじさんのものでした。)
Wilbur's new home was in the lower part of the barn, directly underneath ihe cows. MrZuckerman knew that a manure pile is a good place to keep a young pig. Pigs need warmth, and it was warm and comfortable down there in the barn cellar on the south side.
(ウィルバーの新しい部屋は、牝牛たちの部屋のすぐ下にありました。ザッカーマンさんは、小さい子ブタを飼うには、堆肥の山がちょうどいいことを知っていたのです。ブタは暖かいのが好きでしたし、納屋の床下の南側は、ぬくぬくとあたたかったのです。)
Fern came slmost every day to visit him. She found an old milking stool that had been discarded, and she placed the stool in the sheepfold next to Wilbur's pen. Here she sat quietly during the long afternoons, thinking and listening and watching Wilbur. The sheep soon got to know her and trust her. So did the geese, who lived with the sheep. All the animals trusted her, she was so quiet and friendly. Mr.Zuckerman did not allow her to take Wilbur out, and he did not allow her to get into the pigpen. But to hold Fern that she could sit on the stool and watch Wilbur as long as she wanted to. It made her happy just to be near the pig, and it made Wilbur happy to know that she was sitting there, right outside his pen. But he never had any fun--no walks, no rides, no swaims.
(ファーンは毎日のようにウィルバーに会いに行きました。父絞りの時に使ういすが捨ててあったので、ファーンはそのいすをウィルバーの部屋の隣にある羊の部屋に置きました。そしてそこに腰を下ろすと、ウィルバーのことを考えたり、ウィルバーの声を聞いたり、ウィルバーのしぐさを眺めたりしながら、昼下がりの長い時間をおとなしく過ごしていたのです。羊はすぐにファーンになじみ、警戒しなくなりました。羊と一緒に暮らしていたガチョウも同じでした。なやの動物はみんな、ものしずかで優しいファーンに気をゆるすようになりました。ザッカーマンさんは、ファーンがウィルバーの囲いの中に入ったり、ウィルバーを外につれだしたりするのは、許してくれませんでした。けれども、いすに腰かけてウィルバーをながめるのは、すきなだけよっていてよかったのです。ファーンは、ウィルバーのそばにいられるだけで満足でしたし、ウィルバーも、自分のへやのすぐ外にファーンが座っているだけで幸せでした。でも、散歩にでかけたり、乳母車に乗ったり、水遊びをしたりする楽しみはありませんでした。)
One afternoon in June, when Wilbur was almost two months old, he wandered out into his small yard outside the barn. Fern had not arrived for her usual visit. Wilbur stood in the sun feeling lonely and bored.
(ウィルバーが生まれてもうすぐ2ヶ月になるという、ある6月の朝のことです。ウィルバーは床下から、外にある小さな囲いの中にでていきました。いつもくるファーンは、まだ顔を見せません。一人ぼっちで退屈してきたウィルバーは、日の光をあびながら、じっと立っていました。「ここには、あんまりやることがないんだよな。」と思いながら、えさ箱のほうに歩いていって、アヒルご飯がひょっとして残っていないかどうか、匂いをかぎました。ジャガイモの皮がちょっぴりのこっていたので、それを食べました。背中がかゆくなってきたので、へいにもたれかかって、板に背中をこすり付けました。それにもあきると、ウィルバーは床下の部屋にもどって、堆肥の山に腰を下ろしました。眠る気にもなれないし、穴を掘る気にも慣れません。かといって、じっと立っているのにもあきたし、横になるのにもあきていました。)
"There's never anything to do around here," he thought. He walked slowly to his food trough and sniffed to see if anything had been overlooked at lunch. He found a small strip of potato skin and ate it. His back itched, climbed to the top of the manure pile, and sat down. He didn't feel like going to sleep, he didn't feel like digging, he was tired of standing still, tired of lying down. "I'm less than two months old and I'm tired of living," he said. He walked out to the yard again.
(「まだうまれて2ヶ月にもならないのに、僕はもう生きているのにうんざりしちゃった。」そういうとウィルバーは、また外のかこいに出て行きました。)
"When I'm out here," he said, "there's no place to go but in. When I'm indoors, there's no place to go but out in the yard."
(「外のかこいに出れば、次は部屋の中に行くしか、いくところがないだろ。部屋の中に入れば、あとは外の囲いしか、行くところがないんだよな。」と、ウィルバーはひとり言をいいました。)
"That's when you're wrong, my friend, my friend," said a voice.
(「ちがう、ちがう、ちがう。」と、声がしました。)
Wilbur looked through the fence and saw the goose standing there.
(へいの向こうを見ると、そこにはガチョウのおばさんが立っていました。)
"You don't have to stay in that dirty-little dirty-tittle yard," said the gooes, who talked rather fast. "One of the boards is loose. Push on it, push-push-push on it, and come on out!"
(「そんなうすぎたない、ちっぽけな、ちっぽけな、ちっぽけなかこいにいることないのよ。」と、ガチョウのおばさんは早口で言いました。「へいのかこいの板が1枚、ぐらぐらになってるのよ。そこを、おして、おして、おして、外にでといで!」)
"What?" said Wilbur. "Say it slower!"
(「なに?もう少しゆっくりいってよ!」と、ウィルバーはいいました。)
"At-at-at, at the risk of repeating myself," said the goose, "I suggest that you come on out. It's wonderful out here."
(「しょうが、しょうが、しょうがないわねえ。でておいでって、いったのよ。外はすてきだよ。」)
"Did you say a board was loose?"
(「ぐらぐらの板があるって、いったの?」)
"That I did, that I did," said the goose.
(「そう、そう、そうよ。」)
Wilbur walked up to the fence and saw that the goose was right--one board was loose. He put his head down, shut his eyes, and pushed. The board gave way. In a minute he had squeezed through the fence and was standing in the long grass outside his yard. The goose chuckled.
(へいのそばまでいってみると、ガチョウのおばさんの言ったとおりだといいうことが分かりました。へい板の1つが、ゆるくなっていました。ウィルバーは頭を下げて、目をとじると、ぐいっと押しました。板の片方がはずれました。そこをくぐった向こうには、草が高くおいしげっていました。ウィルバーは外にでたのです。ガチョウが、くすくす笑いました。)
"How does it feel to be free?" she asked.
(「自由になった気分はどう?」ガチョウのおばさんがたずねました。)
"I like it," said Wilbur. "That is, I guess I like it. Actually, Wilbur felt queer to be outside his fence, with nothing between him and the big world.
(「いいね。」と、ウィルバーはいいました。「たぶん、いいんだと思うんだけど」へいの外にはでたものの、ウィルバーは少し面食らっていました。なにしろ、広い世界と自分とのあいだには板塀も何もないんです。)
"Where do you think I'd better go?"
(「ぼく、どっちへいったらいいんだろう?」)
"Anywhere you like, anywhere you like," said the goose. "Go down through the orchard, root up the sod! Go down through the garden, dig up the radishes! Root up everything! Eat grass! Look for corn! Look for oats! Run all over! Skip and dance, jump and prance! Go down through the orchard and stroll in the woods! The world is a wonderful place when you're young."
(「どこでも、どこでも、おすきなところへ」と、ガチョウのおばさんは言いました。「果樹園に行って、芝土をほってもいい!畑にいって、アカカブをほってもいい!あっちこっちほりかえしたっていいわ!草を食べてもいい!さがせばトウモロコシが見つかるわ!カラス麦も見つかるわ!そこらじゅう走り回りなさいよ!スキップして、おどって、ジャンプして、はねて!果樹園をぬければ、森だって散歩できるわ!若いときなら、この世界はすばらしいものよ。」)
"I can see that," replied Wilbur. He gave a jump in the air, twirled, run a few steps, stopped, looked all around, sniffed the the smells of afternoon, and then set off walking down through the orchard. Pausing in the shade of an apple tree, he put his strong snout into the ground and began pushing, digging, and rooting. He felt very happy. He had plowed up quite a piece of ground before anyone noticed him. Mrs.Zuckerman was the first to see him. She saw him from the kitchen window, and she immediately shouted for the men.
(「そうだろうね。」ウィルバーはそういって、ぴょんととびあがり、くるっとまわり、ちょこちょこっと走り、立ち止まり、あたりを見まわし、昼下がりのにおいをかぎ、それから果樹園のなかを歩き始めました。1本のリンゴの木の下で立ち止まると、丈夫な鼻を地面につっこんで、ほじくりかえしました。なんてすてきなんでしょう!だれも気づかないでいるあいだに、ウィルバーは、あちこちをさんざん掘り返していました。最初に気づいたのは、ザッカーマンのおばさんでした。台所のまどからウィルバーが見えたとたん、大声で叫びました。)
"Ho-mer!" she cried. "Pig's out! Lurvy! Pig's out! Homer! Lurvy! Pig's out. He's down there under that apple tree."
(「ホーマー!ブタが外にでちゃったわよ!ラーヴィー!ブタが逃げたのよ!ホーマー!ラーヴィー!ブタが逃げたわ!リンゴの木の下よ!」)
"Now the trouble starts," through Wilbur. "Now I'll catch it."
(「たいへんだ。つかまっちゃうぞ!」ウィルバーは思いました。)
The goose head the racket and she, too, started hollering. "Run-run-run downhill, make for the woods, the woods!" she shouted to Wilbur. "They'll never-never-never catch you in the woods."
(さわぎを聞きつけたガチョウのおばさんも、大声でウィルバーにどなりました。「坂を下って、走って、走って、走って!森へ、森へ、森へ!森の中に入れば、絶対、絶対、絶対つかまらないからね!」)
The cocker spaniel heard the commotion and he ran out from the barn to join the chase. Mr.Zuckerman heard, and he came out of the machine shed where he was mending a tool. Lurvy, the hired man, heard the noise and came up from the asparagus patch where he was pulling weeds. Everybody walked toward Wilbur and Wilbur didn't know what to do. The woods seemed a long way off, and anyway, he had never been down there in the woods and wasn't sure he would like it.
(コッカースパニエル犬が、ごたごたをききつけて納屋から出てくると、追っ手に加わりました。機械小屋で道具を修理していたザッカーマンのおじさんが、声をきいてでてきました。アスパラガスの畑で草とりをしていた雇い人のラーヴィーも、声を聞きつけてでてきました。みんなが自分のほうへやってくるので、ウィルバーはとまどいました。森はずいぶん遠そうでしたし、1度もいったことがないので、素敵なところかどうかも、わかりません。)
"Get around behind him, Lurvy," said Mr.Zuckerman, "and drive him toward the barn! And take it easy--don't rush him! I'll go and get a bucket of slops."
(「ラーヴィー、うしろへまわってくれ。」ザッカーマンのおじさんが言いました。「納屋のほうへ追い込むんだ!そろそろいけよ。おどかさないでな。わたしは残飯をとってくる。」)
The news of Wilbur's escape spread repidly among the animals on the place. Whenever any creature broke loose on Zuckerman's farm, the event was of great interest to the others. The goose shouted to the nearest cow that Wilbur was free, and soon all the cows knew. Then one of the cows told one of the sheep, and soon all the sheep knew. The lambs learned about it from their mothers. The horses, in their stalls in the barn, pricked up their ears when they heard the goose hollering; and soon the hotses had caught on to what was happening. "Wilbur's out," they said. Every animal sirred and lifted its head and became excited to know that one of his friends had got free and was no konger penned up or tied fast.
(ウィルバーが逃げ出したというニュースは、農場の動物のあいだに、ぱっと広がりました。ザッカーマン農場では、誰かの脱出は、みんなの興味の的でした。ガチョウのおばさんが、すぐ近くにいた雌牛に、ウィルバーが外に出たと大声で告げると、ニュースはたちまち雌牛全員に伝わりました。つぎに、雌牛が1匹の羊に話すと、ニュースはたちまち羊全員に伝わりました。子羊たちは、お母さんからニュースを聞きました。納屋の仕切りの中にいた馬たちは、ガチョウが叫んだときに耳をそばだてて、何が起こったかをたちまち知りました。「ウィルバーが逃げたんだ!」と、馬はいいました。仲間が逃げ出して、もう囲いに閉じ込められたり、綱につながれたりしていないのを知ると、動物たちはみなじっとしていられず、頭を持ち上げてもぞもぞ動き、胸をドキドキさせるのでした。)
Wilbur didn't know what to do or which way to run. It seemed as though everybody was after him. "If this is waht it's like to be free," he thought, "I believe I'd rather be penned up in my own yard."
(ウィルバーは、どうしていいかも分からなければ、どっちににげたらいいのかも知りませんでした。誰かもかれもが追いかけ来るような気がしました。「自由になるっていうのがこういうことなら、納屋の前の囲いの中にいたほうがよかったな。」と、ウィルバーは思いました。)
The cocker spaniel was sneaking up on him from one side, Lurvy the hired man was sneaking up on him from the other side. Mrs.Zuckerman stood ready to head him off if he started for the garden, and now Mr.Zuckerman was coming doen toward him carrying a pail. "This is really awful," thought Wilbur. "Why doesn't Fern come?" He began to cry.
(コッカースパニエル犬が、片側からそろそろとウィルバーに近づいてきました。雇い人のラーヴィーが、反対側からそろそろとウィルバーに近づいてきました。ザッカーマンのおばさんは、畑の前で通せんぼをしていました。そしてザッカーマンのおじさんも、残飯の入ったバケツを持って近づいてきました。「ああ、いやんなっちゃうな。ファーンはどうしてきてくれないのかな?」ウィルバーは、泣き声をあげました。)
The goose took command and began to give orders.
(ガチョウのおばさんが、先にたって命令しました。)
"Don't just stand there, Wilbur! Dodge about, dodge about!" cried the goose. "Skip around, run toward me, slip in and out, in and out, in and out! Make for the woods! Twist and turn!"
(「つっ立ってちゃだめよ、ウィルバー!かわして、かわして!」ガチョウは叫びました。「ぴょんととんで、こっちへくるのよ。すりぬけて、すりぬけて、すりぬけて!森へ行きなさい!くるっと向きを変えるのよ!」)
The cocker spaniel sprang for Wilbur's hind leg. Wilbur jumped and ran. Lurvy reached out and grabbed. Mrs.Zuckerman screamed at Lurvy. The goose cheered for Wilbur. Wilbur dodged between Lurvy's legs. Lurvy missed Wilbur and grabbed the spaniel instead. "Nicely done, nicely done!" cried the goose. "Try it again, try it again!"
(コッカースパニエル犬が、ウィルバーの後足にとびかかりました。ウィルバーはぴょんととびあがって、逃げました。ラーヴィーが手を伸ばして、ウィルバーを捕まえようとしました。ザッカーマンのおばさんが、かなきり声をあげました。ガチョウのおばさんがウィルバーに声援を送りました。ウィルバーは、ラーヴィーの足のあいだをすり抜けました。ラーヴィーはウィルバーを捕まえそこね、かわりにコッカースパニエル犬をつかんでしまいました。「その調子、その調子!」ガチョウのおばさんがさけびました。「もういちど、もういちど!」)
"Run downhill!" suggested the cows.
(「坂をくだるのよ!」雌牛たちが言いました。)
"Run toward me!" yelled the gander.
(「こっちへ逃げて来い!」がちょうのおじさんがどなりました。)
"Run uphill!" cried the sheep.
(「坂をのぼりなさい!」羊たちが叫びました。)
"Turn and twist!" honked the goose.
(「くるっと体をひねって!」ガチョウのおばさんががなりたてました。)
"Jump and dance!" said the rooster.
(「ジャンプしてはねるんだ!」おんどりが言いました。)
"Look out for Lurvy!" called the cows.
(「ラーヴィーに気をつけて!」雌牛たちが言いました。)
"Look out for Zuckerman!" yelled the gander.
(「ザッカーマンに気をつけるんだ!」ガチョウのおじさんが叫びました。)
"Watch out for the dog!" cried the sheep.
(「犬に注意して!」羊たちがどなりました。)
"Listen to me, listen to me!" screamed the goose.
(「あたしのいうとおりに、いうとおりに!」ガチョウのおばさんが声を張り上げました。)
Poor Wilbur was dazed and frightened by this hullabaloo. He didn't like being the center of all this fuss. He tried to follow the instructions his friends were giving him, but he couldn't run downhill and uphill at the same time, and he couldn't turn and twist when he was jumping and dancing and he was crying so hard he could barely see anything that was happening. After all, Wilbur was a very young pig--not much more than a baby, really. He wished Fern were thereto take him in her arms and comfort him. When he looked up and saw Mr.Zuckerman standing quite close to him, holding a pail of warm slope, he felt relieved. He lifted his mose and sniffed. The smell was delicious--warm milk, potato skins, wheat middlings, Kellogg's Corn Flakes, and a popover left from the Zuckermans' breakfast.
(やかましいさわぎに、あわれなウィルバーはすっかりのぼせあがり、怖くなってしまいました。自分のことで、誰もが大騒ぎしているのです。仲間の言うとおりにしようと思っても、坂を下るのと坂をのぼるのを同時にすることはできません。ジャンプしてはねているときに、くるっと体をひねることもできません。それに、ウィルバーは自分でも大声を出していたので、もう何が起こっているのか、よく分からなくなっていました。なんといっても、ウィルバーはまだ赤ちゃんといったっていいくらい、本当に小さいブタだったんですからね。ああ、ファーンがここにいて、だっこしてくれたらいいのになあ。ふと顔をあげると、ザッカーマンのおじさんが、あたたかい残飯の入ったバケツを持って、すぐそばに立っていました。ウィルバーは、ほっとして鼻をもちあげ、クンクンとにおいをかぎました。美味しそうなにおいがします。あったかいミルクと、ジャガイモの皮と、フスマ飼料と、ケロッグのコーンフレークと、ザッカーマンさんたちが朝ごはんのときに食べ残したパンのにおいです。)
"Come, pig!" said Mr.Zuckerman, tapping the pail. "Come pig!"
(「おいで!」と、ザッカーマンのおじさんが、バケツをトントンたたきながらいいました。「さあ、おいで!」)
Wilbur took a step toward the pail.
(ウィルバーは、バケツのほうに1歩足をふみだしました。)
"No-no-no!" said the goose. "It's the old pail trick, Wilbur. Don't fall for it, don't fall it! He's trying to lure you back into captivity-ivity. He's appealing to you stomach."
(「だめ、だめ、だめ!餌でだまそうっていう手なのよ、ウィルバー。だまされないで、だまされないで!えさでさそって、またかこいにとじこめるつもりなのさ。ひっかかっちゃだめだよ。」ガチョウのおばさんがいいました。)
Wilbur didn't care. the food smelled appetizing. He took another step toward the pail.
(ウィルバーは、もうそれでもかまいませんでした。なにしろバケツのなかからは、とてもいいにおいがしていたのです。そこれ、もう1歩バケツに近づきました。)
"Pig, pig!" said Mr.Zuckerman in a kind voice, and began walking slowly toward the barnyard, looking all about him innocently, as if he didn't know that a little white pig was following along behind him.
(「よしよし、ブタくん!」ザッカーマンのおじさんは、やさしい声でよびかけると、ゆっくりと納屋のまえのかこいのほうに歩いていきました。まるで、小さな白いブタが後ろからうしろからついてくるかどうかなど、まったく気にかけていない様子で、まわりを見渡しながら。)
"You'll be sorry-sorry-sorry," called the goose.
(「後悔するよ、後悔、後悔。」ガチョウのおばさんが大声で言いました。)
Wilbur didn't care. He kept walking toward the pail of slops.
(ウィルバーは、それでもかまいませんでした。残飯バケツのあとについて、どんどん歩いていきました。)
"You'll miss your freedom," honked the goose. "An hour of hreedom is worth a barrel of slops."
(「自由がなくなっちゃうんだよ。」ガチョウのおばさんが言いました。「自由な1時間は、バケツ1杯の残飯に負けないくらいすてきなのにさ。」)
Wilbur didn't care.
(ウィルバーはそれでもかまいませんでした。)
When Mr.Zuckerman reached the pigpen, he climbed over the fence and poured the slops into the trough. Then he pulled the loose board away from the fence, so that there was a wide hole for Wilbur to walk through.
(ザッカーマンのおじさんは、ブタのかこいまでやってくると、へいをまたいで、バケツの中の残飯をえさ箱にいれました。それから、ウィルバーをなかに入れるために、ぐらぐらになってぶらさがっていた板をへいからはずしました。)
"Reconsider, reconsider!" cried the goose.
(「考え直して、考え直して!」ガチョウのおばさんがさけびました。)
Wilbur paid no attention. He stepped through the fence into his yard. He walked to the trough and took a long drink of slops, sucking in the milk hungrily and chewing the popover. It was good to be home again.
(ウィルバーは聞いていませんでした。へいにあいた穴から中に入り、えさ箱に近より、ズズズッと残飯をすすり、ミルクを飲み、パンをかみました。家に帰ってこられて、ほっとしていました。)
While Wilbur ate, Lurvy fetched a hammer and some 8-penny nails and nailed the board in place. Then he and Mr.Zuckerman leaned lazily on the fence and Mr.Zuckerman scratched Wilbur's back with a stick.
(ウィルバーが食べているあいだに、ラーヴィーがかなづちと釘を持っていき、へいに板を打ち付けました。それからザッカーマンのおじさんは、ラーヴィーと一緒にへいにゆったりとよりかかり、棒でウィルバーの背中をかいてやりました。)
"He's quite a pig," said Lurvy.
(「こいつはなかなかのブタですね。」と、ラーヴィーはいいました。)
"Yes, he'll make a good pig," said Mr.Zuckerman.
(「そうなだ。いいブタになるぞ。」と、ザッカーマンのおじさんはいいました。)
Wilbur heard the words of praise. He felt the warm milk inside his stomach. He felt the pleasant rubbing of the stick along his itchy back. He felt peaceful and hapy and sleepy. This had been a tiring afternoon. It was still only four o'clock but Wilbur was ready for bed.
(ほめ言葉がウィルバーの耳に入りました。おなかの中には温かいミルクが流れ込んでいました。背中のかゆいとこを棒でかいてもらって、いい気持ちでした。穏やかで、しあわせで、ねむたくなってきました。なんといっても、午後の冒険でウィルバーはぐったり疲れていました。まだ4時にしかなっていませんでしたが、ウィルバーはもう眠かったのです。)
"I'm really too young to go out into the world alone," he thought as he lay down.
(「僕はまだ、ひとりで世界に出て行くには、小さすぎるんだな。」横になりながら、ウィルバーはそう思っていました。)
英文のみです。
Ⅲ. Escape
The baran was very large. It was very old. It smelled of hey and it smelled of tired horses and the wonderful sweet breath of patient cows. It often had a sort of peaceful smell--as though nothing bad could happen ever again in the world. It smelled of grain and of harness dressing and of axle grease and of rubber boots and of new rope. And whenever the cat was given a fish-head to eat, the barn would smell of fish. But mostly it smelled of hay, for there was always hay in the great loft up overhead. And there was always hay being pitched down to the cows and the horses and the sheep.
The barn was pleasantly warm in winter when the animals spent most of their time indoors, and it was pleasantly cool in summer when the big doors stood wide open to the breeze. The barn had stalls on the main floor for the work horses, tie-ups on the main floor for the cows, a sheepfold down below for the sheep, a pigpen down below for Wilbur, and it was full of all sorts of things that you find in barns: ladders, grindstones, pitch forks, monkey wrenches, scythes, lawn mowers, snow shovels, ax handles, milk pails, water buckets, empty grain sacks, and rusty rat traps. It was the kind of barn that swallows like to build their neses in. It was the kind of barn that children like to play in. And the whole thing was owned by Fern's uncle, Mr.Homer L.Zuckerman.
Wilbur's new home was in the lower part of the barn, directly underneath ihe cows. MrZuckerman knew that a manure pile is a good place to keep a young pig. Pigs need warmth, and it was warm and comfortable down there in the barn cellar on the south side.
Fern came slmost every day to visit him. She found an old milking stool that had been discarded, and she placed the stool in the sheepfold next to Wilbur's pen. Here she sat quietly during the long afternoons, thinking and listening and watching Wilbur. The sheep soon got to know her and trust her. So did the geese, who lived with the sheep. All the animals trusted her, she was so quiet and friendly. Mr.Zuckerman did not allow her to take Wilbur out, and he did not allow her to get into the pigpen. But to hold Fern that she could sit on the stool and watch Wilbur as long as she wanted to. It made her happy just to be near the pig, and it made Wilbur happy to know that she was sitting there, right outside his pen. But he never had any fun--no walks, no rides, no swaims.
One afternoon in June, when Wilbur was almost two months old, he wandered out into his small yard outside the barn. Fern had not arrived for her usual visit. Wilbur stood in the sun feeling lonely and bored.
"There's never anything to do around here," he thought. He walked slowly to his food trough and sniffed to see if anything had been overlooked at lunch. He found a small strip of potato skin and ate it. His back itched, climbed to the top of the manure pile, and sat down. He didn't feel like going to sleep, he didn't feel like digging, he was tired of standing still, tired of lying down. "I'm less than two months old and I'm tired of living," he said. He walked out to the yard again.
"When I'm out here," he said, "there's no place to go but in. When I'm indoors, there's no place to go but out in the yard."
"That's when you're wrong, my friend, my friend," said a voice.
Wilbur looked through the fence and saw the goose standing there.
"You don't have to stay in that dirty-little dirty-tittle yard," said the gooes, who talked rather fast. "One of the boards is loose. Push on it, push-push-push on it, and come on out!"
"What?" said Wilbur. "Say it slower!"
"At-at-at, at the risk of repeating myself," said the goose, "I suggest that you come on out. It's wonderful out here."
"Did you say a board was loose?"
"That I did, that I did," said the goose.
Wilbur walked up to the fence and saw that the goose was right--one board was loose. He put his head down, shut his eyes, and pushed. The board gave way. In a minute he had squeezed through the fence and was standing in the long grass outside his yard. The goose chuckled.
"How does it feel to be free?" she asked.
"I like it," said Wilbur. "That is, I guess I like it. Actually, Wilbur felt queer to be outside his fence, with nothing between him and the big world.
"Where do you think I'd better go?"
"Anywhere you like, anywhere you like," said the goose. "Go down through the orchard, root up the sod! Go down through the garden, dig up the radishes! Root up everything! Eat grass! Look for corn! Look for oats! Run all over! Skip and dance, jump and prance! Go down through the orchard and stroll in the woods! The world is a wonderful place when you're young."
"I can see that," replied Wilbur. He gave a jump in the air, twirled, run a few steps, stopped, looked all around, sniffed the the smells of afternoon, and then set off walking down through the orchard. Pausing in the shade of an apple tree, he put his strong snout into the ground and began pushing, digging, and rooting. He felt very happy. He had plowed up quite a piece of ground before anyone noticed him. Mrs.Zuckerman was the first to see him. She saw him from the kitchen window, and she immediately shouted for the men.
"Ho-mer!" she cried. "Pig's out! Lurvy! Pig's out! Homer! Lurvy! Pig's out. He's down there under that apple tree."
"Now the trouble starts," through Wilbur. "Now I'll catch it."
The goose head the racket and she, too, started hollering. "Run-run-run downhill, make for the woods, the woods!" she shouted to Wilbur. "They'll never-never-never catch you in the woods."
The cocker spaniel heard the commotion and he ran out from the barn to join the chase. Mr.Zuckerman heard, and he came out of the machine shed where he was mending a tool. Lurvy, the hired man, heard the noise and came up from the asparagus patch where he was pulling weeds. Everybody walked toward Wilbur and Wilbur didn't know what to do. The woods seemed a long way off, and anyway, he had never been down there in the woods and wasn't sure he would like it.
"Get around behind him, Lurvy," said Mr.Zuckerman, "and drive him toward the barn! And take it easy--don't rush him! I'll go and get a bucket of slops."
The news of Wilbur's escape spread repidly among the animals on the place. Whenever any creature broke loose on Zuckerman's farm, the event was of great interest to the others. The goose shouted to the nearest cow that Wilbur was free, and soon all the cows knew. Then one of the cows told one of the sheep, and soon all the sheep knew. The lambs learned about it from their mothers. The horses, in their stalls in the barn, pricked up their ears when they heard the goose hollering; and soon the hotses had caught on to what was happening. "Wilbur's out," they said. Every animal sirred and lifted its head and became excited to know that one of his friends had got free and was no konger penned up or tied fast.
Wilbur didn't know what to do or which way to run. It seemed as though everybody was after him. "If this is waht it's like to be free," he thought, "I believe I'd rather be penned up in my own yard."
The cocker spaniel was sneaking up on him from one side, Lurvy the hired man was sneaking up on him from the other side. Mrs.Zuckerman stood ready to head him off if he started for the garden, and now Mr.Zuckerman was coming doen toward him carrying a pail. "This is really awful," thought Wilbur. "Why doesn't Fern come?" He began to cry.
The goose took command and began to give orders.
"Don't just stand there, Wilbur! Dodge about, dodge about!" cried the goose. "Skip around, run toward me, slip in and out, in and out, in and out! Make for the woods! Twist and turn!"
The cocker spaniel sprang for Wilbur's hind leg. Wilbur jumped and ran. Lurvy reached out and grabbed. Mrs.Zuckerman screamed at Lurvy. The goose cheered for Wilbur. Wilbur dodged between Lurvy's legs. Lurvy missed Wilbur and grabbed the spaniel instead. "Nicely done, nicely done!" cried the goose. "Try it again, try it again!"
"Run downhill!" suggested the cows.
"Run toward me!" yelled the gander.
"Run uphill!" cried the sheep.
"Turn and twist!" honked the goose.
"Jump and dance!" said the rooster.
"Look out for Lurvy!" called the cows.
"Look out for Zuckerman!" yelled the gander.
"Watch out for the dog!" cried the sheep.
"Listen to me, listen to me!" screamed the goose.
Poor Wilbur was dazed and frightened by this hullabaloo. He didn't like being the center of all this fuss. He tried to follow the instructions his friends were giving him, but he couldn't run downhill and uphill at the same time, and he couldn't turn and twist when he was jumping and dancing and he was crying so hard he could barely see anything that was happening. After all, Wilbur was a very young pig--not much more than a baby, really. He wished Fern were thereto take him in her arms and comfort him. When he looked up and saw Mr.Zuckerman standing quite close to him, holding a pail of warm slope, he felt relieved. He lifted his mose and sniffed. The smell was delicious--warm milk, potato skins, wheat middlings, Kellogg's Corn Flakes, and a popover left from the Zuckermans' breakfast.
"Come, pig!" said Mr.Zuckerman, tapping the pail. "Come pig!"
Wilbur took a step toward the pail.
"No-no-no!" said the goose. "It's the old pail trick, Wilbur. Don't fall for it, don't fall it! He's trying to lure you back into captivity-ivity. He's appealing to you stomach."
Wilbur didn't care. the food smelled appetizing. He took another step toward the pail.
"Pig, pig!" said Mr.Zuckerman in a kind voice, and began walking slowly toward the barnyard, looking all about him innocently, as if he didn't know that a little white pig was following along behind him.
"You'll be sorry-sorry-sorry," called the goose.
Wilbur didn't care. He kept walking toward the pail of slops.
"You'll miss your freedom," honked the goose. "An hour of hreedom is worth a barrel of slops."
Wilbur didn't care.
When Mr.Zuckerman reached the pigpen, he climbed over the fence and poured the slops into the trough. Then he pulled the loose board away from the fence, so that there was a wide hole for Wilbur to walk through.
"Reconsider, reconsider!" cried the goose.
Wilbur paid no attention. He stepped through the fence into his yard. He walked to the trough and took a long drink of slops, sucking in the milk hungrily and chewing the popover. It was good to be home again.
While Wilbur ate, Lurvy fetched a hammer and some 8-penny nails and nailed the board in place. Then he and Mr.Zuckerman leaned lazily on the fence and Mr.Zuckerman scratched Wilbur's back with a stick.
"He's quite a pig," said Lurvy.
"Yes, he'll make a good pig," said Mr.Zuckerman.
Wilbur heard the words of praise. He felt the warm milk inside his stomach. He felt the pleasant rubbing of the stick along his itchy back. He felt peaceful and hapy and sleepy. This had been a tiring afternoon. It was still only four o'clock but Wilbur was ready for bed.
"I'm really too young to go out into the world alone," he thought as he lay down.
The baran was very large. It was very old. It smelled of hey and it smelled of tired horses and the wonderful sweet breath of patient cows. It often had a sort of peaceful smell--as though nothing bad could happen ever again in the world. It smelled of grain and of harness dressing and of axle grease and of rubber boots and of new rope. And whenever the cat was given a fish-head to eat, the barn would smell of fish. But mostly it smelled of hay, for there was always hay in the great loft up overhead. And there was always hay being pitched down to the cows and the horses and the sheep.
The barn was pleasantly warm in winter when the animals spent most of their time indoors, and it was pleasantly cool in summer when the big doors stood wide open to the breeze. The barn had stalls on the main floor for the work horses, tie-ups on the main floor for the cows, a sheepfold down below for the sheep, a pigpen down below for Wilbur, and it was full of all sorts of things that you find in barns: ladders, grindstones, pitch forks, monkey wrenches, scythes, lawn mowers, snow shovels, ax handles, milk pails, water buckets, empty grain sacks, and rusty rat traps. It was the kind of barn that swallows like to build their neses in. It was the kind of barn that children like to play in. And the whole thing was owned by Fern's uncle, Mr.Homer L.Zuckerman.
Wilbur's new home was in the lower part of the barn, directly underneath ihe cows. MrZuckerman knew that a manure pile is a good place to keep a young pig. Pigs need warmth, and it was warm and comfortable down there in the barn cellar on the south side.
Fern came slmost every day to visit him. She found an old milking stool that had been discarded, and she placed the stool in the sheepfold next to Wilbur's pen. Here she sat quietly during the long afternoons, thinking and listening and watching Wilbur. The sheep soon got to know her and trust her. So did the geese, who lived with the sheep. All the animals trusted her, she was so quiet and friendly. Mr.Zuckerman did not allow her to take Wilbur out, and he did not allow her to get into the pigpen. But to hold Fern that she could sit on the stool and watch Wilbur as long as she wanted to. It made her happy just to be near the pig, and it made Wilbur happy to know that she was sitting there, right outside his pen. But he never had any fun--no walks, no rides, no swaims.
One afternoon in June, when Wilbur was almost two months old, he wandered out into his small yard outside the barn. Fern had not arrived for her usual visit. Wilbur stood in the sun feeling lonely and bored.
"There's never anything to do around here," he thought. He walked slowly to his food trough and sniffed to see if anything had been overlooked at lunch. He found a small strip of potato skin and ate it. His back itched, climbed to the top of the manure pile, and sat down. He didn't feel like going to sleep, he didn't feel like digging, he was tired of standing still, tired of lying down. "I'm less than two months old and I'm tired of living," he said. He walked out to the yard again.
"When I'm out here," he said, "there's no place to go but in. When I'm indoors, there's no place to go but out in the yard."
"That's when you're wrong, my friend, my friend," said a voice.
Wilbur looked through the fence and saw the goose standing there.
"You don't have to stay in that dirty-little dirty-tittle yard," said the gooes, who talked rather fast. "One of the boards is loose. Push on it, push-push-push on it, and come on out!"
"What?" said Wilbur. "Say it slower!"
"At-at-at, at the risk of repeating myself," said the goose, "I suggest that you come on out. It's wonderful out here."
"Did you say a board was loose?"
"That I did, that I did," said the goose.
Wilbur walked up to the fence and saw that the goose was right--one board was loose. He put his head down, shut his eyes, and pushed. The board gave way. In a minute he had squeezed through the fence and was standing in the long grass outside his yard. The goose chuckled.
"How does it feel to be free?" she asked.
"I like it," said Wilbur. "That is, I guess I like it. Actually, Wilbur felt queer to be outside his fence, with nothing between him and the big world.
"Where do you think I'd better go?"
"Anywhere you like, anywhere you like," said the goose. "Go down through the orchard, root up the sod! Go down through the garden, dig up the radishes! Root up everything! Eat grass! Look for corn! Look for oats! Run all over! Skip and dance, jump and prance! Go down through the orchard and stroll in the woods! The world is a wonderful place when you're young."
"I can see that," replied Wilbur. He gave a jump in the air, twirled, run a few steps, stopped, looked all around, sniffed the the smells of afternoon, and then set off walking down through the orchard. Pausing in the shade of an apple tree, he put his strong snout into the ground and began pushing, digging, and rooting. He felt very happy. He had plowed up quite a piece of ground before anyone noticed him. Mrs.Zuckerman was the first to see him. She saw him from the kitchen window, and she immediately shouted for the men.
"Ho-mer!" she cried. "Pig's out! Lurvy! Pig's out! Homer! Lurvy! Pig's out. He's down there under that apple tree."
"Now the trouble starts," through Wilbur. "Now I'll catch it."
The goose head the racket and she, too, started hollering. "Run-run-run downhill, make for the woods, the woods!" she shouted to Wilbur. "They'll never-never-never catch you in the woods."
The cocker spaniel heard the commotion and he ran out from the barn to join the chase. Mr.Zuckerman heard, and he came out of the machine shed where he was mending a tool. Lurvy, the hired man, heard the noise and came up from the asparagus patch where he was pulling weeds. Everybody walked toward Wilbur and Wilbur didn't know what to do. The woods seemed a long way off, and anyway, he had never been down there in the woods and wasn't sure he would like it.
"Get around behind him, Lurvy," said Mr.Zuckerman, "and drive him toward the barn! And take it easy--don't rush him! I'll go and get a bucket of slops."
The news of Wilbur's escape spread repidly among the animals on the place. Whenever any creature broke loose on Zuckerman's farm, the event was of great interest to the others. The goose shouted to the nearest cow that Wilbur was free, and soon all the cows knew. Then one of the cows told one of the sheep, and soon all the sheep knew. The lambs learned about it from their mothers. The horses, in their stalls in the barn, pricked up their ears when they heard the goose hollering; and soon the hotses had caught on to what was happening. "Wilbur's out," they said. Every animal sirred and lifted its head and became excited to know that one of his friends had got free and was no konger penned up or tied fast.
Wilbur didn't know what to do or which way to run. It seemed as though everybody was after him. "If this is waht it's like to be free," he thought, "I believe I'd rather be penned up in my own yard."
The cocker spaniel was sneaking up on him from one side, Lurvy the hired man was sneaking up on him from the other side. Mrs.Zuckerman stood ready to head him off if he started for the garden, and now Mr.Zuckerman was coming doen toward him carrying a pail. "This is really awful," thought Wilbur. "Why doesn't Fern come?" He began to cry.
The goose took command and began to give orders.
"Don't just stand there, Wilbur! Dodge about, dodge about!" cried the goose. "Skip around, run toward me, slip in and out, in and out, in and out! Make for the woods! Twist and turn!"
The cocker spaniel sprang for Wilbur's hind leg. Wilbur jumped and ran. Lurvy reached out and grabbed. Mrs.Zuckerman screamed at Lurvy. The goose cheered for Wilbur. Wilbur dodged between Lurvy's legs. Lurvy missed Wilbur and grabbed the spaniel instead. "Nicely done, nicely done!" cried the goose. "Try it again, try it again!"
"Run downhill!" suggested the cows.
"Run toward me!" yelled the gander.
"Run uphill!" cried the sheep.
"Turn and twist!" honked the goose.
"Jump and dance!" said the rooster.
"Look out for Lurvy!" called the cows.
"Look out for Zuckerman!" yelled the gander.
"Watch out for the dog!" cried the sheep.
"Listen to me, listen to me!" screamed the goose.
Poor Wilbur was dazed and frightened by this hullabaloo. He didn't like being the center of all this fuss. He tried to follow the instructions his friends were giving him, but he couldn't run downhill and uphill at the same time, and he couldn't turn and twist when he was jumping and dancing and he was crying so hard he could barely see anything that was happening. After all, Wilbur was a very young pig--not much more than a baby, really. He wished Fern were thereto take him in her arms and comfort him. When he looked up and saw Mr.Zuckerman standing quite close to him, holding a pail of warm slope, he felt relieved. He lifted his mose and sniffed. The smell was delicious--warm milk, potato skins, wheat middlings, Kellogg's Corn Flakes, and a popover left from the Zuckermans' breakfast.
"Come, pig!" said Mr.Zuckerman, tapping the pail. "Come pig!"
Wilbur took a step toward the pail.
"No-no-no!" said the goose. "It's the old pail trick, Wilbur. Don't fall for it, don't fall it! He's trying to lure you back into captivity-ivity. He's appealing to you stomach."
Wilbur didn't care. the food smelled appetizing. He took another step toward the pail.
"Pig, pig!" said Mr.Zuckerman in a kind voice, and began walking slowly toward the barnyard, looking all about him innocently, as if he didn't know that a little white pig was following along behind him.
"You'll be sorry-sorry-sorry," called the goose.
Wilbur didn't care. He kept walking toward the pail of slops.
"You'll miss your freedom," honked the goose. "An hour of hreedom is worth a barrel of slops."
Wilbur didn't care.
When Mr.Zuckerman reached the pigpen, he climbed over the fence and poured the slops into the trough. Then he pulled the loose board away from the fence, so that there was a wide hole for Wilbur to walk through.
"Reconsider, reconsider!" cried the goose.
Wilbur paid no attention. He stepped through the fence into his yard. He walked to the trough and took a long drink of slops, sucking in the milk hungrily and chewing the popover. It was good to be home again.
While Wilbur ate, Lurvy fetched a hammer and some 8-penny nails and nailed the board in place. Then he and Mr.Zuckerman leaned lazily on the fence and Mr.Zuckerman scratched Wilbur's back with a stick.
"He's quite a pig," said Lurvy.
"Yes, he'll make a good pig," said Mr.Zuckerman.
Wilbur heard the words of praise. He felt the warm milk inside his stomach. He felt the pleasant rubbing of the stick along his itchy back. He felt peaceful and hapy and sleepy. This had been a tiring afternoon. It was still only four o'clock but Wilbur was ready for bed.
"I'm really too young to go out into the world alone," he thought as he lay down.
日本語訳のみです。
3.にげろ
ウィルバーが暮らすことになったのは、とても古く大きな納屋で、干草と堆肥のにおいがしました。くたびれた馬のあせのにおいと、しんぼう強い雌牛のあまやかな息のにおいもしました。たいていは、安らかで平和なにおいに満ちていたので、世の中にはもう2度と悪いことなど起こらないように思えました。それに、穀物や、馬具をみがく油や、車軸につける機械油、ゴム長ぐつや新しいロープのにおいもしていました。ネコが魚の頭をもらうと、納屋は魚くさくもなりました。でも、いちばん強くにおうのは、なんといっても干草でした。というのも、納屋の2階には、干草がどっさりつんであったのです。その干草は、下にいる牝牛や馬や羊に必要とあれば、いつでも上から投げ下ろされるのでした。
動物たちがほとんどの時間を屋内で過ごす冬でも、納屋の中は暖かでした。そして夏には、大きなとびらがあけはなたれて風が入ってくるので、なかなか涼しいのでした。納屋の1階には、農耕馬や牝牛のための部屋があり、床下には羊の部屋やウィルバーのためのブタの部屋がありました。それに、この納屋の中には、はしごだとか、丸砥石だとか、くまでだとか、モンキースパナだとか、かまだとか、芝刈り機だとか、雪かきシャベルだとか、斧の枝とか、ミルク容器だとか、バケツだとか、からっぽの穀物袋だとか、さびたネズミとりだとか、ふつうの納屋にありそうなものは、なんでもありました。それに、ここは、ツバメが巣を作りたいと思うような納屋でした。そして子供が遊びたいと思うような、そんな納屋でもありました。そして、納屋にあるものはみんな、ホーマー・L・ザッカーマンという名前の、ファーンおおじさんのものでした。
ウィルバーの新しい部屋は、牝牛たちの部屋のすぐ下にありました。ザッカーマンさんは、小さい子ブタを飼うには、堆肥の山がちょうどいいことを知っていたのです。ブタは暖かいのが好きでしたし、納屋の床下の南側は、ぬくぬくとあたたかったのです。
ファーンは毎日のようにウィルバーに会いに行きました。父絞りの時に使ういすが捨ててあったので、ファーンはそのいすをウィルバーの部屋の隣にある羊の部屋に置きました。そしてそこに腰を下ろすと、ウィルバーのことを考えたり、ウィルバーの声を聞いたり、ウィルバーのしぐさを眺めたりしながら、昼下がりの長い時間をおとなしく過ごしていたのです。
羊はすぐにファーンになじみ、警戒しなくなりました。羊と一緒に暮らしていたガチョウも同じでした。なやの動物はみんな、ものしずかで優しいファーンに気をゆるすようになりました。ザッカーマンさんは、ファーンがウィルバーの囲いの中に入ったり、ウィルバーを外につれだしたりするのは、許してくれませんでした。けれども、いすに腰かけてウィルバーをながめるのは、すきなだけよっていてよかったのです。
ファーンは、ウィルバーのそばにいられるだけで満足でしたし、ウィルバーも、自分のへやのすぐ外にファーンが座っているだけで幸せでした。でも、散歩にでかけたり、乳母車に乗ったり、水遊びをしたりする楽しみはありませんでした。
ウィルバーが生まれてもうすぐ2ヶ月になるという、ある6月の朝のことです。ウィルバーは床下から、外にある小さな囲いの中にでていきました。いつもくるファーンは、まだ顔を見せません。一人ぼっちで退屈してきたウィルバーは、日の光をあびながら、じっと立っていました。「ここには、あんまりやることがないんだよな。」と思いながら、えさ箱のほうに歩いていって、アヒルご飯がひょっとして残っていないかどうか、匂いをかぎました。ジャガイモの皮がちょっぴりのこっていたので、それを食べました。背中がかゆくなってきたので、へいにもたれかかって、板に背中をこすり付けました。それにもあきると、ウィルバーは床下の部屋にもどって、堆肥の山に腰を下ろしました。眠る気にもなれないし、穴を掘る気にも慣れません。かといって、じっと立っているのにもあきたし、横になるのにもあきていました。
「まだうまれて2ヶ月にもならないのに、僕はもう生きているのにうんざりしちゃった。」
そういうとウィルバーは、また外のかこいに出て行きました。
「外のかこいに出れば、次は部屋の中に行くしか、いくところがないだろ。部屋の中に入れば、あとは外の囲いしか、行くところがないんだよな。」と、ウィルバーはひとり言をいいました。
「ちがう、ちがう、ちがう。」と、声がしました。
へいの向こうを見ると、そこにはガチョウのおばさんが立っていました。
「そんなうすぎたない、ちっぽけな、ちっぽけな、ちっぽけなかこいにいることないのよ。」と、ガチョウのおばさんは早口で言いました。「へいのかこいの板が1枚、ぐらぐらになってるのよ。そこを、おして、おして、おして、外にでといで!」
「なに?もう少しゆっくりいってよ!」と、ウィルバーはいいました。
「しょうが、しょうが、しょうがないわねえ。でておいでって、いったのよ。外はすてきだよ。」
「ぐらぐらの板があるって、いったの?」
「そう、そう、そうよ。」
へいのそばまでいってみると、ガチョウのおばさんの言ったとおりだといいうことが分かりました。へい板の1つが、ゆるくなっていました。ウィルバーは頭を下げて、目をとじると、ぐいっと押しました。板の片方がはずれました。そこをくぐった向こうには、草が高くおいしげっていました。ウィルバーは外にでたのです。ガチョウが、くすくす笑いました。
「自由になった気分はどう?」ガチョウのおばさんがたずねました。
「いいね。」と、ウィルバーはいいました。「たぶん、いいんだと思うんだけど」
へいの外にはでたものの、ウィルバーは少し面食らっていました。なにしろ、広い世界と自分とのあいだには板塀も何もないんです。
「ぼく、どっちへいったらいいんだろう?」
「どこでも、どこでも、おすきなところへ」と、ガチョウのおばさんは言いました。「果樹園に行って、芝土をほってもいい!畑にいって、アカカブをほってもいい!あっちこっちほりかえしたっていいわ!草を食べてもいい!さがせばトウモロコシが見つかるわ!カラス麦も見つかるわ!そこらじゅう走り回りなさいよ!スキップして、おどって、ジャンプして、はねて!果樹園をぬければ、森だって散歩できるわ!若いときなら、この世界はすばらしいものよ。」
「そうだろうね。」
ウィルバーはそういって、ぴょんととびあがり、くるっとまわり、ちょこちょこっと走り、立ち止まり、あたりを見まわし、昼下がりのにおいをかぎ、それから果樹園のなかを歩き始めました。1本のリンゴの木の下で立ち止まると、丈夫な鼻を地面につっこんで、ほじくりかえしました。なんてすてきなんでしょう!だれも気づかないでいるあいだに、ウィルバーは、あちこちをさんざん掘り返していました。最初に気づいたのは、ザッカーマンのおばさんでした。台所のまどからウィルバーが見えたとたん、大声で叫びました。
「ホーマー!ブタが外にでちゃったわよ!ラーヴィー!ブタが逃げたのよ!ホーマー!ラーヴィー!ブタが逃げたわ!リンゴの木の下よ!」
「たいへんだ。つかまっちゃうぞ!」ウィルバーは思いました。
さわぎを聞きつけたガチョウのおばさんも、大声でウィルバーにどなりました。
「坂を下って、走って、走って、走って!森へ、森へ、森へ!森の中に入れば、絶対、絶対、絶対つかまらないからね!」
コッカースパニエル犬が、ごたごたをききつけて納屋から出てくると、追っ手に加わりました。機械小屋で道具を修理していたザッカーマンのおじさんが、声をきいてでてきました。アスパラガスの畑で草とりをしていた雇い人のラーヴィーも、声を聞きつけてでてきました。みんなが自分のほうへやってくるので、ウィルバーはとまどいました。森はずいぶん遠そうでしたし、1度もいったことがないので、素敵なところかどうかも、わかりません。
「ラーヴィー、うしろへまわってくれ。」ザッカーマンのおじさんが言いました。「納屋のほうへ追い込むんだ!そろそろいけよ。おどかさないでな。わたしは残飯をとってくる。」
ウィルバーが逃げ出したというニュースは、農場の動物のあいだに、ぱっと広がりました。ザッカーマン農場では、誰かの脱出は、みんなの興味の的でした。ガチョウのおばさんが、すぐ近くにいた雌牛に、ウィルバーが外に出たと大声で告げると、ニュースはたちまち雌牛全員に伝わりました。つぎに、雌牛が1匹の羊に話すと、ニュースはたちまち羊全員に伝わりました。子羊たちは、お母さんからニュースを聞きました。納屋の仕切りの中にいた馬たちは、ガチョウが叫んだときに耳をそばだてて、何が起こったかをたちまち知りました。「ウィルバーが逃げたんだ!」と、馬はいいました。仲間が逃げ出して、もう囲いに閉じ込められたり、綱につながれたりしていないのを知ると、動物たちはみなじっとしていられず、頭を持ち上げてもぞもぞ動き、胸をドキドキさせるのでした。
ウィルバーは、どうしていいかも分からなければ、どっちににげたらいいのかも知りませんでした。誰かもかれもが追いかけ来るような気がしました。
「自由になるっていうのがこういうことなら、納屋の前の囲いの中にいたほうがよかったな。」と、ウィルバーは思いました。
コッカースパニエル犬が、片側からそろそろとウィルバーに近づいてきました。雇い人のラーヴィーが、反対側からそろそろとウィルバーに近づいてきました。ザッカーマンのおばさんは、畑の前で通せんぼをしていました。そしてザッカーマンのおじさんも、残飯の入ったバケツを持って近づいてきました。
「ああ、いやんなっちゃうな。ファーンはどうしてきてくれないのかな?」ウィルバーは、泣き声をあげました。
ガチョウのおばさんが、先にたって命令しました。
「つっ立ってちゃだめよ、ウィルバー!かわして、かわして!」ガチョウは叫びました。
「ぴょんととんで、こっちへくるのよ。すりぬけて、すりぬけて、すりぬけて!森へ行きなさい!くるっと向きを変えるのよ!」
コッカースパニエル犬が、ウィルバーの後足にとびかかりました。ウィルバーはぴょんととびあがって、逃げました。ラーヴィーが手を伸ばして、ウィルバーを捕まえようとしました。ザッカーマンのおばさんが、かなきり声をあげました。ガチョウのおばさんがウィルバーに声援を送りました。ウィルバーは、ラーヴィーの足のあいだをすり抜けました。ラーヴィーはウィルバーを捕まえそこね、かわりにコッカースパニエル犬をつかんでしまいました。
「その調子、その調子!」ガチョウのおばさんがさけびました。「もういちど、もういちど!」
「坂をくだるのよ!」雌牛たちが言いました。
「こっちへ逃げて来い!」がちょうのおじさんがどなりました。
「坂をのぼりなさい!」羊たちが叫びました。
「くるっと体をひねって!」ガチョウのおばさんががなりたてました。
「ジャンプしてはねるんだ!」おんどりが言いました。
「ラーヴィーに気をつけて!」雌牛たちが言いました。
「ザッカーマンに気をつけるんだ!」ガチョウのおじさんが叫びました。
「犬に注意して!」羊たちがどなりました。
「あたしのいうとおりに、いうとおりに!」ガチョウのおばさんが声を張り上げました。
やかましいさわぎに、あわれなウィルバーはすっかりのぼせあがり、怖くなってしまいました。自分のことで、誰もが大騒ぎしているのです。仲間の言うとおりにしようと思っても、坂を下るのと坂をのぼるのを同時にすることはできません。ジャンプしてはねているときに、くるっと体をひねることもできません。それに、ウィルバーは自分でも大声を出していたので、もう何が起こっているのか、よく分からなくなっていました。なんといっても、ウィルバーはまだ赤ちゃんといったっていいくらい、本当に小さいブタだったんですからね。ああ、ファーンがここにいて、だっこしてくれたらいいのになあ。
ふと顔をあげると、ザッカーマンのおじさんが、あたたかい残飯の入ったバケツを持って、すぐそばに立っていました。ウィルバーは、ほっとして鼻をもちあげ、クンクンとにおいをかぎました。美味しそうなにおいがします。あったかいミルクと、ジャガイモの皮と、フスマ飼料と、ケロッグのコーンフレークと、ザッカーマンさんたちが朝ごはんのときに食べ残したパンのにおいです。
「おいで!」と、ザッカーマンのおじさんが、バケツをトントンたたきながらいいました。
「さあ、おいで!」
ウィルバーは、バケツのほうに1歩足をふみだしました。
「だめ、だめ、だめ!餌でだまそうっていう手なのよ、ウィルバー。だまされないで、だまされないで!えさでさそって、またかこいにとじこめるつもりなのさ。ひっかかっちゃだめだよ。」ガチョウのおばさんがいいました。
ウィルバーは、もうそれでもかまいませんでした。なにしろバケツのなかからは、とてもいいにおいがしていたのです。そこれ、もう1歩バケツに近づきました。
「よしよし、ブタくん!」ザッカーマンのおじさんは、やさしい声でよびかけると、ゆっくりと納屋のまえのかこいのほうに歩いていきました。まるで、小さな白いブタが後ろからうしろからついてくるかどうかなど、まったく気にかけていない様子で、まわりを見渡しながら。
「後悔するよ、後悔、後悔。」ガチョウのおばさんが大声で言いました。
ウィルバーは、それでもかまいませんでした。残飯バケツのあとについて、どんどん歩いていきました。
「自由がなくなっちゃうんだよ。」ガチョウのおばさんが言いました。「自由な1時間は、バケツ1杯の残飯に負けないくらいすてきなのにさ。」
ウィルバーはそれでもかまいませんでした。
ザッカーマンのおじさんは、ブタのかこいまでやってくると、へいをまたいで、バケツの中の残飯をえさ箱にいれました。それから、ウィルバーをなかに入れるために、ぐらぐらになってぶらさがっていた板をへいからはずしました。
「考え直して、考え直して!」ガチョウのおばさんがさけびました。
ウィルバーは聞いていませんでした。へいにあいた穴から中に入り、えさ箱に近より、ズズズッと残飯をすすり、ミルクを飲み、パンをかみました。家に帰ってこられて、ほっとしていました。
ウィルバーが食べているあいだに、ラーヴィーがかなづちと釘を持っていき、へいに板を打ち付けました。それからザッカーマンのおじさんは、ラーヴィーと一緒にへいにゆったりとよりかかり、棒でウィルバーの背中をかいてやりました。
「こいつはなかなかのブタですね。」と、ラーヴィーはいいました。
「そうなだ。いいブタになるぞ。」と、ザッカーマンのおじさんはいいました。
ほめ言葉がウィルバーの耳に入りました。おなかの中には温かいミルクが流れ込んでいました。背中のかゆいとこを棒でかいてもらって、いい気持ちでした。穏やかで、しあわせで、ねむたくなってきました。なんといっても、午後の冒険でウィルバーはぐったり疲れていました。まだ4時にしかなっていませんでしたが、ウィルバーはもう眠かったのです。
「僕はまだ、ひとりで世界に出て行くには、小さすぎるんだな。」横になりながら、ウィルバーはそう思っていました。
ウィルバーが暮らすことになったのは、とても古く大きな納屋で、干草と堆肥のにおいがしました。くたびれた馬のあせのにおいと、しんぼう強い雌牛のあまやかな息のにおいもしました。たいていは、安らかで平和なにおいに満ちていたので、世の中にはもう2度と悪いことなど起こらないように思えました。それに、穀物や、馬具をみがく油や、車軸につける機械油、ゴム長ぐつや新しいロープのにおいもしていました。ネコが魚の頭をもらうと、納屋は魚くさくもなりました。でも、いちばん強くにおうのは、なんといっても干草でした。というのも、納屋の2階には、干草がどっさりつんであったのです。その干草は、下にいる牝牛や馬や羊に必要とあれば、いつでも上から投げ下ろされるのでした。
動物たちがほとんどの時間を屋内で過ごす冬でも、納屋の中は暖かでした。そして夏には、大きなとびらがあけはなたれて風が入ってくるので、なかなか涼しいのでした。納屋の1階には、農耕馬や牝牛のための部屋があり、床下には羊の部屋やウィルバーのためのブタの部屋がありました。それに、この納屋の中には、はしごだとか、丸砥石だとか、くまでだとか、モンキースパナだとか、かまだとか、芝刈り機だとか、雪かきシャベルだとか、斧の枝とか、ミルク容器だとか、バケツだとか、からっぽの穀物袋だとか、さびたネズミとりだとか、ふつうの納屋にありそうなものは、なんでもありました。それに、ここは、ツバメが巣を作りたいと思うような納屋でした。そして子供が遊びたいと思うような、そんな納屋でもありました。そして、納屋にあるものはみんな、ホーマー・L・ザッカーマンという名前の、ファーンおおじさんのものでした。
ウィルバーの新しい部屋は、牝牛たちの部屋のすぐ下にありました。ザッカーマンさんは、小さい子ブタを飼うには、堆肥の山がちょうどいいことを知っていたのです。ブタは暖かいのが好きでしたし、納屋の床下の南側は、ぬくぬくとあたたかったのです。
ファーンは毎日のようにウィルバーに会いに行きました。父絞りの時に使ういすが捨ててあったので、ファーンはそのいすをウィルバーの部屋の隣にある羊の部屋に置きました。そしてそこに腰を下ろすと、ウィルバーのことを考えたり、ウィルバーの声を聞いたり、ウィルバーのしぐさを眺めたりしながら、昼下がりの長い時間をおとなしく過ごしていたのです。
羊はすぐにファーンになじみ、警戒しなくなりました。羊と一緒に暮らしていたガチョウも同じでした。なやの動物はみんな、ものしずかで優しいファーンに気をゆるすようになりました。ザッカーマンさんは、ファーンがウィルバーの囲いの中に入ったり、ウィルバーを外につれだしたりするのは、許してくれませんでした。けれども、いすに腰かけてウィルバーをながめるのは、すきなだけよっていてよかったのです。
ファーンは、ウィルバーのそばにいられるだけで満足でしたし、ウィルバーも、自分のへやのすぐ外にファーンが座っているだけで幸せでした。でも、散歩にでかけたり、乳母車に乗ったり、水遊びをしたりする楽しみはありませんでした。
ウィルバーが生まれてもうすぐ2ヶ月になるという、ある6月の朝のことです。ウィルバーは床下から、外にある小さな囲いの中にでていきました。いつもくるファーンは、まだ顔を見せません。一人ぼっちで退屈してきたウィルバーは、日の光をあびながら、じっと立っていました。「ここには、あんまりやることがないんだよな。」と思いながら、えさ箱のほうに歩いていって、アヒルご飯がひょっとして残っていないかどうか、匂いをかぎました。ジャガイモの皮がちょっぴりのこっていたので、それを食べました。背中がかゆくなってきたので、へいにもたれかかって、板に背中をこすり付けました。それにもあきると、ウィルバーは床下の部屋にもどって、堆肥の山に腰を下ろしました。眠る気にもなれないし、穴を掘る気にも慣れません。かといって、じっと立っているのにもあきたし、横になるのにもあきていました。
「まだうまれて2ヶ月にもならないのに、僕はもう生きているのにうんざりしちゃった。」
そういうとウィルバーは、また外のかこいに出て行きました。
「外のかこいに出れば、次は部屋の中に行くしか、いくところがないだろ。部屋の中に入れば、あとは外の囲いしか、行くところがないんだよな。」と、ウィルバーはひとり言をいいました。
「ちがう、ちがう、ちがう。」と、声がしました。
へいの向こうを見ると、そこにはガチョウのおばさんが立っていました。
「そんなうすぎたない、ちっぽけな、ちっぽけな、ちっぽけなかこいにいることないのよ。」と、ガチョウのおばさんは早口で言いました。「へいのかこいの板が1枚、ぐらぐらになってるのよ。そこを、おして、おして、おして、外にでといで!」
「なに?もう少しゆっくりいってよ!」と、ウィルバーはいいました。
「しょうが、しょうが、しょうがないわねえ。でておいでって、いったのよ。外はすてきだよ。」
「ぐらぐらの板があるって、いったの?」
「そう、そう、そうよ。」
へいのそばまでいってみると、ガチョウのおばさんの言ったとおりだといいうことが分かりました。へい板の1つが、ゆるくなっていました。ウィルバーは頭を下げて、目をとじると、ぐいっと押しました。板の片方がはずれました。そこをくぐった向こうには、草が高くおいしげっていました。ウィルバーは外にでたのです。ガチョウが、くすくす笑いました。
「自由になった気分はどう?」ガチョウのおばさんがたずねました。
「いいね。」と、ウィルバーはいいました。「たぶん、いいんだと思うんだけど」
へいの外にはでたものの、ウィルバーは少し面食らっていました。なにしろ、広い世界と自分とのあいだには板塀も何もないんです。
「ぼく、どっちへいったらいいんだろう?」
「どこでも、どこでも、おすきなところへ」と、ガチョウのおばさんは言いました。「果樹園に行って、芝土をほってもいい!畑にいって、アカカブをほってもいい!あっちこっちほりかえしたっていいわ!草を食べてもいい!さがせばトウモロコシが見つかるわ!カラス麦も見つかるわ!そこらじゅう走り回りなさいよ!スキップして、おどって、ジャンプして、はねて!果樹園をぬければ、森だって散歩できるわ!若いときなら、この世界はすばらしいものよ。」
「そうだろうね。」
ウィルバーはそういって、ぴょんととびあがり、くるっとまわり、ちょこちょこっと走り、立ち止まり、あたりを見まわし、昼下がりのにおいをかぎ、それから果樹園のなかを歩き始めました。1本のリンゴの木の下で立ち止まると、丈夫な鼻を地面につっこんで、ほじくりかえしました。なんてすてきなんでしょう!だれも気づかないでいるあいだに、ウィルバーは、あちこちをさんざん掘り返していました。最初に気づいたのは、ザッカーマンのおばさんでした。台所のまどからウィルバーが見えたとたん、大声で叫びました。
「ホーマー!ブタが外にでちゃったわよ!ラーヴィー!ブタが逃げたのよ!ホーマー!ラーヴィー!ブタが逃げたわ!リンゴの木の下よ!」
「たいへんだ。つかまっちゃうぞ!」ウィルバーは思いました。
さわぎを聞きつけたガチョウのおばさんも、大声でウィルバーにどなりました。
「坂を下って、走って、走って、走って!森へ、森へ、森へ!森の中に入れば、絶対、絶対、絶対つかまらないからね!」
コッカースパニエル犬が、ごたごたをききつけて納屋から出てくると、追っ手に加わりました。機械小屋で道具を修理していたザッカーマンのおじさんが、声をきいてでてきました。アスパラガスの畑で草とりをしていた雇い人のラーヴィーも、声を聞きつけてでてきました。みんなが自分のほうへやってくるので、ウィルバーはとまどいました。森はずいぶん遠そうでしたし、1度もいったことがないので、素敵なところかどうかも、わかりません。
「ラーヴィー、うしろへまわってくれ。」ザッカーマンのおじさんが言いました。「納屋のほうへ追い込むんだ!そろそろいけよ。おどかさないでな。わたしは残飯をとってくる。」
ウィルバーが逃げ出したというニュースは、農場の動物のあいだに、ぱっと広がりました。ザッカーマン農場では、誰かの脱出は、みんなの興味の的でした。ガチョウのおばさんが、すぐ近くにいた雌牛に、ウィルバーが外に出たと大声で告げると、ニュースはたちまち雌牛全員に伝わりました。つぎに、雌牛が1匹の羊に話すと、ニュースはたちまち羊全員に伝わりました。子羊たちは、お母さんからニュースを聞きました。納屋の仕切りの中にいた馬たちは、ガチョウが叫んだときに耳をそばだてて、何が起こったかをたちまち知りました。「ウィルバーが逃げたんだ!」と、馬はいいました。仲間が逃げ出して、もう囲いに閉じ込められたり、綱につながれたりしていないのを知ると、動物たちはみなじっとしていられず、頭を持ち上げてもぞもぞ動き、胸をドキドキさせるのでした。
ウィルバーは、どうしていいかも分からなければ、どっちににげたらいいのかも知りませんでした。誰かもかれもが追いかけ来るような気がしました。
「自由になるっていうのがこういうことなら、納屋の前の囲いの中にいたほうがよかったな。」と、ウィルバーは思いました。
コッカースパニエル犬が、片側からそろそろとウィルバーに近づいてきました。雇い人のラーヴィーが、反対側からそろそろとウィルバーに近づいてきました。ザッカーマンのおばさんは、畑の前で通せんぼをしていました。そしてザッカーマンのおじさんも、残飯の入ったバケツを持って近づいてきました。
「ああ、いやんなっちゃうな。ファーンはどうしてきてくれないのかな?」ウィルバーは、泣き声をあげました。
ガチョウのおばさんが、先にたって命令しました。
「つっ立ってちゃだめよ、ウィルバー!かわして、かわして!」ガチョウは叫びました。
「ぴょんととんで、こっちへくるのよ。すりぬけて、すりぬけて、すりぬけて!森へ行きなさい!くるっと向きを変えるのよ!」
コッカースパニエル犬が、ウィルバーの後足にとびかかりました。ウィルバーはぴょんととびあがって、逃げました。ラーヴィーが手を伸ばして、ウィルバーを捕まえようとしました。ザッカーマンのおばさんが、かなきり声をあげました。ガチョウのおばさんがウィルバーに声援を送りました。ウィルバーは、ラーヴィーの足のあいだをすり抜けました。ラーヴィーはウィルバーを捕まえそこね、かわりにコッカースパニエル犬をつかんでしまいました。
「その調子、その調子!」ガチョウのおばさんがさけびました。「もういちど、もういちど!」
「坂をくだるのよ!」雌牛たちが言いました。
「こっちへ逃げて来い!」がちょうのおじさんがどなりました。
「坂をのぼりなさい!」羊たちが叫びました。
「くるっと体をひねって!」ガチョウのおばさんががなりたてました。
「ジャンプしてはねるんだ!」おんどりが言いました。
「ラーヴィーに気をつけて!」雌牛たちが言いました。
「ザッカーマンに気をつけるんだ!」ガチョウのおじさんが叫びました。
「犬に注意して!」羊たちがどなりました。
「あたしのいうとおりに、いうとおりに!」ガチョウのおばさんが声を張り上げました。
やかましいさわぎに、あわれなウィルバーはすっかりのぼせあがり、怖くなってしまいました。自分のことで、誰もが大騒ぎしているのです。仲間の言うとおりにしようと思っても、坂を下るのと坂をのぼるのを同時にすることはできません。ジャンプしてはねているときに、くるっと体をひねることもできません。それに、ウィルバーは自分でも大声を出していたので、もう何が起こっているのか、よく分からなくなっていました。なんといっても、ウィルバーはまだ赤ちゃんといったっていいくらい、本当に小さいブタだったんですからね。ああ、ファーンがここにいて、だっこしてくれたらいいのになあ。
ふと顔をあげると、ザッカーマンのおじさんが、あたたかい残飯の入ったバケツを持って、すぐそばに立っていました。ウィルバーは、ほっとして鼻をもちあげ、クンクンとにおいをかぎました。美味しそうなにおいがします。あったかいミルクと、ジャガイモの皮と、フスマ飼料と、ケロッグのコーンフレークと、ザッカーマンさんたちが朝ごはんのときに食べ残したパンのにおいです。
「おいで!」と、ザッカーマンのおじさんが、バケツをトントンたたきながらいいました。
「さあ、おいで!」
ウィルバーは、バケツのほうに1歩足をふみだしました。
「だめ、だめ、だめ!餌でだまそうっていう手なのよ、ウィルバー。だまされないで、だまされないで!えさでさそって、またかこいにとじこめるつもりなのさ。ひっかかっちゃだめだよ。」ガチョウのおばさんがいいました。
ウィルバーは、もうそれでもかまいませんでした。なにしろバケツのなかからは、とてもいいにおいがしていたのです。そこれ、もう1歩バケツに近づきました。
「よしよし、ブタくん!」ザッカーマンのおじさんは、やさしい声でよびかけると、ゆっくりと納屋のまえのかこいのほうに歩いていきました。まるで、小さな白いブタが後ろからうしろからついてくるかどうかなど、まったく気にかけていない様子で、まわりを見渡しながら。
「後悔するよ、後悔、後悔。」ガチョウのおばさんが大声で言いました。
ウィルバーは、それでもかまいませんでした。残飯バケツのあとについて、どんどん歩いていきました。
「自由がなくなっちゃうんだよ。」ガチョウのおばさんが言いました。「自由な1時間は、バケツ1杯の残飯に負けないくらいすてきなのにさ。」
ウィルバーはそれでもかまいませんでした。
ザッカーマンのおじさんは、ブタのかこいまでやってくると、へいをまたいで、バケツの中の残飯をえさ箱にいれました。それから、ウィルバーをなかに入れるために、ぐらぐらになってぶらさがっていた板をへいからはずしました。
「考え直して、考え直して!」ガチョウのおばさんがさけびました。
ウィルバーは聞いていませんでした。へいにあいた穴から中に入り、えさ箱に近より、ズズズッと残飯をすすり、ミルクを飲み、パンをかみました。家に帰ってこられて、ほっとしていました。
ウィルバーが食べているあいだに、ラーヴィーがかなづちと釘を持っていき、へいに板を打ち付けました。それからザッカーマンのおじさんは、ラーヴィーと一緒にへいにゆったりとよりかかり、棒でウィルバーの背中をかいてやりました。
「こいつはなかなかのブタですね。」と、ラーヴィーはいいました。
「そうなだ。いいブタになるぞ。」と、ザッカーマンのおじさんはいいました。
ほめ言葉がウィルバーの耳に入りました。おなかの中には温かいミルクが流れ込んでいました。背中のかゆいとこを棒でかいてもらって、いい気持ちでした。穏やかで、しあわせで、ねむたくなってきました。なんといっても、午後の冒険でウィルバーはぐったり疲れていました。まだ4時にしかなっていませんでしたが、ウィルバーはもう眠かったのです。
「僕はまだ、ひとりで世界に出て行くには、小さすぎるんだな。」横になりながら、ウィルバーはそう思っていました。
Charlotte's Web 4