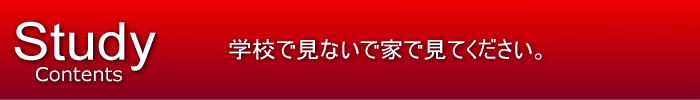Charlotte's Web 4
Ⅳ. Loneliness
(4.ひとりぼっち)
The next day was rainy and dark. Rain fell on the roof of the barn and dripped steadily from the eaves. Rain fell in the barnyard and ran in crooked courses down into the lane where thisles and pigweed grew. Rain spattered against Mrs.Zuckerman's kitchen windows and came gushing out of the downspouts. Rain fell on the backs of the sheep as they grazed in the meadow. When the sheep tired of standing in the rain, they walked slowly up the lane and into the fold.
(翌日は、雨が降って、どんよりしていました。納屋の屋根を雨が叩き、ひさしからは、ポタポタ雨だれが、落ちてきます。納屋の前庭に降った雨は、曲がりくねりながら、アザミや、アカザの生えている小道まで流れていきました。雨は、ザッカーマンさんの台所の窓を打ち、雨どいからもほとばしりでていました。雨は、牧場で草を食べている羊たちの背中を濡らしました。羊たちは、雨にうんざりすると、小道を歩いてきて、屋根の下に入りました。)
Rain upset Wilbur's plans. Wilbur had planned to go out, this day, and dig a new hole in his yard. He had other plans, too. His plans for the day went something like this:
(雨のせいで、ウィルバーの予定は、狂ってしまいました。今日は、外の囲いに出て、新しい穴を掘ろうと思っていたのです。他にも、やりたいことがいろいろありました。予定は、こうでした。)
Breakfast at six-thirty. Skim milk, crusts, middlings, bits of doughnuts, wheat cakes with drops of maple syrup sticking to them, potato skins, leftover custard pudding with raisins, and bits of Shredded Wheat.
(6時半に朝ごはん。スキムミルク、パンの皮、ふすま飼料、ドーナツのかけら、メイプルシロップのついたホットケーキ、ジャガイモの皮、干しブドウ入りのプリンののこり、小麦のシリアルを食べる。)
Breakfast would be finished at seven
(7時に朝ごはんを終える。)
From seven to eight, Wilbur planned to have a talk with Templeton, the rat that lived under his trough. Talking with Templeton was not the most interesting occupation in the wrold but it was better than nothing.
(7時から8時は、餌箱の下で暮しているねずみのテンプルトンとおしゃべりをする。テンプルトンと話をするのは、世界一面白いとは、言えませんが、何もないよりはマシです。)
From eight to nine, Wilbur planned to take a nap outdoors in the sun.
(8時~9時は、外で、日向ぼっこをしながら、一眠り。)
From nine to eleven he planned to dig a hole, or trench, and possibly find something good to eat buried in the dirt.
(9時から11時は、穴かみぞを掘って、ひょっとしたら出てくるかもしれない、おいしいものを探す。)
From eleven to twelve he planned to stand still and watch flies on the boards, watch bees in the clover, and watch swallows in the air.
(11時~12時は、じっと立って板に止まるハエや、クローバーに止まる蜂や、空を飛ぶツバメを見る。)
Twelve o'clock--lunchtime. Middlings, warm water, apple parings, meat gravy, carrot scrapings, meat scraps, stale hominy, and the wrapper off a package of cheese. Lunch would be over at one.
(12時には、昼ごはん。フスマ飼料、お湯、りんごのくず、肉汁、にんじんの皮、肉の切れ端、硬くなったとうもろこし、チーズの外包みを食べる。昼ごはんは、1時に終わる。)
From one to two, Wilbur planned to sleep.
(1時~2時は、お昼寝。)
From two to three, he planned to scratch itchy places by rubbing against the fence.
(2時~3時は、かゆいところを、壁にこすりつける。)
From three to four, he planned to stand perfectly still and think of what it was like to be alive, and to wait for Fern.
(3時~4時は、じっと立ち尽くして、生きているということは、どういうことかを考えながら、ファーンがくるのを待つ。)
At four would come supper. Skim milk, provender, leftover sandwich from Lurvy's lunchbox, prune skins, a morsel of this, a little more of this, a little more of that, piece of baked apple, a scrap of upsidedown cake.
(4時には、夕ご飯。スキムミルク、飼料、ラーヴィーのお弁当のサンドイッチの残り、プルーンの皮、いろんなものを、ひと口ふた口、ポテトフライ、マーマレードをちょっぴり、いろんなものを更にひと口ふた口、焼きりんごのかけら、アプサイドダウンケーキのくずを食べる。)
Wilbur had gone to sleep thinking about these plans. He awoke at six and saw the rain, and it seemed as though he couldn't bear it.
(ウィルバーは、前の晩にこうした予定をしっかり立てて寝たのです。ところが、6時に目を覚ましてみると、雨が降っているではありませんか。何てことでしょう。)
"I get everything all beautifully planned out and it has to go and rain," he said.
(「せっかくきちんと予定を立てたのに、雨で台無しになってしまった。」)
For a while he stood gloomily indoors. Then he walked to the door and looked out. Drops of rain struck his face. His yard was cold and wet. His trough had an inch of rainwater in it. Templeton was nowhere to be seen.
(しばらくの間、ウィルバーは、堆肥の上で、しょんぼりしていました。それから戸口までいって、外を見ました。それから、戸口まで行って、外を見ました。雨が顔に当たります。前庭は、寒くてビショビショでした。餌箱の底にも、2、3センチほど水がたまっています。テンプルトンの姿も見えません。)
"Are you out there, Templeton?" called Wilbur. There was no answer. Suddenly Wilbur felt lonely and friendless.
(「テンプルトンいるのかい?」ウィルバーは、声をかけました。答えはありません。急にウィルバーは、友達のいない寂しさを感じました。)
"One day just like another," he groaned. "I'm very young, I have no real friend here in the barn, it's going to rain all morning and all afternoon, and Fern won't come in such bad weather. Oh, honestly!" And Wilbur was crying again, for the second time in two days.
(「来る日も来る日も同じだ。」ウィルバーは、うめきました。「僕は、まだ小さいし、この納屋には、本当の友達はいないし、今日は、一日中雨が降り続きそうだし、こんなにひどい天気じゃ、ファーンも着てくれないだろうな。ああ、やんなっちゃうな!!」ウィルバーは、昨日も泣いたばかりなのに、また泣き始めてしまいました。)
At six-thirty Wilbur heard the banging of a pail. Lurvy was standing outside in the rain, stirring up breakfast.
(6時半にもなると、バケツがガチャガチャ言う音が聞こえてきました。ラーヴィーが雨の中に立って、朝ごはんの残飯を混ぜているのです。)
"C'mon, pig!" said Lurvy.
(「さぁ、食べろよ。」とラーヴィーは、言いました。)
Wilbur did not budge. Lurvy dumped the slops, scraped the pail, and walked away. He noticed that something was wrong with the pig.
(ウィルバーは、動きませんでした。ラーヴィーは、残飯を餌箱にあけ、バケツの底についているのをかき出すと、戻って行きましたが、豚の様子が、いつもと違うなと思っていました。)
Wilbur didn't want food, he wanted love. He wanted a friend--someone who would play with him. He mentioned this to the goose, who was sitting quietly in a corner of the sheepfold.
(ウィルバーがほしいのは、食べ物ではなく、愛情だったのです。一緒に遊んでくれる友達がほしかったのです。羊の部屋で静かに座っているガチョウのおばさんに、ウィルバーは、聞きました。)
"Will you come over and play with me?" he asked.
(「こっちにきて、一緒に遊んでくれない?」)
"Sorry, sonny, sorry," said the goose. "I'm sitting-sitting on my eggs. Eight of them. Got to keep them toasty-oasty-oasty warm. I have to stay right here, I'm no fibberty-ibberty-gibbet. I do not play when there are eggs to hatch. I'm expecting goslings."
(「ごめんね坊や。ごめんね。」と、ガチョウのおばさんは、言いました。「私は、たまごを温めてるところなの。全部で8個もね。温かく温かくしておかなければならないんだよ。だから、ここでじっとしていなきゃね。遊んでる暇は、ないんだよ。たまごが孵るまではね。ガチョウの赤ちゃんが生まれるまでは。」)
"Well, I didn't think you were expecting wood-peckers," said Wilbur, bitterly.
(「そりゃ僕だって、キツツキの赤ちゃんが生まれてくるとは、思ってないけどね。」と、ウィルバーは、がっかりしながら言いました。)
Wilbur next tried one of the lambs.
(次にウィルバーは子羊にも声をかけました。)
"Will you please play with me?" he asked.
(「ねぇ僕と遊んでくれない?」)
"Certainly not," said the lamb. "In the first place, I cannot get into your pen, as I am not old enough to jump over the fence. In the second place, I am not interested in pigs. Pigs mean less than nothing to me."
(「嫌だね。それに第一僕は、そっちには行けないよ。まだ小さくて、塀を飛び越えることが、できないもの。それに、僕は、豚には、興味ないんだ。僕にとっちゃ豚なんて、ゼロ以下のつまらないものだね。」と子羊が言いました。)
"What do you mean, less than nothing?" replied Wilbur. "I don't think there is any such things as less than nothing. Nothing is absolutely the limit of nothingness. It's the lowest you can go. It's the end of the line. How can something be less than nothing, then nothing would not be nothing, it would be something--even though it's just a very little bit of something. But if nothing is nothing, then nothing has nothing that is less than it is."
(「ゼロ以下ってどういうことなの?」と、ウィルバーは、訊きました。「僕、ゼロ以下のものなんて、無いと思うな。ゼロって、全くなんにもないことでしょ?それよりも下のものなんてないはずだよ。どうやったら、ゼロ以下になれるのさ?もし何にも無いよりももっと無いってことがあるなら、それなら元々は、何も無かったんでしょ?ほんのちょっぴりにしろ、何かは、あるってことでしょ?でも、本当に何も無いなら、それより少なくは、なりようが、無いもの。」)
"Oh, be quiet!" said the lamb. "Go play by yourself! i don't play with pigs."
(「あー、うるさいな!!! 1人で遊びなよ! 僕は、豚なんかと遊ばないんだから。」と子羊は、言いました。)
Sadly, Wilbur lay down and listened to the rain. Soon he saw the rat climbing down a slanting board that he used as a stairway.
(ウィルバーは、しょんぼりと横になり、雨の音を聞いていました。するとまもなく、ねずみが1匹階段代わりに使っている、斜めの板を降りてきました。)
"Will you play with me, Templeton?" asked Wilbur.
(「ねぇ、テンプルトン。僕と遊ばない?」と、ウィルバーは、尋ねました。)
"Play?" said Templeton, twirling his whiskers. "Play? I hardly know the meaning of the word."
(「遊ぶだって?」と、テンプルトンは、髭をひねりながら、言いました。「遊ぶ? はてさてそれは、どういう意味だったかな?」)
"Well," said Wilbur, "it means to have fun, to frolic, to run and skip and make merry."
(「あのね、遊ぶって、面白いことをしたり、うかれて騒いだり、走ったり、スキップしたり、陽気に楽しんだりすることだよ。」と、ウィルバーは言いました。)
"I never do those things if I can avoid them," replied the rat, sourly. "I prefer to spend my time eating, gnawing, spying, and hiding. I am a glutton but not a merrymaker. Right now I am on way to your trough to eat your breakfast, since you haven't got sense enough to eat it yourself." And Templeton, the rat, cept stealthily along the wall and disappeared into a private tunnel that he had dug between the door and the trough in Wilbur's yard. Templeton was a crafty rat, and he had things pretty much his own way. The tunnel was an example of his skill and cunning. The tunnel enabled him to get from the barn to his hiding place under the pig trough without coming out into the open. He had tunnels and runways all over Mr.Zuckerman's farm and could get from one place to another without being seen. Usually he slept during the daytime and was abroad only after dark.
(「俺は、そんなことは、しなくていいならしないね。」ネズミは、機嫌の悪そうな声で、こたえました。「そんな時間があるなら、食べたり、かじったり、探したり、隠れたりしているほうが、よっぽどいいさ。俺は、うかれ屋じゃなくて、食いしん坊なんでね。たった今も、君の朝ごはんが入った餌箱まで、行くとこさ。君は、ぼんやりしてて、ご飯も食べないらしいからね。」ネズミのテンプルトンは、壁をつたって、自分専用のトンネルの中に、姿を消しました。戸口と、ウィルバーに餌箱の間に、自分で掘ったトンネルです。テンプルトンは、なかなか頭の働くネズミで、自分勝手にいろいろな工夫をしていました。このトンネルも、テンプルトンの悪知恵と腕のよさがあらわれた、いい例でした。このトンネルをくぐれば、納屋からブタのえさ箱の下にあるかくれ家まで、誰にも見られずに行くことができました。テンプルトンは、ザッカーマン農場中にトンネルや通路を張り巡らせていて、姿を隠したまま、あっちこっちへ行くことができたのです。たいていテンプルトンは、昼間は寝ていて、暗くなってから外へ出てきました。)
Wilbur watched him disappear into his tunnel. In a moment he saw the rat's sharp nose poke out from underneath the wooden trough. Cautiously Templeton pulled himself up over the edge of the trough. This was almost more than Wilbur could stand: on this dreary, rainy day to see his breakfast being eaten by somebody else. He knew Templeton was getting soaked, out there in the pouring rain, but even that didn't comfort him. Friendless, dejected, and hungry, he threw himself down in the manure and sobbed.
(テンプルトンは、トンネルの中に消えたかと思うと、すぐにえさ箱のしたからとがった鼻先をのぞかせました。そして、用心深しながら箱のふちを登りました。ウィルバーは、もう我慢できませんでした。雨がしょぼしょぼふってるだけでもいやなのに、朝ごはんまで横取りされてしまったのです。どしゃぶりの雨に、テンプルトンはきっとずぶぬれになるでしょう。でも、そう思ったところで、なぐさめにはなりませんでした。おなかを空かせて、しょんぼりとした、友達のいないウィルバーは、堆肥に身を投げ出して、しくしく泣き出しました。)
Late that afternoon, Lurvy went to Mr.Zuckerman. "I think there's something wrong with that pig of yours. He hasn't touched his food."
(午後も遅くなってから、ラーヴィーがザッカーマンさんに言いました。「あのブタは、どっか具合がわるいんじゃないですかね。なんにも食べてくれませんよ。」)
"Give him two spoonfuls of sulphur and a little molassws," said Mr.Zuckerman.
(「硫黄ふたさじに、ちょぴっと糖蜜をまぜて、のませてくれ。」と、ザッカーマンのおじさんは言いました。)
Wilbur couldn't believe what was happening to him when Lurvy caught him and forced the medicine down his throat. This was certainly the worst day of his life. He didn't know whether he could endure the awful loneliness any more.
(ラーヴィーにつかまって、むりやり薬をつっこまれたとき、ウィルバーはどうしてこんなにひどい目にあうのか、信じられませんでした。たしかに、生涯最悪の日に違いありません。ひとりぼっちの寂しさにも、これ以上もうたえられそうにありませんでした。)
Darkness settled over everything. Soon there were only shadows and the noises of the sheep chewing their cuds, and occasionally the rattle of a cow-chain up overhead. You can imagine Wilbur's surprise when, out of the darkness, came a small voice he had never heard before. It sounded rather thin, but pleasant. "Do you want a friend, Wilbur?" it said. "I'll be a friend to you. I've watched you all day and I like you."
(やがて、あたりはとっぷりと暗くなりました。もう羊の姿も影絵のようにしか見えず、聞こえるのは、羊が食べ戻しをするクチャクチャという音や、頭上でときどき雌牛のくさりがガチャガチャ鳴る音くらいでした。そんな暗闇の中から、これまできいたことのない小さな声が聞こえてきたのですから、ウィルバーがどんなにびっくりしたか、分かりますよね。かぼそいけれど、愛想のいい声でした。「ねえ、ウィルバー、友達が欲しいの?わたし、お友達になってあげるわ。1日中見てたら、あなたのことすきになっちゃったの。」と、声の主は言いました。ウィルバーはあわてて立ち上がって、いいました。)
"But I can't see you," said Wilbur, jumping to his feet. "Where are you? And who are you?"
(「でも、僕には君が見えないよ。どこにいるの?だれなの?」)
"I'm right up here," said the voice. "Go to sleep. You'll see me in the morning."
(「わたしは、上にいるの。おやすみなさい。朝になったら会いましょうね。」と、その声はこたえました。)
英文のみです。
日本語訳のみです。
Charlotte's Web 5
(4.ひとりぼっち)
The next day was rainy and dark. Rain fell on the roof of the barn and dripped steadily from the eaves. Rain fell in the barnyard and ran in crooked courses down into the lane where thisles and pigweed grew. Rain spattered against Mrs.Zuckerman's kitchen windows and came gushing out of the downspouts. Rain fell on the backs of the sheep as they grazed in the meadow. When the sheep tired of standing in the rain, they walked slowly up the lane and into the fold.
(翌日は、雨が降って、どんよりしていました。納屋の屋根を雨が叩き、ひさしからは、ポタポタ雨だれが、落ちてきます。納屋の前庭に降った雨は、曲がりくねりながら、アザミや、アカザの生えている小道まで流れていきました。雨は、ザッカーマンさんの台所の窓を打ち、雨どいからもほとばしりでていました。雨は、牧場で草を食べている羊たちの背中を濡らしました。羊たちは、雨にうんざりすると、小道を歩いてきて、屋根の下に入りました。)
Rain upset Wilbur's plans. Wilbur had planned to go out, this day, and dig a new hole in his yard. He had other plans, too. His plans for the day went something like this:
(雨のせいで、ウィルバーの予定は、狂ってしまいました。今日は、外の囲いに出て、新しい穴を掘ろうと思っていたのです。他にも、やりたいことがいろいろありました。予定は、こうでした。)
Breakfast at six-thirty. Skim milk, crusts, middlings, bits of doughnuts, wheat cakes with drops of maple syrup sticking to them, potato skins, leftover custard pudding with raisins, and bits of Shredded Wheat.
(6時半に朝ごはん。スキムミルク、パンの皮、ふすま飼料、ドーナツのかけら、メイプルシロップのついたホットケーキ、ジャガイモの皮、干しブドウ入りのプリンののこり、小麦のシリアルを食べる。)
Breakfast would be finished at seven
(7時に朝ごはんを終える。)
From seven to eight, Wilbur planned to have a talk with Templeton, the rat that lived under his trough. Talking with Templeton was not the most interesting occupation in the wrold but it was better than nothing.
(7時から8時は、餌箱の下で暮しているねずみのテンプルトンとおしゃべりをする。テンプルトンと話をするのは、世界一面白いとは、言えませんが、何もないよりはマシです。)
From eight to nine, Wilbur planned to take a nap outdoors in the sun.
(8時~9時は、外で、日向ぼっこをしながら、一眠り。)
From nine to eleven he planned to dig a hole, or trench, and possibly find something good to eat buried in the dirt.
(9時から11時は、穴かみぞを掘って、ひょっとしたら出てくるかもしれない、おいしいものを探す。)
From eleven to twelve he planned to stand still and watch flies on the boards, watch bees in the clover, and watch swallows in the air.
(11時~12時は、じっと立って板に止まるハエや、クローバーに止まる蜂や、空を飛ぶツバメを見る。)
Twelve o'clock--lunchtime. Middlings, warm water, apple parings, meat gravy, carrot scrapings, meat scraps, stale hominy, and the wrapper off a package of cheese. Lunch would be over at one.
(12時には、昼ごはん。フスマ飼料、お湯、りんごのくず、肉汁、にんじんの皮、肉の切れ端、硬くなったとうもろこし、チーズの外包みを食べる。昼ごはんは、1時に終わる。)
From one to two, Wilbur planned to sleep.
(1時~2時は、お昼寝。)
From two to three, he planned to scratch itchy places by rubbing against the fence.
(2時~3時は、かゆいところを、壁にこすりつける。)
From three to four, he planned to stand perfectly still and think of what it was like to be alive, and to wait for Fern.
(3時~4時は、じっと立ち尽くして、生きているということは、どういうことかを考えながら、ファーンがくるのを待つ。)
At four would come supper. Skim milk, provender, leftover sandwich from Lurvy's lunchbox, prune skins, a morsel of this, a little more of this, a little more of that, piece of baked apple, a scrap of upsidedown cake.
(4時には、夕ご飯。スキムミルク、飼料、ラーヴィーのお弁当のサンドイッチの残り、プルーンの皮、いろんなものを、ひと口ふた口、ポテトフライ、マーマレードをちょっぴり、いろんなものを更にひと口ふた口、焼きりんごのかけら、アプサイドダウンケーキのくずを食べる。)
Wilbur had gone to sleep thinking about these plans. He awoke at six and saw the rain, and it seemed as though he couldn't bear it.
(ウィルバーは、前の晩にこうした予定をしっかり立てて寝たのです。ところが、6時に目を覚ましてみると、雨が降っているではありませんか。何てことでしょう。)
"I get everything all beautifully planned out and it has to go and rain," he said.
(「せっかくきちんと予定を立てたのに、雨で台無しになってしまった。」)
For a while he stood gloomily indoors. Then he walked to the door and looked out. Drops of rain struck his face. His yard was cold and wet. His trough had an inch of rainwater in it. Templeton was nowhere to be seen.
(しばらくの間、ウィルバーは、堆肥の上で、しょんぼりしていました。それから戸口までいって、外を見ました。それから、戸口まで行って、外を見ました。雨が顔に当たります。前庭は、寒くてビショビショでした。餌箱の底にも、2、3センチほど水がたまっています。テンプルトンの姿も見えません。)
"Are you out there, Templeton?" called Wilbur. There was no answer. Suddenly Wilbur felt lonely and friendless.
(「テンプルトンいるのかい?」ウィルバーは、声をかけました。答えはありません。急にウィルバーは、友達のいない寂しさを感じました。)
"One day just like another," he groaned. "I'm very young, I have no real friend here in the barn, it's going to rain all morning and all afternoon, and Fern won't come in such bad weather. Oh, honestly!" And Wilbur was crying again, for the second time in two days.
(「来る日も来る日も同じだ。」ウィルバーは、うめきました。「僕は、まだ小さいし、この納屋には、本当の友達はいないし、今日は、一日中雨が降り続きそうだし、こんなにひどい天気じゃ、ファーンも着てくれないだろうな。ああ、やんなっちゃうな!!」ウィルバーは、昨日も泣いたばかりなのに、また泣き始めてしまいました。)
At six-thirty Wilbur heard the banging of a pail. Lurvy was standing outside in the rain, stirring up breakfast.
(6時半にもなると、バケツがガチャガチャ言う音が聞こえてきました。ラーヴィーが雨の中に立って、朝ごはんの残飯を混ぜているのです。)
"C'mon, pig!" said Lurvy.
(「さぁ、食べろよ。」とラーヴィーは、言いました。)
Wilbur did not budge. Lurvy dumped the slops, scraped the pail, and walked away. He noticed that something was wrong with the pig.
(ウィルバーは、動きませんでした。ラーヴィーは、残飯を餌箱にあけ、バケツの底についているのをかき出すと、戻って行きましたが、豚の様子が、いつもと違うなと思っていました。)
Wilbur didn't want food, he wanted love. He wanted a friend--someone who would play with him. He mentioned this to the goose, who was sitting quietly in a corner of the sheepfold.
(ウィルバーがほしいのは、食べ物ではなく、愛情だったのです。一緒に遊んでくれる友達がほしかったのです。羊の部屋で静かに座っているガチョウのおばさんに、ウィルバーは、聞きました。)
"Will you come over and play with me?" he asked.
(「こっちにきて、一緒に遊んでくれない?」)
"Sorry, sonny, sorry," said the goose. "I'm sitting-sitting on my eggs. Eight of them. Got to keep them toasty-oasty-oasty warm. I have to stay right here, I'm no fibberty-ibberty-gibbet. I do not play when there are eggs to hatch. I'm expecting goslings."
(「ごめんね坊や。ごめんね。」と、ガチョウのおばさんは、言いました。「私は、たまごを温めてるところなの。全部で8個もね。温かく温かくしておかなければならないんだよ。だから、ここでじっとしていなきゃね。遊んでる暇は、ないんだよ。たまごが孵るまではね。ガチョウの赤ちゃんが生まれるまでは。」)
"Well, I didn't think you were expecting wood-peckers," said Wilbur, bitterly.
(「そりゃ僕だって、キツツキの赤ちゃんが生まれてくるとは、思ってないけどね。」と、ウィルバーは、がっかりしながら言いました。)
Wilbur next tried one of the lambs.
(次にウィルバーは子羊にも声をかけました。)
"Will you please play with me?" he asked.
(「ねぇ僕と遊んでくれない?」)
"Certainly not," said the lamb. "In the first place, I cannot get into your pen, as I am not old enough to jump over the fence. In the second place, I am not interested in pigs. Pigs mean less than nothing to me."
(「嫌だね。それに第一僕は、そっちには行けないよ。まだ小さくて、塀を飛び越えることが、できないもの。それに、僕は、豚には、興味ないんだ。僕にとっちゃ豚なんて、ゼロ以下のつまらないものだね。」と子羊が言いました。)
"What do you mean, less than nothing?" replied Wilbur. "I don't think there is any such things as less than nothing. Nothing is absolutely the limit of nothingness. It's the lowest you can go. It's the end of the line. How can something be less than nothing, then nothing would not be nothing, it would be something--even though it's just a very little bit of something. But if nothing is nothing, then nothing has nothing that is less than it is."
(「ゼロ以下ってどういうことなの?」と、ウィルバーは、訊きました。「僕、ゼロ以下のものなんて、無いと思うな。ゼロって、全くなんにもないことでしょ?それよりも下のものなんてないはずだよ。どうやったら、ゼロ以下になれるのさ?もし何にも無いよりももっと無いってことがあるなら、それなら元々は、何も無かったんでしょ?ほんのちょっぴりにしろ、何かは、あるってことでしょ?でも、本当に何も無いなら、それより少なくは、なりようが、無いもの。」)
"Oh, be quiet!" said the lamb. "Go play by yourself! i don't play with pigs."
(「あー、うるさいな!!! 1人で遊びなよ! 僕は、豚なんかと遊ばないんだから。」と子羊は、言いました。)
Sadly, Wilbur lay down and listened to the rain. Soon he saw the rat climbing down a slanting board that he used as a stairway.
(ウィルバーは、しょんぼりと横になり、雨の音を聞いていました。するとまもなく、ねずみが1匹階段代わりに使っている、斜めの板を降りてきました。)
"Will you play with me, Templeton?" asked Wilbur.
(「ねぇ、テンプルトン。僕と遊ばない?」と、ウィルバーは、尋ねました。)
"Play?" said Templeton, twirling his whiskers. "Play? I hardly know the meaning of the word."
(「遊ぶだって?」と、テンプルトンは、髭をひねりながら、言いました。「遊ぶ? はてさてそれは、どういう意味だったかな?」)
"Well," said Wilbur, "it means to have fun, to frolic, to run and skip and make merry."
(「あのね、遊ぶって、面白いことをしたり、うかれて騒いだり、走ったり、スキップしたり、陽気に楽しんだりすることだよ。」と、ウィルバーは言いました。)
"I never do those things if I can avoid them," replied the rat, sourly. "I prefer to spend my time eating, gnawing, spying, and hiding. I am a glutton but not a merrymaker. Right now I am on way to your trough to eat your breakfast, since you haven't got sense enough to eat it yourself." And Templeton, the rat, cept stealthily along the wall and disappeared into a private tunnel that he had dug between the door and the trough in Wilbur's yard. Templeton was a crafty rat, and he had things pretty much his own way. The tunnel was an example of his skill and cunning. The tunnel enabled him to get from the barn to his hiding place under the pig trough without coming out into the open. He had tunnels and runways all over Mr.Zuckerman's farm and could get from one place to another without being seen. Usually he slept during the daytime and was abroad only after dark.
(「俺は、そんなことは、しなくていいならしないね。」ネズミは、機嫌の悪そうな声で、こたえました。「そんな時間があるなら、食べたり、かじったり、探したり、隠れたりしているほうが、よっぽどいいさ。俺は、うかれ屋じゃなくて、食いしん坊なんでね。たった今も、君の朝ごはんが入った餌箱まで、行くとこさ。君は、ぼんやりしてて、ご飯も食べないらしいからね。」ネズミのテンプルトンは、壁をつたって、自分専用のトンネルの中に、姿を消しました。戸口と、ウィルバーに餌箱の間に、自分で掘ったトンネルです。テンプルトンは、なかなか頭の働くネズミで、自分勝手にいろいろな工夫をしていました。このトンネルも、テンプルトンの悪知恵と腕のよさがあらわれた、いい例でした。このトンネルをくぐれば、納屋からブタのえさ箱の下にあるかくれ家まで、誰にも見られずに行くことができました。テンプルトンは、ザッカーマン農場中にトンネルや通路を張り巡らせていて、姿を隠したまま、あっちこっちへ行くことができたのです。たいていテンプルトンは、昼間は寝ていて、暗くなってから外へ出てきました。)
Wilbur watched him disappear into his tunnel. In a moment he saw the rat's sharp nose poke out from underneath the wooden trough. Cautiously Templeton pulled himself up over the edge of the trough. This was almost more than Wilbur could stand: on this dreary, rainy day to see his breakfast being eaten by somebody else. He knew Templeton was getting soaked, out there in the pouring rain, but even that didn't comfort him. Friendless, dejected, and hungry, he threw himself down in the manure and sobbed.
(テンプルトンは、トンネルの中に消えたかと思うと、すぐにえさ箱のしたからとがった鼻先をのぞかせました。そして、用心深しながら箱のふちを登りました。ウィルバーは、もう我慢できませんでした。雨がしょぼしょぼふってるだけでもいやなのに、朝ごはんまで横取りされてしまったのです。どしゃぶりの雨に、テンプルトンはきっとずぶぬれになるでしょう。でも、そう思ったところで、なぐさめにはなりませんでした。おなかを空かせて、しょんぼりとした、友達のいないウィルバーは、堆肥に身を投げ出して、しくしく泣き出しました。)
Late that afternoon, Lurvy went to Mr.Zuckerman. "I think there's something wrong with that pig of yours. He hasn't touched his food."
(午後も遅くなってから、ラーヴィーがザッカーマンさんに言いました。「あのブタは、どっか具合がわるいんじゃないですかね。なんにも食べてくれませんよ。」)
"Give him two spoonfuls of sulphur and a little molassws," said Mr.Zuckerman.
(「硫黄ふたさじに、ちょぴっと糖蜜をまぜて、のませてくれ。」と、ザッカーマンのおじさんは言いました。)
Wilbur couldn't believe what was happening to him when Lurvy caught him and forced the medicine down his throat. This was certainly the worst day of his life. He didn't know whether he could endure the awful loneliness any more.
(ラーヴィーにつかまって、むりやり薬をつっこまれたとき、ウィルバーはどうしてこんなにひどい目にあうのか、信じられませんでした。たしかに、生涯最悪の日に違いありません。ひとりぼっちの寂しさにも、これ以上もうたえられそうにありませんでした。)
Darkness settled over everything. Soon there were only shadows and the noises of the sheep chewing their cuds, and occasionally the rattle of a cow-chain up overhead. You can imagine Wilbur's surprise when, out of the darkness, came a small voice he had never heard before. It sounded rather thin, but pleasant. "Do you want a friend, Wilbur?" it said. "I'll be a friend to you. I've watched you all day and I like you."
(やがて、あたりはとっぷりと暗くなりました。もう羊の姿も影絵のようにしか見えず、聞こえるのは、羊が食べ戻しをするクチャクチャという音や、頭上でときどき雌牛のくさりがガチャガチャ鳴る音くらいでした。そんな暗闇の中から、これまできいたことのない小さな声が聞こえてきたのですから、ウィルバーがどんなにびっくりしたか、分かりますよね。かぼそいけれど、愛想のいい声でした。「ねえ、ウィルバー、友達が欲しいの?わたし、お友達になってあげるわ。1日中見てたら、あなたのことすきになっちゃったの。」と、声の主は言いました。ウィルバーはあわてて立ち上がって、いいました。)
"But I can't see you," said Wilbur, jumping to his feet. "Where are you? And who are you?"
(「でも、僕には君が見えないよ。どこにいるの?だれなの?」)
"I'm right up here," said the voice. "Go to sleep. You'll see me in the morning."
(「わたしは、上にいるの。おやすみなさい。朝になったら会いましょうね。」と、その声はこたえました。)
英文のみです。
Ⅳ. Loneliness
The next day was rainy and dark. Rain fell on the roof of the barn and dripped steadily from the eaves. Rain fell in the barnyard and ran in crooked courses down into the lane where thisles and pigweed grew. Rain spattered against Mrs.Zuckerman's kitchen windows and came gushing out of the downspouts. Rain fell on the backs of the sheep as they grazed in the meadow. When the sheep tired of standing in the rain, they walked slowly up the lane and into the fold.
Rain upset Wilbur's plans. Wilbur had planned to go out, this day, and dig a new hole in his yard. He had other plans, too. His plans for the day went something like this:
Breakfast at six-thirty. Skim milk, crusts, middlings, bits of doughnuts, wheat cakes with drops of maple syrup sticking to them, potato skins, leftover custard pudding with raisins, and bits of Shredded Wheat.
Breakfast would be finished at seven
From seven to eight, Wilbur planned to have a talk with Templeton, the rat that lived under his trough. Talking with Templeton was not the most interesting occupation in the wrold but it was better than nothing.
From eight to nine, Wilbur planned to take a nap outdoors in the sun.
From nine to eleven he planned to dig a hole, or trench, and possibly find something good to eat buried in the dirt.
From eleven to twelve he planned to stand still and watch flies on the boards, watch bees in the clover, and watch swallows in the air.
Twelve o'clock--lunchtime. Middlings, warm water, apple parings, meat gravy, carrot scrapings, meat scraps, stale hominy, and the wrapper off a package of cheese. Lunch would be over at one.
From one to two, Wilbur planned to sleep.
From two to three, he planned to scratch itchy places by rubbing against the fence.
From three to four, he planned to stand perfectly still and think of what it was like to be alive, and to wait for Fern.
At four would come supper. Skim milk, provender, leftover sandwich from Lurvy's lunchbox, prune skins, a morsel of this, a little more of this, a little more of that, piece of baked apple, a scrap of upsidedown cake.
Wilbur had gone to sleep thinking about these plans. He awoke at six and saw the rain, and it seemed as though he couldn't bear it.
"I get everything all beautifully planned out and it has to go and rain," he said.
For a while he stood gloomily indoors. Then he walked to the door and looked out. Drops of rain struck his face. His yard was cold and wet. His trough had an inch of rainwater in it. Templeton was nowhere to be seen.
"Are you out there, Templeton?" called Wilbur. There was no answer. Suddenly Wilbur felt lonely and friendless.
"One day just like another," he groaned. "I'm very young, I have no real friend here in the barn, it's going to rain all morning and all afternoon, and Fern won't come in such bad weather. Oh, honestly!" And Wilbur was crying again, for the second time in two days.
At six-thirty Wilbur heard the banging of a pail. Lurvy was standing outside in the rain, stirring up breakfast.
"C'mon, pig!" said Lurvy.
Wilbur did not budge. Lurvy dumped the slops, scraped the pail, and walked away. He noticed that something was wrong with the pig.
Wilbur didn't want food, he wanted love. He wanted a friend--someone who would play with him. He mentioned this to the goose, who was sitting quietly in a corner of the sheepfold.
"Will you come over and play with me?" he asked.
"Sorry, sonny, sorry," said the goose. "I'm sitting-sitting on my eggs. Eight of them. Got to keep them toasty-oasty-oasty warm. I have to stay right here, I'm no fibberty-ibberty-gibbet. I do not play when there are eggs to hatch. I'm expecting goslings."
"Well, I didn't think you were expecting wood-peckers," said Wilbur, bitterly.
Wilbur next tried one of the lambs.
"Will you please play with me?" he asked.
"Certainly not," said the lamb. "In the first place, I cannot get into your pen, as I am not old enough to jump over the fence. In the second place, I am not interested in pigs. Pigs mean less than nothing to me."
"What do you mean, less than nothing?" replied Wilbur. "I don't think there is any such things as less than nothing. Nothing is absolutely the limit of nothingness. It's the lowest you can go. It's the end of the line. How can something be less than nothing, then nothing would not be nothing, it would be something--even though it's just a very little bit of something. But if nothing is nothing, then nothing has nothing that is less than it is."
"Oh, be quiet!" said the lamb. "Go play by yourself! i don't play with pigs."
Sadly, Wilbur lay down and listened to the rain. Soon he saw the rat climbing down a slanting board that he used as a stairway.
"Will you play with me, Templeton?" asked Wilbur.
"Play?" said Templeton, twirling his whiskers. "Play? I hardly know the meaning of the word."
"Well," said Wilbur, "it means to have fun, to frolic, to run and skip and make merry."
"I never do those things if I can avoid them," replied the rat, sourly. "I prefer to spend my time eating, gnawing, spying, and hiding. I am a glutton but not a merrymaker. Right now I am on way to your trough to eat your breakfast, since you haven't got sense enough to eat it yourself." And Templeton, the rat, cept stealthily along the wall and disappeared into a private tunnel that he had dug between the door and the trough in Wilbur's yard. Templeton was a crafty rat, and he had things pretty much his own way. The tunnel was an example of his skill and cunning. The tunnel enabled him to get from the barn to his hiding place under the pig trough without coming out into the open. He had tunnels and runways all over Mr.Zuckerman's farm and could get from one place to another without being seen. Usually he slept during the daytime and was abroad only after dark.
Wilbur watched him disappear into his tunnel. In a moment he saw the rat's sharp nose poke out from underneath the wooden trough. Cautiously Templeton pulled himself up over the edge of the trough. This was almost more than Wilbur could stand: on this dreary, rainy day to see his breakfast being eaten by somebody else. He knew Templeton was getting soaked, out there in the pouring rain, but even that didn't comfort him. Friendless, dejected, and hungry, he threw himself down in the manure and sobbed.
Late that afternoon, Lurvy went to Mr.Zuckerman. "I think there's something wrong with that pig of yours. He hasn't touched his food."
"Give him two spoonfuls of sulphur and a little molassws," said Mr.Zuckerman.
Wilbur couldn't believe what was happening to him when Lurvy caught him and forced the medicine down his throat. This was certainly the worst day of his life. He didn't know whether he could endure the awful loneliness any more.
Darkness settled over everything. Soon there were only shadows and the noises of the sheep chewing their cuds, and occasionally the rattle of a cow-chain up overhead. You can imagine Wilbur's surprise when, out of the darkness, came a small voice he had never heard before. It sounded rather thin, but pleasant. "Do you want a friend, Wilbur?" it said. "I'll be a friend to you. I've watched you all day and I like you."
"But I can't see you," said Wilbur, jumping to his feet. "Where are you? And who are you?"
"I'm right up here," said the voice. "Go to sleep. You'll see me in the morning."
The next day was rainy and dark. Rain fell on the roof of the barn and dripped steadily from the eaves. Rain fell in the barnyard and ran in crooked courses down into the lane where thisles and pigweed grew. Rain spattered against Mrs.Zuckerman's kitchen windows and came gushing out of the downspouts. Rain fell on the backs of the sheep as they grazed in the meadow. When the sheep tired of standing in the rain, they walked slowly up the lane and into the fold.
Rain upset Wilbur's plans. Wilbur had planned to go out, this day, and dig a new hole in his yard. He had other plans, too. His plans for the day went something like this:
Breakfast at six-thirty. Skim milk, crusts, middlings, bits of doughnuts, wheat cakes with drops of maple syrup sticking to them, potato skins, leftover custard pudding with raisins, and bits of Shredded Wheat.
Breakfast would be finished at seven
From seven to eight, Wilbur planned to have a talk with Templeton, the rat that lived under his trough. Talking with Templeton was not the most interesting occupation in the wrold but it was better than nothing.
From eight to nine, Wilbur planned to take a nap outdoors in the sun.
From nine to eleven he planned to dig a hole, or trench, and possibly find something good to eat buried in the dirt.
From eleven to twelve he planned to stand still and watch flies on the boards, watch bees in the clover, and watch swallows in the air.
Twelve o'clock--lunchtime. Middlings, warm water, apple parings, meat gravy, carrot scrapings, meat scraps, stale hominy, and the wrapper off a package of cheese. Lunch would be over at one.
From one to two, Wilbur planned to sleep.
From two to three, he planned to scratch itchy places by rubbing against the fence.
From three to four, he planned to stand perfectly still and think of what it was like to be alive, and to wait for Fern.
At four would come supper. Skim milk, provender, leftover sandwich from Lurvy's lunchbox, prune skins, a morsel of this, a little more of this, a little more of that, piece of baked apple, a scrap of upsidedown cake.
Wilbur had gone to sleep thinking about these plans. He awoke at six and saw the rain, and it seemed as though he couldn't bear it.
"I get everything all beautifully planned out and it has to go and rain," he said.
For a while he stood gloomily indoors. Then he walked to the door and looked out. Drops of rain struck his face. His yard was cold and wet. His trough had an inch of rainwater in it. Templeton was nowhere to be seen.
"Are you out there, Templeton?" called Wilbur. There was no answer. Suddenly Wilbur felt lonely and friendless.
"One day just like another," he groaned. "I'm very young, I have no real friend here in the barn, it's going to rain all morning and all afternoon, and Fern won't come in such bad weather. Oh, honestly!" And Wilbur was crying again, for the second time in two days.
At six-thirty Wilbur heard the banging of a pail. Lurvy was standing outside in the rain, stirring up breakfast.
"C'mon, pig!" said Lurvy.
Wilbur did not budge. Lurvy dumped the slops, scraped the pail, and walked away. He noticed that something was wrong with the pig.
Wilbur didn't want food, he wanted love. He wanted a friend--someone who would play with him. He mentioned this to the goose, who was sitting quietly in a corner of the sheepfold.
"Will you come over and play with me?" he asked.
"Sorry, sonny, sorry," said the goose. "I'm sitting-sitting on my eggs. Eight of them. Got to keep them toasty-oasty-oasty warm. I have to stay right here, I'm no fibberty-ibberty-gibbet. I do not play when there are eggs to hatch. I'm expecting goslings."
"Well, I didn't think you were expecting wood-peckers," said Wilbur, bitterly.
Wilbur next tried one of the lambs.
"Will you please play with me?" he asked.
"Certainly not," said the lamb. "In the first place, I cannot get into your pen, as I am not old enough to jump over the fence. In the second place, I am not interested in pigs. Pigs mean less than nothing to me."
"What do you mean, less than nothing?" replied Wilbur. "I don't think there is any such things as less than nothing. Nothing is absolutely the limit of nothingness. It's the lowest you can go. It's the end of the line. How can something be less than nothing, then nothing would not be nothing, it would be something--even though it's just a very little bit of something. But if nothing is nothing, then nothing has nothing that is less than it is."
"Oh, be quiet!" said the lamb. "Go play by yourself! i don't play with pigs."
Sadly, Wilbur lay down and listened to the rain. Soon he saw the rat climbing down a slanting board that he used as a stairway.
"Will you play with me, Templeton?" asked Wilbur.
"Play?" said Templeton, twirling his whiskers. "Play? I hardly know the meaning of the word."
"Well," said Wilbur, "it means to have fun, to frolic, to run and skip and make merry."
"I never do those things if I can avoid them," replied the rat, sourly. "I prefer to spend my time eating, gnawing, spying, and hiding. I am a glutton but not a merrymaker. Right now I am on way to your trough to eat your breakfast, since you haven't got sense enough to eat it yourself." And Templeton, the rat, cept stealthily along the wall and disappeared into a private tunnel that he had dug between the door and the trough in Wilbur's yard. Templeton was a crafty rat, and he had things pretty much his own way. The tunnel was an example of his skill and cunning. The tunnel enabled him to get from the barn to his hiding place under the pig trough without coming out into the open. He had tunnels and runways all over Mr.Zuckerman's farm and could get from one place to another without being seen. Usually he slept during the daytime and was abroad only after dark.
Wilbur watched him disappear into his tunnel. In a moment he saw the rat's sharp nose poke out from underneath the wooden trough. Cautiously Templeton pulled himself up over the edge of the trough. This was almost more than Wilbur could stand: on this dreary, rainy day to see his breakfast being eaten by somebody else. He knew Templeton was getting soaked, out there in the pouring rain, but even that didn't comfort him. Friendless, dejected, and hungry, he threw himself down in the manure and sobbed.
Late that afternoon, Lurvy went to Mr.Zuckerman. "I think there's something wrong with that pig of yours. He hasn't touched his food."
"Give him two spoonfuls of sulphur and a little molassws," said Mr.Zuckerman.
Wilbur couldn't believe what was happening to him when Lurvy caught him and forced the medicine down his throat. This was certainly the worst day of his life. He didn't know whether he could endure the awful loneliness any more.
Darkness settled over everything. Soon there were only shadows and the noises of the sheep chewing their cuds, and occasionally the rattle of a cow-chain up overhead. You can imagine Wilbur's surprise when, out of the darkness, came a small voice he had never heard before. It sounded rather thin, but pleasant. "Do you want a friend, Wilbur?" it said. "I'll be a friend to you. I've watched you all day and I like you."
"But I can't see you," said Wilbur, jumping to his feet. "Where are you? And who are you?"
"I'm right up here," said the voice. "Go to sleep. You'll see me in the morning."
日本語訳のみです。
4.ひとりぼっち
翌日は、雨が降って、どんよりしていました。
納屋の屋根を雨が叩き、ひさしからは、ポタポタ雨だれが、落ちてきます。
納屋の前庭に降った雨は、曲がりくねりながら、アザミや、アカザの生えている小道まで流れていきました。
雨は、ザッカーマンさんの台所の窓を打ち、雨どいからもほとばしりでていました。
雨は、牧場で草を食べている羊たちの背中を濡らしました。羊たちは、雨にうんざりすると、小道を歩いてきて、屋根の下に入りました。
雨のせいで、ウィルバーの予定は、狂ってしまいました。今日は、外の囲いに出て、新しい穴を掘ろうと思っていたのです。
他にも、やりたいことがいろいろありました。
予定は、こうでした。
6時半に朝ごはん。
スキムミルク、パンの皮、ふすま飼料、ドーナツのかけら、メイプルシロップのついたホットケーキ、ジャガイモの皮、干しブドウ入りのプリンののこり、小麦のシリアルを食べる。
7時に朝ごはんを終える。7時から8時は、餌箱の下で暮しているねずみのテンプルトンとおしゃべりをする。
テンプルトンと話をするのは、世界一面白いとは、言えませんが、何もないよりはマシです。
8時~9時は、外で、日向ぼっこをしながら、一眠り。
9時から11時は、穴かみぞを掘って、ひょっとしたら出てくるかもしれない、おいしいものを探す。
11時~12時は、じっと立って板に止まるハエや、クローバーに止まる蜂や、空を飛ぶツバメを見る。
12時には、昼ごはん。フスマ飼料、お湯、りんごのくず、肉汁、にんじんの皮、肉の切れ端、硬くなったとうもろこし、チーズの外包みを食べる。昼ごはんは、1時に終わる。
1時~2時は、お昼寝。
2時~3時は、かゆいところを、壁にこすりつける。
3時~4時は、じっと立ち尽くして、生きているということは、どういうことかを考えながら、ファーンがくるのを待つ。
4時には、夕ご飯。スキムミルク、飼料、ラーヴィーのお弁当のサンドイッチの残り、プルーンの皮、いろんなものを、ひと口ふた口、ポテトフライ、マーマレードをちょっぴり、いろんなものを更にひと口ふた口、焼きりんごのかけら、アプサイドダウンケーキのくずを食べる。
ウィルバーは、前の晩にこうした予定をしっかり立てて寝たのです。
ところが、6時に目を覚ましてみると、雨が降っているではありませんか。何てことでしょう。
「せっかくきちんと予定を立てたのに、雨で台無しになってしまった。」
しばらくの間、ウィルバーは、堆肥の上で、しょんぼりしていました。
それから戸口までいって、外を見ました。それから、戸口まで行って、外を見ました。雨が顔に当たります。
前庭は、寒くてビショビショでした。
餌箱の底にも、2、3センチほど水がたまっています。
テンプルトンの姿も見えません。
「テンプルトンいるのかい?」ウィルバーは、声をかけました。答えはありません。急にウィルバーは、友達のいない寂しさを感じました。
「来る日も来る日も同じだ。」ウィルバーは、うめきました。「僕は、まだ小さいし、この納屋には、本当の友達はいないし、今日は、一日中雨が降り続きそうだし、こんなにひどい天気じゃ、ファーンも着てくれないだろうな。ああ、やんなっちゃうな!!」
ウィルバーは、昨日も泣いたばかりなのに、また泣き始めてしまいました。
6時半にもなると、バケツがガチャガチャ言う音が聞こえてきました。
ラーヴィーが雨の中に立って、朝ごはんの残飯を混ぜているのです。
「さぁ、食べろよ。」とラーヴィーは、言いました。
ウィルバーは、動きませんでした。ラーヴィーは、残飯を餌箱にあけ、バケツの底についているのをかき出すと、戻って行きましたが、豚の様子が、いつもと違うなと思っていました。
ウィルバーがほしいのは、食べ物ではなく、愛情だったのです。一緒に遊んでくれる友達がほしかったのです。羊の部屋で静かに座っているガチョウのおばさんに、ウィルバーは、聞きました。
「こっちにきて、一緒に遊んでくれない?」
「ごめんね坊や。ごめんね。」と、ガチョウのおばさんは、言いました。「私は、たまごを温めてるところなの。全部で8個もね。温かく温かくしておかなければならないんだよ。だから、ここでじっとしていなきゃね。遊んでる暇は、ないんだよ。たまごが孵るまではね。ガチョウの赤ちゃんが生まれるまでは。」
「そりゃ僕だって、キツツキの赤ちゃんが生まれてくるとは、思ってないけどね。」と、ウィルバーは、がっかりしながら言いました。
ウィルバーは子羊にも声をかけました。
「ねぇ僕と遊んでくれない?」
「嫌だね。それに第一僕は、そっちには行けないよ。まだ小さくて、塀を飛び越えることが、できないもの。それに、僕は、豚には、興味ないんだ。僕にとっちゃ豚なんて、ゼロ以下のつまらないものだね。」と子羊が言いました。
「ゼロ以下ってどういうことなの?」と、ウィルバーは、訊きました。
「僕、ゼロ以下のものなんて、無いと思うな。ゼロって、全くなんにもないことでしょ?それよりも下のものなんてないはずだよ。どうやったら、ゼロ以下になれるのさ?もし何にも無いよりももっと無いってことがあるなら、それなら元々は、何も無かったんでしょ?ほんのちょっぴりにしろ、何かは、あるってことでしょ?でも、本当に何も無いなら、それより少なくは、なりようが、無いもの。」
「あー、うるさいな!!! 1人で遊びなよ! 僕は、豚なんかと遊ばないんだから。」と子羊は、言いました。
ウィルバーは、しょんぼりと横になり、雨の音を聞いていました。
するとまもなく、ねずみが1匹階段代わりに使っている、斜めの板を降りてきました。
「ねぇ、テンプルトン。僕と遊ばない?」と、ウィルバーは、尋ねました。
「遊ぶだって?」と、テンプルトンは、髭をひねりながら、言いました。「遊ぶ? はてさてそれは、どういう意味だったかな?」
「あのね、遊ぶって、面白いことをしたり、うかれて騒いだり、走ったり、スキップしたり、陽気に楽しんだりすることだよ。」と、ウィルバーは言いました。
「俺は、そんなことは、しなくていいならしないね。」ネズミは、機嫌の悪そうな声で、こたえました。
「そんな時間があるなら、食べたり、かじったり、探したり、隠れたりしているほうが、よっぽどいいさ。俺は、うかれ屋じゃなくて、食いしん坊なんでね。たった今も、君の朝ごはんが入った餌箱まで、行くとこさ。君は、ぼんやりしてて、ご飯も食べないらしいからね。」
ネズミのテンプルトンは、壁をつたって、自分専用のトンネルの中に、姿を消しました。戸口と、ウィルバーに餌箱の間に、自分で掘ったトンネルです。テンプルトンは、なかなか頭の働くネズミで、自分勝手にいろいろな工夫をしていました。
このトンネルも、テンプルトンの悪知恵と腕のよさがあらわれた、いい例でした。
このトンネルをくぐれば、納屋からブタのえさ箱の下にあるかくれ家まで、誰にも見られずに行くことができました。テンプルトンは、ザッカーマン農場中にトンネルや通路を張り巡らせていて、姿を隠したまま、あっちこっちへ行くことができたのです。たいていテンプルトンは、昼間は寝ていて、暗くなってから外へ出てきました。
テンプルトンは、トンネルの中に消えたかと思うと、すぐにえさ箱のしたからとがった鼻先をのぞかせました。そして、用心深しながら箱のふちを登りました。ウィルバーは、もう我慢できませんでした。雨がしょぼしょぼふってるだけでもいやなのに、朝ごはんまで横取りされてしまったのです。どしゃぶりの雨に、テンプルトンはきっとずぶぬれになるでしょう。でも、そう思ったところで、なぐさめにはなりませんでした。おなかを空かせて、しょんぼりとした、友達のいないウィルバーは、堆肥に身を投げ出して、しくしく泣き出しました。
午後も遅くなってから、ラーヴィーがザッカーマンさんに言いました。
「あのブタは、どっか具合がわるいんじゃないですかね。なんにも食べてくれませんよ。」
「硫黄ふたさじに、ちょぴっと糖蜜をまぜて、のませてくれ。」と、ザッカーマンのおじさんは言いました。ラーヴィーにつかまって、むりやり薬をつっこまれたとき、ウィルバーはどうしてこんなにひどい目にあうのか、信じられませんでした。たしかに、生涯最悪の日に違いありません。ひとりぼっちの寂しさにも、これ以上もうたえられそうにありませんでした。
やがて、あたりはとっぷりと暗くなりました。もう羊の姿も影絵のようにしか見えず、聞こえるのは、羊が食べ戻しをするクチャクチャという音や、頭上でときどき雌牛のくさりがガチャガチャ鳴る音くらいでした。そんな暗闇の中から、これまできいたことのない小さな声が聞こえてきたのですから、ウィルバーがどんなにびっくりしたか、分かりますよね。かぼそいけれど、愛想のいい声でした。
「ねえ、ウィルバー、友達が欲しいの?わたし、お友達になってあげるわ。1日中見てたら、あなたのことすきになっちゃったの。」と、声の主は言いました。
ウィルバーはあわてて立ち上がって、いいました。
「でも、僕には君が見えないよ。どこにいるの?だれなの?」
「わたしは、上にいるの。おやすみなさい。朝になったら会いましょうね。」と、その声はこたえました。
翌日は、雨が降って、どんよりしていました。
納屋の屋根を雨が叩き、ひさしからは、ポタポタ雨だれが、落ちてきます。
納屋の前庭に降った雨は、曲がりくねりながら、アザミや、アカザの生えている小道まで流れていきました。
雨は、ザッカーマンさんの台所の窓を打ち、雨どいからもほとばしりでていました。
雨は、牧場で草を食べている羊たちの背中を濡らしました。羊たちは、雨にうんざりすると、小道を歩いてきて、屋根の下に入りました。
雨のせいで、ウィルバーの予定は、狂ってしまいました。今日は、外の囲いに出て、新しい穴を掘ろうと思っていたのです。
他にも、やりたいことがいろいろありました。
予定は、こうでした。
6時半に朝ごはん。
スキムミルク、パンの皮、ふすま飼料、ドーナツのかけら、メイプルシロップのついたホットケーキ、ジャガイモの皮、干しブドウ入りのプリンののこり、小麦のシリアルを食べる。
7時に朝ごはんを終える。7時から8時は、餌箱の下で暮しているねずみのテンプルトンとおしゃべりをする。
テンプルトンと話をするのは、世界一面白いとは、言えませんが、何もないよりはマシです。
8時~9時は、外で、日向ぼっこをしながら、一眠り。
9時から11時は、穴かみぞを掘って、ひょっとしたら出てくるかもしれない、おいしいものを探す。
11時~12時は、じっと立って板に止まるハエや、クローバーに止まる蜂や、空を飛ぶツバメを見る。
12時には、昼ごはん。フスマ飼料、お湯、りんごのくず、肉汁、にんじんの皮、肉の切れ端、硬くなったとうもろこし、チーズの外包みを食べる。昼ごはんは、1時に終わる。
1時~2時は、お昼寝。
2時~3時は、かゆいところを、壁にこすりつける。
3時~4時は、じっと立ち尽くして、生きているということは、どういうことかを考えながら、ファーンがくるのを待つ。
4時には、夕ご飯。スキムミルク、飼料、ラーヴィーのお弁当のサンドイッチの残り、プルーンの皮、いろんなものを、ひと口ふた口、ポテトフライ、マーマレードをちょっぴり、いろんなものを更にひと口ふた口、焼きりんごのかけら、アプサイドダウンケーキのくずを食べる。
ウィルバーは、前の晩にこうした予定をしっかり立てて寝たのです。
ところが、6時に目を覚ましてみると、雨が降っているではありませんか。何てことでしょう。
「せっかくきちんと予定を立てたのに、雨で台無しになってしまった。」
しばらくの間、ウィルバーは、堆肥の上で、しょんぼりしていました。
それから戸口までいって、外を見ました。それから、戸口まで行って、外を見ました。雨が顔に当たります。
前庭は、寒くてビショビショでした。
餌箱の底にも、2、3センチほど水がたまっています。
テンプルトンの姿も見えません。
「テンプルトンいるのかい?」ウィルバーは、声をかけました。答えはありません。急にウィルバーは、友達のいない寂しさを感じました。
「来る日も来る日も同じだ。」ウィルバーは、うめきました。「僕は、まだ小さいし、この納屋には、本当の友達はいないし、今日は、一日中雨が降り続きそうだし、こんなにひどい天気じゃ、ファーンも着てくれないだろうな。ああ、やんなっちゃうな!!」
ウィルバーは、昨日も泣いたばかりなのに、また泣き始めてしまいました。
6時半にもなると、バケツがガチャガチャ言う音が聞こえてきました。
ラーヴィーが雨の中に立って、朝ごはんの残飯を混ぜているのです。
「さぁ、食べろよ。」とラーヴィーは、言いました。
ウィルバーは、動きませんでした。ラーヴィーは、残飯を餌箱にあけ、バケツの底についているのをかき出すと、戻って行きましたが、豚の様子が、いつもと違うなと思っていました。
ウィルバーがほしいのは、食べ物ではなく、愛情だったのです。一緒に遊んでくれる友達がほしかったのです。羊の部屋で静かに座っているガチョウのおばさんに、ウィルバーは、聞きました。
「こっちにきて、一緒に遊んでくれない?」
「ごめんね坊や。ごめんね。」と、ガチョウのおばさんは、言いました。「私は、たまごを温めてるところなの。全部で8個もね。温かく温かくしておかなければならないんだよ。だから、ここでじっとしていなきゃね。遊んでる暇は、ないんだよ。たまごが孵るまではね。ガチョウの赤ちゃんが生まれるまでは。」
「そりゃ僕だって、キツツキの赤ちゃんが生まれてくるとは、思ってないけどね。」と、ウィルバーは、がっかりしながら言いました。
ウィルバーは子羊にも声をかけました。
「ねぇ僕と遊んでくれない?」
「嫌だね。それに第一僕は、そっちには行けないよ。まだ小さくて、塀を飛び越えることが、できないもの。それに、僕は、豚には、興味ないんだ。僕にとっちゃ豚なんて、ゼロ以下のつまらないものだね。」と子羊が言いました。
「ゼロ以下ってどういうことなの?」と、ウィルバーは、訊きました。
「僕、ゼロ以下のものなんて、無いと思うな。ゼロって、全くなんにもないことでしょ?それよりも下のものなんてないはずだよ。どうやったら、ゼロ以下になれるのさ?もし何にも無いよりももっと無いってことがあるなら、それなら元々は、何も無かったんでしょ?ほんのちょっぴりにしろ、何かは、あるってことでしょ?でも、本当に何も無いなら、それより少なくは、なりようが、無いもの。」
「あー、うるさいな!!! 1人で遊びなよ! 僕は、豚なんかと遊ばないんだから。」と子羊は、言いました。
ウィルバーは、しょんぼりと横になり、雨の音を聞いていました。
するとまもなく、ねずみが1匹階段代わりに使っている、斜めの板を降りてきました。
「ねぇ、テンプルトン。僕と遊ばない?」と、ウィルバーは、尋ねました。
「遊ぶだって?」と、テンプルトンは、髭をひねりながら、言いました。「遊ぶ? はてさてそれは、どういう意味だったかな?」
「あのね、遊ぶって、面白いことをしたり、うかれて騒いだり、走ったり、スキップしたり、陽気に楽しんだりすることだよ。」と、ウィルバーは言いました。
「俺は、そんなことは、しなくていいならしないね。」ネズミは、機嫌の悪そうな声で、こたえました。
「そんな時間があるなら、食べたり、かじったり、探したり、隠れたりしているほうが、よっぽどいいさ。俺は、うかれ屋じゃなくて、食いしん坊なんでね。たった今も、君の朝ごはんが入った餌箱まで、行くとこさ。君は、ぼんやりしてて、ご飯も食べないらしいからね。」
ネズミのテンプルトンは、壁をつたって、自分専用のトンネルの中に、姿を消しました。戸口と、ウィルバーに餌箱の間に、自分で掘ったトンネルです。テンプルトンは、なかなか頭の働くネズミで、自分勝手にいろいろな工夫をしていました。
このトンネルも、テンプルトンの悪知恵と腕のよさがあらわれた、いい例でした。
このトンネルをくぐれば、納屋からブタのえさ箱の下にあるかくれ家まで、誰にも見られずに行くことができました。テンプルトンは、ザッカーマン農場中にトンネルや通路を張り巡らせていて、姿を隠したまま、あっちこっちへ行くことができたのです。たいていテンプルトンは、昼間は寝ていて、暗くなってから外へ出てきました。
テンプルトンは、トンネルの中に消えたかと思うと、すぐにえさ箱のしたからとがった鼻先をのぞかせました。そして、用心深しながら箱のふちを登りました。ウィルバーは、もう我慢できませんでした。雨がしょぼしょぼふってるだけでもいやなのに、朝ごはんまで横取りされてしまったのです。どしゃぶりの雨に、テンプルトンはきっとずぶぬれになるでしょう。でも、そう思ったところで、なぐさめにはなりませんでした。おなかを空かせて、しょんぼりとした、友達のいないウィルバーは、堆肥に身を投げ出して、しくしく泣き出しました。
午後も遅くなってから、ラーヴィーがザッカーマンさんに言いました。
「あのブタは、どっか具合がわるいんじゃないですかね。なんにも食べてくれませんよ。」
「硫黄ふたさじに、ちょぴっと糖蜜をまぜて、のませてくれ。」と、ザッカーマンのおじさんは言いました。ラーヴィーにつかまって、むりやり薬をつっこまれたとき、ウィルバーはどうしてこんなにひどい目にあうのか、信じられませんでした。たしかに、生涯最悪の日に違いありません。ひとりぼっちの寂しさにも、これ以上もうたえられそうにありませんでした。
やがて、あたりはとっぷりと暗くなりました。もう羊の姿も影絵のようにしか見えず、聞こえるのは、羊が食べ戻しをするクチャクチャという音や、頭上でときどき雌牛のくさりがガチャガチャ鳴る音くらいでした。そんな暗闇の中から、これまできいたことのない小さな声が聞こえてきたのですから、ウィルバーがどんなにびっくりしたか、分かりますよね。かぼそいけれど、愛想のいい声でした。
「ねえ、ウィルバー、友達が欲しいの?わたし、お友達になってあげるわ。1日中見てたら、あなたのことすきになっちゃったの。」と、声の主は言いました。
ウィルバーはあわてて立ち上がって、いいました。
「でも、僕には君が見えないよ。どこにいるの?だれなの?」
「わたしは、上にいるの。おやすみなさい。朝になったら会いましょうね。」と、その声はこたえました。
Charlotte's Web 5