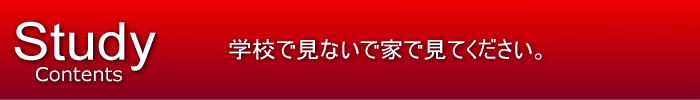クラウン1-Reading2 Menu
クラウン1-Reading2
Reading 2
HARRY POTTER and the Philosopher’s Stone
─The First Flying Lesson─
「ハリーポッターと賢者の石─飛行授業初日─」
1
その日の午後三時半、ハリー、ロン、クラスのみんなは初めての飛行の授業を受けるため正面玄関の階段を急いで下りていった。晴れた日で風が少しあった。他のクラスの生徒たちはすでに揃っていた。校庭には20本のほうきが数列に並んでいた。
マダム・フーチ先生が来た。先生は短い銀髪で鳥のような黄色い目をしていた。「ちょっと。みんな何をもたもたしているの?」先生は怒鳴った。「ほうきの横に立つ。さあさあ、急いで!」
ハリーは自分のほうきを見下ろした。古びたヤツだ。「ほうきに右手をかざしなさい。」フーチ先生が正面から声をかける。「『上がれ!』と言いなさい。」「上がれ!」みんなは叫んだ。ハリーのほうきはポンと彼の手に飛び上がったが、他に飛び上がったほうきは少なかった。ハーマイオニーのほうきは校庭を転げまわっただけだし、ネビルのなんかピクリともしなかった。たぶんほうきも馬と同じように相手が怖がっているのが分かるんだろう。つまりほうきはネビルが飛びたくない、地面から足を離したくないという彼の心の声を聞いたんだ。
それからフーチ先生はほうきの乗り方を教えた。行ったり来たりしながらほうきの握り方をやってみせた。先生がマルフォイにあなたはいつも間違うわね、と言うとハリーとロンはこっそり笑った。
「さあ、私が笛を吹いたら地面を蹴って離陸するのよ。思いっきり。」フーチ先生は言った。「ほうきは動かさないで。何フィートか上昇したら少し前傾姿勢をとってすぐに戻ってきなさい。いい?・・・3・・・2・・・」
しかしネビルは置いてけぼりを食うのを恐れるあまり、先生が笛を口につけもしないうちに地面を蹴り離陸してしまった。「君、戻りなさい!」先生は叫んだが、ネビルはビンから弾き飛んだコルク栓のように一直線に上昇していく─12フィート─20フィート。ハリーは見た。離陸するとき下を見下ろしたネビルの怯えて青ざめた顔を。彼が口を開けるのを。そして─ほうきから落下するのを。
ドスーン!大きな嫌な音がした。ネビルは芝の上にうつ伏せに倒れていた。ほうきはなお上へ上へと上昇していき、徐々に森の方へと離れていった。
フーチ先生はネビルを見ていた。先生の顔は彼の顔と同じくらい青ざめていた。「腕が折れてる。」先生は静かに言った。「しっかりなさい。大丈夫、起き上がって。」先生は他の生徒の方を向いて言った。「じゃあ、みんなは私がこの子を病院に連れて行く間じっとしてて。ほうきはこのままにしておきなさい。みんないい子だから。」
2
「ネビルの顔見たか?間抜けなヤツだぜ。」去り際にマルフォイが言った。彼は芝から何か拾い上げた。「これはあいつの婆さんがあいつに贈ったばかげた物じゃないか。」彼が太陽の光にかざすと思い出し玉はきらりと光った。
「それをこっちによこすんだ、マルフォイ。」ハリーが静かに言った。みんなおしゃべりを止め見守った。マルフォイはいやらしい笑みを浮かべた。「ネビルが後で見つけられるようにどっかに置いておいてやろうと思ってさ・・・木の上なんかどうだ?」
「こっちによこせ!」ハリーは声を上げた。しかしマルフォイはすぐさまほうきに飛び乗って離陸した。マルフォイはほんとに飛行がうまかった。それは確かだった。彼は一番大きな木のてっぺんまで飛んで行き呼びかけてきた。「ポッタァー、こーこまでおーいで!」
ハリーはほうきを手に取った。「ダメよ!」ハーマイオニーが叫んだ。「フーチ先生がじっとしてなさいって言ってたでしょう。私達みんなをごたごたに巻き込むつもり?」
3
ハリーは聞く耳を持たなかった。耳で血がドクン、ドクン、と脈打った。彼はほうきに飛び乗り、地面を強く蹴り、マルフォイを追って一気に離陸した。風を受けて髪がなびく。
─刹那、歓喜に包まれ彼は気付いた。教えられなくたってできることがあるんだ─こんなの簡単じゃん。すげえや!彼はもっと高く上がろうとほうきの柄を引き上へ向けた。下で女の子達が叫んでいる。ロンもはしゃいで大声を上げている。
彼は素早く方向転換し、マルフォイと向き合った。マルフォイはうろたえたように見えた。
「そいつをよこせ。でないとほうきから突き落すぞ!」ハリーは叫んだ。「へぇー、そうかい。」マルフォイは言いながら笑おうとしたが不安げな様子だった。
どういうわけだろう。ハリーは何をすればいいのか分かっていた。彼はほうきを両手でしっかりつかんで前に身をかがめた。するとほうきは弾かれたようにマルフォイめがけて突っ込んでいった。マルフォイは身をかわすのがやっとだった。ハリーは急回転してからほうきを安定させた。下では何人かが拍手をしている。
4
「ここまで助けに来てくれるヤツはいないぜ。」ハリーは叫んだ。マルフォイもちょうど同じことを思ったらしい。「じゃあ、取れるものなら取ってみろよ!」マルフォイはそう叫んでガラス玉を空中高く放り投げると、自分は地面へとすっ飛んでいった。ハリーはガラス玉が空中高くゆっくり上がり、それから落ちていくのを見た。
彼は前かがみになりほうきのへさきを下に向けた─と次の瞬間、彼は下へ下へとぐんぐんスピードを上げ、玉と競争していた─耳元の風を切る音、見守る人たちの歓声─彼は手を指し出し─地面まであと一フィートのところで玉を?まえ、ぎりぎりでほうきを水平に戻し、無事、思い出し玉を手にそっと芝生に着地した。
「ハリィーポッタァァアアー!!」
彼はがっくり来た。とても厄介なことになったのだ。マクゴナガル先生が駆け寄って来た。彼は立ち上がったものの足元がおぼつかなかった。
「とんでもないこと─私がホグワーツにいるあいだにこんなことが─」マクゴナガル先生はショックのあまりろくに口もきけなかった。怒ったようにメガネがギラリと光った。「よくもまあ、あなたって人は!─首の骨を折るところだったんですよ。ポッター、さあついてらっしゃい。」
ハリーが向きを変えたとき、マルフォイが意地悪な笑みを浮かべているのが見えた。僕は退学しなければならなくなるのだろう。彼には分かっていた。
クラウン1 Top